教育課程論の教科書
2017年に学習指導要領が改訂され、「社会に開かれた教育課程」や「カリキュラム・マネジメント」といった用語が全面的に展開され、「教育課程」を扱う教科書は従来の在り方から抜本的に変化することを余儀なくされている。また「主体的・対話的で深い学び」という概念によって教育課程論と教育方法論が原理的に結びついたため、「教育課程」を扱う教科書でも教育方法論に触れざるを得なくなっている。さらに「指導と評価の一体化」により、「評価」に対する記述も厚くしていく必要がある。
それぞれの教科書が新学習指導要領にどのように対応しようとしているのか、確認しておきたい。
 ■田中耕治・水原克敏・三石初雄・西岡加名恵『新しい時代の教育課程 第4版』有斐閣、2018年
■田中耕治・水原克敏・三石初雄・西岡加名恵『新しい時代の教育課程 第4版』有斐閣、2018年
【特徴】2005年に初版が発行され、教育課程論の理論的な背景を一通り押さえられる定番教科書の一つではあるが、学習指導要領改訂を受けた2018年第4版では大幅な書き直しが行なわれている。「第2章 現代日本の教育課程の歩み」では「特別の教科道徳」や「主体的・対話的で深い学び」に関する記述が加わった。さらに「カリキュラム・マネジメント」が新たに章立てられている。戦前戦後のカリキュラム変遷に詳しい他、研究開発学校の具体的な取り組みや諸外国の教育課程が紹介されているのも一つの特徴。
【感想】理論的にも歴史的にも、そこそこ内容は盛りだくさんで、教職課程の初学者は読みこなすのが大変かもしれない。まあ、このくらいはしっかり読んで勉強して欲しいところではある。「社会に開かれた教育課程」という今時学習指導要領の理念が本書では前面に出てきていないのは、編集方針によるところかどうか、多少気になるところではある。
 ■細尾萌子・田中耕治編著『新しい教職教育講座教職教育編6 教育課程・教育評価』ミネルヴァ書房、2018年
■細尾萌子・田中耕治編著『新しい教職教育講座教職教育編6 教育課程・教育評価』ミネルヴァ書房、2018年
【特徴】タイトルに「教育課程」と並んで「教育評価」と銘打ってあるとおり、「指導と評価の一体化」の流れに沿って、教育評価と一体化した教育課程論を目指している。戦前の教育課程や海外動向をばっさり切り落として、カリキュラム評価や学校評価に関する記述が手厚くなっている。
【感想】やはり「社会に開かれた教育課程」という観点の記述が薄いところが気になるところではある。特別活動や総合的な学習の時間の構想について最新改訂と絡めて言及されてはいるのだが、内在的なカリキュラム論として展開されるわけではない。編集方針なのか、単に展開しにくいだけか、どうか。
 ■松尾知明『新版 教育課程・方法論 コンピテンシーを育てる学びのデザイン』学文社、2018年
■松尾知明『新版 教育課程・方法論 コンピテンシーを育てる学びのデザイン』学文社、2018年
【特徴】従来は「教育課程」と「教育方法」を一緒に扱う教科書はあまりなかったように思うのだが、今時学習指導要領改訂は「過程を重視した学び」や「指導と評価の一体化」の掛け声に象徴的なように、教育課程と教育方法を一体化した記述となっている。それを受け、本書は「教育課程=カリキュラム・マネジメント」と「教育方法=主体的・対話的で深い学び」を一体化し、「コンテンツからコンピテンシーへの転換」を意識した記述となっている。
【感想】「教育課程」と「教育方法」を一体化して扱うことで学習指導要領が目指す教育の姿の全体をカバーしてはいるのだが、キーワードを表面的になぞるだけで、教育学的な本質に触れているかどうかについては気にかかるところ。少々論理的な記述内容が薄いような気はするが、一人の著者で膨大な領域をカバーしようとするとこうならざるをえないか。
教育原理の教科書
 ■木村元・汐見稔幸『アクティベート教育学01教育原理』ミネルヴァ書房、2020年
■木村元・汐見稔幸『アクティベート教育学01教育原理』ミネルヴァ書房、2020年
【特徴】西洋教育思想史の基本的事項について手堅く抑えつつも、近代教育(学校教育というシステム)の賞味期限切れという喫緊の事態に大きな危機感を抱いて、「教育」という概念そのものを根本的に捉えなおそうという意図で貫かれている。そういう意味では、教員採用試験で必要とされる知識の範囲を大きく超えているわけだが、これから教育という仕事に参入しようという人(教員に限らない)にはぜひ目を通してほしい充実した内容になっている。
【感想】さすが木村先生と汐見先生の名前が編著としてクレジットされているだけあって、基本的な知識や最新のトピックを着実に押さえながらも、読者に本質的な思考を促すような挑発的な仕掛けにも満ちている。教育原理の教科書は、「教育原理」と名乗るからにはこうありたいものだ。
 ■佐々木司・熊井将太編著『やさしく学ぶ教育原理』ミネルヴァ書房、2018年
■佐々木司・熊井将太編著『やさしく学ぶ教育原理』ミネルヴァ書房、2018年
【特徴】平易な言葉で、分かりやすく書かれている。養護教諭課程でも使用されることを想定しており、教育の他に「看護」に関する記述が厚い。「働き方改革」や人工知能など最新トピックにも言及されている他、批判的思考を養うための配慮もされている。
【感想】平易なぶん密度は薄めになっているが、本質的なところを外しているわけではなく、コンパクトに要点がまとまっているように思う。誤字・脱字等も見当たらず、丁寧に作られているような印象を持った。初学者には入りやすいのではないか。とはいえ、教員採用試験に対応しようと思ったら、もうちょっと密度が高い知識が必要になってくるだろうとは思ってしまう。ここを入口にして、教育課程論や教師論等の詳細に入って行くと良いのかなと思う。
【特徴】典型的な教科書とは趣が異なって、全編が著者の言葉で語られている。トピックの解説に終始せず、著者の教育学的観点(人間の学としての教育学)が全面に打ち出されており、教科書的な読み方を超えて、読み物としても面白く読めると思う。ただしそのぶん、個々の人名や語句に対する解説は省かれており、引用のスタイルも学術的で、初歩的な知識を習得し終えている中級者向けか。
【感想】教育人間学に関するトピックでは原典を直接参照しており、手厚くて面白く読めるが、その一方で日本や東洋の教育に関する記述(たとえば儒教)には二次的な引用が多く、多少食い足りない感じはする。一人でオールレンジをカバーする教科書を執筆するのは大変である。
とはいうものの、読み物として体系的にまとまっていて面白いので、初歩的な人名や語句を覚えたばかりの学部生に読ませて総合的な概念の定着を図るためには優れた本じゃないだろうか。ありそうで実はあまりないタイプの本のような気がする。
教育制度・教育法・教育行政の教科書
2006年の教育基本法改訂以後、教育委員会制度の改正や教育機会確保法制定、義務教育学校の登場、教員養成制度改革などなど、教育制度はめまぐるしく変化している。教育制度・教育法・教育行政に関わる教科書は、最新のものでないと用をなさないようになっている。5年前のものは、もう古い。
 ■川口洋誉・古里貴士・中山弘之『新版 未来を創る教育制度論』北樹出版、新版2020年
■川口洋誉・古里貴士・中山弘之『新版 未来を創る教育制度論』北樹出版、新版2020年
【特徴】「子どもの学習権を保障する」というコンセプトで中心的となる柱をがっちりと固めつつ、教育制度に関わる領域を満遍なく網羅していて、全体的な統一度・完成度が高い。コラム等で具体的な判例や実践例が数多く紹介されており、説得力も高い。
【感想】筋が一本通っていて、とても読みやすく、分かりやすい。好感度が高い。単なる知識ではなく、自分なりに物事を考えるための「観点」を得ることに意味がある。「子どもの学習権」という観点を身につけると、教育に関する様々な事象の問題がクリアに見通せるようになる。
 河野和清『現代教育の制度と行政(改訂版)』福村出版、2017年
河野和清『現代教育の制度と行政(改訂版)』福村出版、2017年
【特徴】一歩引いたような地点から、教育制度・行政を概観するようなスタイル。タイトルに「現代」とついているように、ポスト近代の流れを意識したような構成になっている。そのせいで「未完の近代プロジェクト」としての「子どもの学習権」は前面に打ち出されない。ここは好き嫌いが分かれるところなのだろう。
【感想】「理念」としての教育制度・行政を考えるのではなく、現実問題としての教育制度・行政をまず知るという点では良いのかもしれない。特に臨時教育審議会以後の教育制度改革について記述が厚かったように思った。
教育方法の教科書
2017年度版学習指導要領に登場した「主体的・対話的で深い学び」という言葉によって、それ以前の教科書は基本的に用なしになっている。さらにGIGAスクール構想や令和の日本型学校教育によって、いま出回っている教科書もすぐに役立たずになってしまいそうだ。
 ■稲垣忠編著『教育の方法と技術Ver.2 IDとICTでつくる主体的・対話的で深い学び』北大路書房、2022年
■稲垣忠編著『教育の方法と技術Ver.2 IDとICTでつくる主体的・対話的で深い学び』北大路書房、2022年
【特徴】「主体的・対話的で深い学び」を実現するための具体的な方法が、豊富な理論を背景に説明されていて、実践に活用できるように思わせる説得力がある。またGIGAスクール構想や令和の日本型学校教育の方針も視野に入っていて、ICTを活用した個別最適化についても配慮している。
【感想】子ども主体の方法が貫かれていて、ひと世代前の「教育方法論」とはずいぶん雰囲気が異なるような印象を受けた。
教育史の教科書
 ■山本正身『日本教育史:教育の「今」を歴史から考える』慶応義塾大学出版会、2014年
■山本正身『日本教育史:教育の「今」を歴史から考える』慶応義塾大学出版会、2014年
【特徴】古代・中世の教育的事項にはあまりページを割いていないが、近代以降の記述が厚く、特に戦後教育史に関する分析が鋭い。
【感想】一人で通史を書くのはほとんどドン・キホーテ的な蛮勇に類するものになってしまっているが、本書は誤字脱字も見当たらず、教員採用試験に登場するような基本的事項は一通り網羅した上で、全体を貫く構想にも説得力があって、学生にも安心して勧められるように思う。個人的には、特に戦後教育史に対する見方を共有していて、心強い。
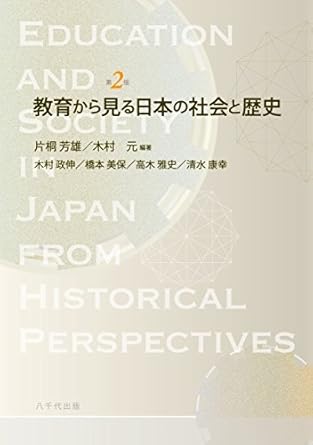 ■片桐芳雄・木村元編著/木村政伸・橋本美保・高木雅史・清水康幸著『教育から見る日本の社会と歴史』八千代出版、第二刷2017年
■片桐芳雄・木村元編著/木村政伸・橋本美保・高木雅史・清水康幸著『教育から見る日本の社会と歴史』八千代出版、第二刷2017年
【特徴】日本教育史の通史。古代から現代まで過不足なく網羅している。当代一流の執筆陣で、安心して読める。第二刷で、最新の状況にも対応している。
【感想】単なる固有名詞の羅列ではなく、歴史の原則を踏まえた説明がしっかりしている。そのぶん、単に教員採用試験合格を目指すレベルの層には難しいかもしれないが、これくらいは読みこなしてもらいたいところ。

 ■寺下明『教育原理 第2版』ミネルヴァ書房、2012年
■寺下明『教育原理 第2版』ミネルヴァ書房、2012年


