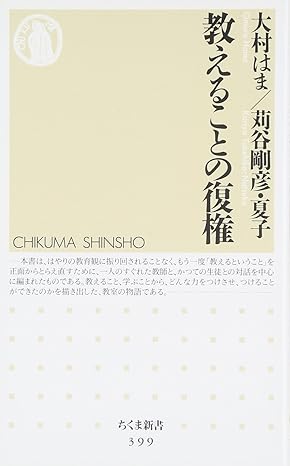
【要約】大村はまの国語教室で実際に受けた授業を振り返り、さらに教育学的に考察を加え、「教えること」の重要性を再確認します。近年のいわゆる「新学力観」によって、教えることを躊躇する教師が増えましたが、とんでもない間違いです。一方的な詰め込みも、ただの放任も、どちらも教育の本質を見失っています。
しっかりと「教える」ためには、目の前の一人一人の子どもの個性を理解し、それぞれに適した教材を用意し、「てびき」を作って「考える」ためのきっかけをお膳立てし、それぞれの躓きを把握するために適切な評価を行ない、さりげなく背中を押すことです。教師は楽をしてはいけません。
【感想】なかなか凄い組み合わせの本だ。奇跡的な繋がりと言ってもいいのかもしれない。(まあ、教育界隈にいる人じゃないと、どこがどう奇跡的なのか分からないとは思うけれども……)
著者の組み合わせから受ける期待に違わず、中身もエキサイティングであった。昨今(といってももう15年前か)の「新学力観」に真っ向から立ち向かい、実践面と理論面の両方からばったばったと薙ぎ倒していく様は、かなり痛快だ。まあその痛快さは、ブーメランのように自分自身に突き刺さってくることになるのだけれども。
ともかく「教育の本質」を考える上で、侮れない本であることは間違いないように思う。私自身も、いろいろ反省しなければならない。
「「生きる力」を唱える教育学者の授業が、案外と学生たちに考える力をつけさせない、退屈で一方的な授業にとどまっているという皮肉な例も少なくないようだ。」209頁
あいたたた。
【言質】
「個性」とか「自己実現」に関する多角的な言質を得た。
大村:損なわれない。」124頁
「教育関係の審議会の答申などでも、教育は子どもたちの「自己実現」をめざすものだとか、教師の役割は、生徒の「自己実現」を支援するといったような文章が登場することが多い。」201頁
「これと似た例に、「個性」がある。教育の世界で多用される個性ということばは、実に多義的に使われている。いろいろな意味を帯びているのに、それでも会話が成立してしまう。ちょっと考えてみると、不思議ではないか。」204頁
苅谷は、「自己実現」や「個性」という言葉が、内実を伴わず、イメージと雰囲気で流通している様を浮き彫りにする。まあ、言うとおりなんだろう。が、個人的には、それを現象として認めた上で、さらに一歩本質的に先を行きたい気分ではあるのだった。
【個人的研究のための備忘録】
「学力」に関する言及も、メモしておく。もちろん、新学力観を批判する文脈である。




