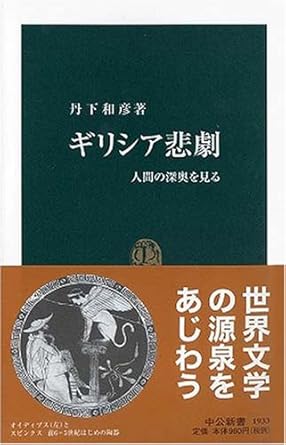■新松戸キャンパス 12/21(金)
前回のおさらい
・道徳の教科化
教育行政:教育委員会制度
教育委員会は、都道府県及び市町村等に置かれる合議制の執行機関であり、生涯学習・教育・文化・スポーツ等の幅広い施策を展開します。
1948年「教育委員会法」:旧教育基本法第10条に基づいて教育委員会を創設。
1956年「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」:公選制から任命制への転換。
2015年「改正地方教育行政法」:教育委員長を廃止して事務を教育長に一本化。首長の主催による「総合教育会議」の設置を義務化。
旧教育基本法第十条(教育行政) 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。
2教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。
教育委員会制度の概要
(1)政治的中立性の確保→首長からの独立性。
行政委員会の一つとして、独立した機関を置き、教育行政を担当させることにより、首長への権限の集中を防止し、中立的・専門的な行政運営を担保します。
(2)継続性、安定性の確保。
教育は、子どもの健全な成長発達のため、学習期間を通じて一貫した方針の下、安定的に行われることが必要です。
また、教育は、結果が出るまで時間がかかり、その結果も把握しにくい特性から、学校運営の方針変更などの改革・改善は漸進的なものであることが必要です。
→合議制:多様な属性を持った複数の委員による合議により、様々な意見や立場を集約した中立的な意思決定を行います。
(3)地域住民の意向の反映→レイマンコントロール
住民が専門的な行政官で構成される事務局を指揮監督する、いわゆるレイマンコントロールの仕組みにより、専門家の判断のみによらない、広く地域住民の意向を反映した教育行政を実現します。
教育委員会制度の仕組み
・教育委員会は、地域の学校教育、社会教育、文化、スポーツ等に関する事務を担当する機関として、全ての都道府県及び市町村等に設置します。
・首長から独立した行政委員会として位置付けられます。
・教育委員会は、教育行政における重要事項や基本方針を決定し、それに基づいて教育長が具体の事務を執行します。
・月1~2回の定例会のほか、臨時会や非公式の協議会を開催します。
・教育長及び教育委員は、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命します。任期は教育長は3年、教育委員は4年で、再任可です。
・教育委員は原則4人です。ただし条例によって、都道府県・政令指定都市は5人以上、町村は2人以上にすることが可能です。
教育委員会の事務
(1)学校教育の振興
学校の設置管理、教職員の人事及び研修、児童・生徒の就学及び学校の組織編成、校舎等の施設・設備の整備、教科書その他の教材の取り扱いに関する事務の処理。
(2)生涯学習・社会教育の振興
生涯学習・社会教育事業の実施、公民館・図書館・博物館等の設置管理、社会教育関係団体等に対する指導・助言・援助
(3)芸術文化の振興・文化財の保護
文化財の保存・活用、文化施設の設置運営、文化事業の実施
(4)スポーツの振興
指導者の育成・確保、体育館・陸上競技場等スポーツ施設の設置運営、スポーツ事業の実施、スポーツ情報の提供
総合教育会議と教育振興基本計画
・すべての地方公共団体に「総合教育会議」を設置します。←首長のリーダーシップが強化されると予測されています。
・教育に関する「大綱」を首長が策定します。←エビデンス(客観的な根拠)に基づいた着実な施策(PDCAサイクル)が求められています。
第三章 教育行政
(教育行政)
第十六条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。
(教育振興基本計画)
第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。
第3期教育振興基本計画
・内閣が2018年度~2022年度の教育方針を閣議決定(2018年6月)しました。生涯にわたる一人一人の「可能性」と「チャンス」を最大化することを重点事項としました。
(1)夢と志を持ち、可能性に挑戦するために必要となる力を育成する。
(2)社会の持続的な発展を牽引するための多様な力を育成する。
(3)生涯学び、活躍できる環境を整える。
(4)誰もが社会の担い手となるための学びのセーフティネットを構築する。
(5)教育政策推進のための基盤を整備する。
都道府県・市町村の教育振興基本計画
・教員採用試験に決定的に重要なので、志望する自治体の計画は読み込んでおくこと。
復習
・「教育行政」という言葉の中身について、「教育委員会」の具体的な仕組みとともに理解しよう。

【要約】演劇とは時代の雰囲気を反映する総合芸術であって、観客の反応を抜きにして語ることはできません。ローマ喜劇とは、外来のギリシア演劇を受容して独自の展開を見せた総合的な芸術運動と把握して初めて理解できるものであって、単にテキストだけを解釈するのでは見失うものが多いでしょう。具体的には、たとえば「プロロゴス」の在り方を見ることによって、ローマ時代の芸術運動の一端を伺うことができます。そしてその時代に寄り添う芸術運動の在り方は、まさに日本の演劇運動を理解する上での参照軸となり得るものです。