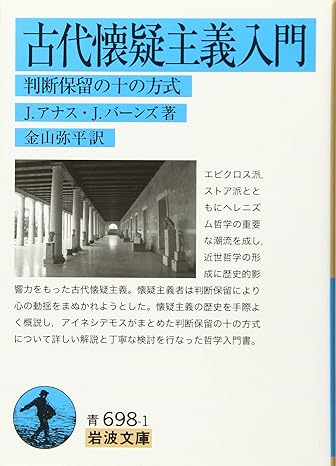【要約】幸せに生きましょう。そのために、自分の力の範囲でできることと、できないことを、明確に区別しましょう。自分の力が及ばないことに執着すると、必ず不幸になります。たとえば、財産、健康、家族、生死といったものは、自分の力ではどうにもなりません。自分の力が及ばない不運が人生に降りかかってきたときは、「ふーん」「ですよね」とでも思いましょう。それは私たちの善悪とは何の関係もありませんから、特に気にする必要はありません。不幸とは、不運なことではなく、不運を気にかける心が原因で陥ってしまうものです。
【要約】幸せに生きましょう。そのために、自分の力の範囲でできることと、できないことを、明確に区別しましょう。自分の力が及ばないことに執着すると、必ず不幸になります。たとえば、財産、健康、家族、生死といったものは、自分の力ではどうにもなりません。自分の力が及ばない不運が人生に降りかかってきたときは、「ふーん」「ですよね」とでも思いましょう。それは私たちの善悪とは何の関係もありませんから、特に気にする必要はありません。不幸とは、不運なことではなく、不運を気にかける心が原因で陥ってしまうものです。
一方、自分の力が及ぶものに関しては、力の限り頑張りましょう。その価値はありますし、トレーニングすれば誰にでもできるようになります。すぐやりましょう。自分の力が及ぶ対象とは、自分の心に浮かび上がってくる「心像」です。何でも自分の思い通りになります。心像を思うがままにコントロールすることで、私たちは幸せになることができます。そんなわけで、哲学とは、心像を把握し、容認し、判断するための知恵です。
 【感想】後期ストア派を代表する哲学者エピクテトスの言葉を弟子が書き記した『語録』と、思想の要点をまとめた『要録』が収められている。文章量は多いけれども、言っている内容そのものはかなり単純で、同じ趣旨を何度も繰り返している。いつもいつも初心者が同じような初歩的な質問をしてくるから、何度も何度も基礎・基本を確認している、ということなのだろう。というわけで、ストア派の考え方の基礎・基本がよく理解できる本になっている。
【感想】後期ストア派を代表する哲学者エピクテトスの言葉を弟子が書き記した『語録』と、思想の要点をまとめた『要録』が収められている。文章量は多いけれども、言っている内容そのものはかなり単純で、同じ趣旨を何度も繰り返している。いつもいつも初心者が同じような初歩的な質問をしてくるから、何度も何度も基礎・基本を確認している、ということなのだろう。というわけで、ストア派の考え方の基礎・基本がよく理解できる本になっている。
ところで、本書に示されているエピクテトスの考え方は、ひろゆきの考え方とよく似ている、と思う。自分の力が及ばないことには関心を持たず、他人の意見や感情などどうでもよく、見栄や外聞などに気を揉むことなく、できないことができるようになるような努力などせず、ただただ自分のやりたいこと=やれることに力を傾けながら、生活の静穏と安寧を心がけ、ひたすら幸福を噛みしめる、という観点で。という私の直観が正しいとして、もしも仮に今人々がひろゆきの言動に説得力を感じているとすれば、本質的には、実はストア派の考え方に人々が共振している、ということだ。その仮説を傍証するかどうかは分からないが、今まさにストア派の需要が広く生じている。エピクテトスを扱った一般書が立て続けに出版されていたりもするし、セネカ(同じくストア派の思想家)が脚光を浴びていたりもする。
思い返してみると、エピクテトスが活躍していた帝政期ローマの状況と、現代日本の状況は、「行き詰まり感」という意味において、よく似ている気もする。都市の消費文化が頽廃を極めて拝金主義が横行し、地域格差や経済格差が埋め合わせ不可能なところまで拡大し、人生がうまくいくかどうかは「〇〇ガチャ」で決まり、人々を束ねる共通の目的が見失われ、古くからの共同体が機能しなくなり、人々は剥き出しの「個」として自己責任の名の元に放り出されている。そんな行き詰まり感。そんな真綿に首を絞められて窒息死させられそうな状況で、それでもなんとかサバイバルしようと手を伸ばしたときに、指先にひっかかるのがストア派であり、ひろゆきである、ということなのかもしれない。まあ、おそらく悪いことではない。どのみち、私たちは、何らかの手段で以て、サバイバルしなければならない。
【今後の研究のための備忘録】
本書には「教育」という言葉がよく出てくる。ただしその中身は、いま我々が考える教育とはずいぶん趣を異にする。
「概してあらゆる能力は教育がなく力が弱い人がもつと、それによって自惚れ尊大になってしまう怖れがあるのだ。」1-8
「人は自分になにか優れた点があるとき、あるいはないのにあると思っているとき、教育を受けていなければ、必ずそのために自惚れることになる。」1-19
「むしろ、教育を受けるというのは、それぞれの物事が起きるがままに起きるように願うことを学ぶということなのである。」1-12
「とすると、教育を受けるというのはどのようなことなのか。それは、自然な先取観念を個々のものに自然本性にかなうようにあてはめ、さらには、物事のうち、あるものはわれわれの力の及ぶものであり、あるものは及ばないものであるということ、つまり意志や意志に基づく行為はわれわれの力の及ぶものであるが、身体、身体の一部、所有物、両親、兄弟、子供、祖国、要するに社会的なものはわれわれの力の及ばないものであるということだが、そのような区別をするしかたを学ぶことである。」1-22
「真の意味で教育を受けた人にとって最もうるわしく最もふさわしいものは、平静であること、恐れのないこと、自由である。自由人だけが教育を受けることを許されるという多くの人たちの言葉を信じるべきではなく、教育を受けた者だけが自由であるという哲学者たちの言葉を信じるべきである。」2-1
「教育を受けるというのは、自分に関わるものと他人に関わるものとの区別を学ぶことだ。」4-5
「自分がうまくいっていないことで他人を非難するのは、教育を受けていない人がすることである。むしろ、教育を受け始めた人なら自分を非難するし、教育を受けてしまった人なら他人も自分も非難しないであろう。」『要録』5
つまりエピクテトスが言う「教育」とは、ストア派の考え方を本質的に理解して実生活で実践できるようになることを指している。単に知識や技術を身につけることはまったく意味していない。(このあたり、原語を踏まえて研究を深めておく意味がありそうだ。)
それを踏まえると、やたらと「子供」を例に出してくることもおもしろい。エピクテトスにとって、子どもは単に「教育」を受けていない未熟なものに過ぎない。そこに発達可能性の一端も見ることはない。
「何のためにか。自分が納得するだけで十分ではないのか。子供たちがやって来て、手をたたきながら「サトゥルナリア祭おめでとうございます」と言っているのに、彼らに「それはめでたくないよ」などと答えるだろうか。けっしてそんなことはしない。むしろ、自分たちも手をたたくのだ。だから、君もだれかの考えを変えることができなければ、その人を子供だと思って、一緒に手をたたけばよい。そんな気持ちにならなければ、それからは黙っていることだ。」1-29
「だが、ソクラテスはそれらのものをうまくお化けと呼んでいた。つまり、経験がないために子供たちにはその仮面が恐ろしくて怖いもののようにみえるように、われわれもまた、子供たちがお化けに対するのと少しも変わることなく、それらの事柄に対して同様の感情を抱くわけである。というのも、子供とは何であるか。無知である。子供とは何であるのか。学びの欠如である。子供が知っているところでは、彼らもわれわれと変わるところがない。」2-1
「そうしないと、子供に戻って、ある時はレスリングで、ある時は一騎打ちをして遊んだり、ある時は喇叭を吹いたり、さらにみたり驚いたりしたことで悲劇の芝居ごっこをする。そのようにして、君もある時は競技者になり、ある時は剣闘士になり、さらに哲学者に、またさらには弁論家になるけれども、本気ではなににもなっていない。」3-15
「子供のように、今が哲学者だが、後で税務官に、その次には弁論家に、またその次は皇帝任命の太守になりたがってはならない。」3-15
「例えば、われわれがまだ子供だった頃、口を開けて歩いていてなにかに躓いたりすると、乳母はわれわれを叱らずに、その石を叩いたものだった。いったい石は何をしたというのか。君の子供の馬鹿な行動のために、石はよけねばならなかったのか。さらに、われわれが風呂から帰ってきたときに食べるものがないと、子守役の召使はわれわれの欲求を抑えてかかるのではなく、代わりに料理係を打ちすえる。ねえ君、われわれは君を料理係の守役に決めたのではなく、われわれの子供の守役にしたのだから、子供をしつけて、子供のためになることをすればいいのだ。
このように、われわれは成長しても子供のようにみえる。音楽を知らない人は音楽において子供であり、読み書きを知らない人は読み書きにおいて子供であり、教育のない人は人生において子供であるからだ。」3-19
「そんなふうに幼稚で子供っぽくふるまうのをやめる気はまったくないのか。子供のようにふるまう人が歳を重ねると、それだけ滑稽になるということが分からないのか。」3-24
「それでは、子供を護衛兵がついている僭主のところに連れていっても、怖がらないのはどうしてだろうか。子供が護衛兵を知らないからか。」4-7
「だれかがイチジクやアーモンドを撒くと、子供たちが奪い合って、互いにけんかを始める。だが、大人たちはつまらないことだと思うから、そんなことはしない。しかし、だれかが陶片を撒いたら、子供たちも奪い合うことはない。地方総督の仕事が配分される。子供たちは黙ってみているだろう。お金が配分される。子供たちは黙ってみているだろう。将軍や執政官の職が配分される。子供たちに奪い合いをさせるがよい。」4-7
徹頭徹尾、子どもを未熟で無知でくだらないことをする取るに足らない存在だと見なしているのであった。まあ、エピクテトスに限らず、西洋の古代から中世にかけてあらゆる人が同様の見解を示しているわけではあるが、分かりやすく表現されたサンプルということでは、けっこう貴重かもしれない。
それから、「有機体」思想に関するおもしろい表現もサンプリングしておきたい。
「つまり、足については清潔であることが自然本性にかなっていると私は言うだろうが、もし君が足を足として認め、ほかから切り離されたものではないと考えるならば、それを泥の中に突っ込んだり、茨を踏んだり、時には全身のために切り離したりすることがふさわしく、もしそうでなければ、もはや足でないことになるだろう。われわれについても、なにかそんなふうに考えねばならない。君は何であるのか。人間である。もし君が自分をほかから切り離されたものと考えるならば、老年まで生き、富を蓄え、健康であることが自然本性にかなっている。だが、自分を人間として、つまりある全体の一部だと考えるならば、その全体のために時には病気をし、時には航海して危険を冒し、時には困窮し、また寿命の前に死ぬこともふさわしくなる。そうすると、なぜ君は腹を立てているのか。切り離された足がもはや足でないように、君も人間でなくなるということに気付かないのか。というのは、人間とは何であるのか。それは国家の一部である。第一には、人間と神々とからなる国家の、その次には、これに最も近似していると言われているもので、全体的な国家のなにか小さな模倣である国家の一部である。」2-5
「君は野獣と区別され、家畜と区別される。それに加えて、君は宇宙の市民であり、その一部であり、奉仕するものではなく指図するもののひとつである。なぜなら、君は神の支配を理解し、それから結果することを考慮することができるからである。ところで、市民の務めとは何であるのか。市民の務めは、どんなことでも私的な利益に関わるものとみなさず、どんなことについてもほかから切り離されたものと考えず、かりに手足が理性をもち、自然の仕組みを理解しているならば、全体に関わること以外のことに衝動を感じたり、欲求したりすることはけっしてないであろうが、それと同じように行動することである。」「それが全体の秩序から分かれて配分されたこと、全体は部分よりも、国家は市民よりも優れたものであることに気づいているからだ。」2-10
もちろんこういう有機体思想は、既にプラトン『国家』の中に色濃く見られる(というか主題そのもの)であって、エピクテトスやストア派の専売特許というわけではない。後にキリスト教思想においても「神の国」における一体化が強調されていくことにもなるだろうし、ヘーゲルは「胃」によるメタファーを好んで使うことになるだろう。ここでは具体的に「足」や「手」というメタファーが使われているということに注目しておきたい。
さてまたさらに、「人格」(ギリシア語でプロポーソン)の用例サンプルを得た。
「しかし、理にかなうこと、かなわないことを判別するために、われわれは外的なものの価値だけでなく、それぞれが自分の人格に関わるものの価値も用いている。」1-2
「というのは、一度でもそのようなことを考えたり、外的なものの価値を計算したりした者は、自分自身の人格を忘れてしまった者とほとんど変わらないからだ。」1-2
「ある人がこう訪ねた。「どうやってわれわれはそれぞれ自分の人格にかなったことを知ることになるのでしょうか」」1-2
「このことをよく記憶していれば、どんな場合にも、君がもつべき君自身の人格を保つことができるだろう。」4-3
これに関して、本書の解説では以下のように指摘している。
「人格と訳したギリシア語のプロソーポンは顔の意味であるが、仮面をも意味しうる。いわば内面の自己である。それは本来の人間性を指し、同じく仮面を意味するペルソーナ(persona)によってラテン語化されて、キケロなどを通じて後に近代の人格概念(personality)へと受け継がれる。基本的には人格の喪失が個人の存在意義の喪失を結果させることを意味するわけであるが、尊厳を失わないための手段とされる自殺は、今日的な意味よりも範囲が広いことが注意されてよいであろう。」下486-487
解説では、キケロを通じて近代の人格概念へと受け継がれるとサラッと書いてあるが、果たしてそんなにサラッと理解してよいのかどうか。別の研究者はキリスト教の「三位一体」思想が決定的に重要な役割を果たしたと言っている。個人的には、「有機体」の思想も背後で大きな役割を果たしているような直感がある。
このテーマに関して「カラクテール=刻印」に関する記述もサンプリングしておきたい。
「つまり、土地、家屋、旅館、奴隷ではなく――これらは人間にとって真に固有のものではなく、すべて他人のもの、隷属的、従属的であるもの、主人によってその時々に各人にあたえられたものだからである――、むしろ人間的なもの、心の中にもってこの世に生まれてきた刻印を失った人を悲しむべきなのだ。われわれはこにょうな刻印を貨幣の中にも探し、これをみつければ貨幣として認めるが、みつからないとそれを投げ捨ててしまう。」4-5
ここに表現された「刻印」とはカラクテール、後には「性格」と訳されるような言葉である。むしろ近現代の「人格性=personality」とは、人間が人間である所以のものをさしており、こちらの「刻印」のほうが意味内容としては近いのではないか。だからというか、現代においてもcharacterという言葉は「性格」と訳されることもあれば「人格」と訳されることもある。エピクテトスの段階においては、むしろプロポーソンという言葉には「社会的な役割=仮面」という意味合いが強く、近現代のような「責任の主体」という意味合いは薄いような印象がある。このあたり、もっとたくさんサンプルを集めて検討しなければならない。
また近代以降に表明される考え方と響き合うような表現がいくつかあったのでサンプリングしておく。まず個別の利益が集団の利益と自然に一致することに関して。(もちろんアダム・スミスとの関連)
「一般的に言って、ゼウスはこのような自然本性をもった理性的な動物をこしらえたが、それは共通の利益になんらかの貢献をするのでないかぎり、個別的な善のいかなるものも獲得できないようにするためなのである。かくして、すべてのことを自分のためにするからといって非社会的であるわけではないことになる。」1-19
それから、一般と個別の明確な区別に関して。(教育に関しては、普通教育=education/専門教育=instructionの区別)
「さらに、目的には一般的なものと個別的なものとがある。最初のものは人間としてあるための目的である。これには何が含まれているか。たとえおとなしくても羊のように行動することではなく、野獣のように有害な行動をすることでもない。個別的な目的のほうは、各人の生の営みや意志に関連している。竪琴を弾いて歌う人は竪琴を弾いて歌う人として、大工は大工として、哲学者は哲学者として、弁論家は弁論家として行動する。」3-23
もちろんこれらはエピクテトスやストア派固有の考えというよりは、アリストテレスを引き継いで様々な立場から表明されているものではある。サンプルをたくさん集めて、近現代に流れ込んでくる様子を把握したいものではある。
■エピクテトス『人生談義(上)』國方栄二訳、岩波書店、2020年
■エピクテトス『人生談義(下)』國方栄二訳、岩波書店、2021年
 【要約】西洋哲学史のうち、特に紀元前4世紀(ヘレニズム期)から紀元2世紀(ローマ帝政前期)までに活躍した、ストア派の哲学者たちの思想を詳説しています。ストア前史としてキュニコス派の樽のディオゲネスから始まって、ストア前期(ゼノンなど)、ストア中期(パナイティオスなど)を経て、後期ストア派のキケロ、セネカ、エピクテトス、マルクス・アウレリウスを大きく扱っています。
【要約】西洋哲学史のうち、特に紀元前4世紀(ヘレニズム期)から紀元2世紀(ローマ帝政前期)までに活躍した、ストア派の哲学者たちの思想を詳説しています。ストア前史としてキュニコス派の樽のディオゲネスから始まって、ストア前期(ゼノンなど)、ストア中期(パナイティオスなど)を経て、後期ストア派のキケロ、セネカ、エピクテトス、マルクス・アウレリウスを大きく扱っています。