
 【要約】「個としての個」の思想は近代に誕生したと思い込まれていますが、実は決定的に重要なのは4~6世紀の古代末期(ビザンツ初期)にキリスト教公会議で交わされた三位一体とキリスト論に関わる教義論争で、特に古代ギリシア哲学の伝統を引き継ぎつつもそれと対決した東ローマ(ビザンツ)の神学者の思想が重要です。ウシア、ピュシスという概念(実体・本質)からヒュポスタシスという概念(基体)を切り離し、その宇宙論的な意味を担うヒュポスタシスというギリシア語が法的・社会的な意味を担うペルソナというラテン語によって翻訳されたときに、広大で多様なローマ帝国の多文化世界を背景とした化学変化が起き、元の概念を超える豊かな概念が新たに形成され、その新たな概念「ヒュポスタシス=ペルソナ」こそがまさにキリスト教が古代ギリシアの実体・本質重視の思想・文化を超えて表現しようとしていた「隣人への愛」という教義に明確な形を与え、「個としての個」の理念が固まりました。
【要約】「個としての個」の思想は近代に誕生したと思い込まれていますが、実は決定的に重要なのは4~6世紀の古代末期(ビザンツ初期)にキリスト教公会議で交わされた三位一体とキリスト論に関わる教義論争で、特に古代ギリシア哲学の伝統を引き継ぎつつもそれと対決した東ローマ(ビザンツ)の神学者の思想が重要です。ウシア、ピュシスという概念(実体・本質)からヒュポスタシスという概念(基体)を切り離し、その宇宙論的な意味を担うヒュポスタシスというギリシア語が法的・社会的な意味を担うペルソナというラテン語によって翻訳されたときに、広大で多様なローマ帝国の多文化世界を背景とした化学変化が起き、元の概念を超える豊かな概念が新たに形成され、その新たな概念「ヒュポスタシス=ペルソナ」こそがまさにキリスト教が古代ギリシアの実体・本質重視の思想・文化を超えて表現しようとしていた「隣人への愛」という教義に明確な形を与え、「個としての個」の理念が固まりました。
【感想】非常におもしろい。論旨は極めて明快で、私の個人的な研究(人格概念の探求)にとっても実に都合がいい見解が小気味よく並んでおり、喜んで今後の論文に引用させていただくことについては吝かではない。勉強になった。
ただし、逆に明快すぎて眉に唾をつけたくなる部分もなくはない。たとえばアリストテレスの評価と位置づけについては慎重に裏付けをとる必要を感じる。たとえばアリストテレスは「個あるいは一」を共約不可能な特異点としつつ、それが成立する条件を執拗に細かく分析していたのではなかったか。いわゆる「普遍論争」における唯名論の立場は、アリストテレスの範疇論における議論を背景として、存在するのは「個物」だと主張したのではなかったか。
また東ローマ(ビザンツ)を重視する本書全体の傾向は、ラテン的西欧(あるいはカトリック)に対するカウンターとしての意味と意義は十分に理解できるものの、本書が書かれた20世紀後半におけるアカデミズム全体のポストモダン・ポストコロニアル的ムーブメントの文脈に置いて、多少は差っ引いて考える必要を感じる。
また、歴史的には、「個の重視」はローマ文化にゲルマン的な要素が混入して誕生したというストーリーもあるはずだ。自由と権利を重視する「ゲルマン的な個」と、本書が扱う「ビザンツ的な個」は、やはり何か依って立つところが違っているのではないか。本書が言う「ビザンツ的な個」は、確かに「なんらかの単位としての個」であることは間違いないとしても、その属性として「自由・権利・尊厳」が伴うことはまったく自明ではない。ピュシスから切り離されたヒュポスタシスには自由や尊厳などない。それは線に対する点のような、無属性の特異点に過ぎない。かろうじてペルソナという言葉と概念が神と人の両者を表現する際に同じように使用されるという「類似」と「連想」によって自由・権利・尊厳の所在を仄めかすに過ぎない。しかし一方の「ゲルマン的な個」の本質は自由と切り離せないと理解されているのではないか。
そしてどうしても2023年の段階で想起してしまうのは、ビザンツ的なプーチンが、ゲルマン的な自由の精神を心底憎んでいるという事実である。そしてそこから逆算すると、東方ではグノーシス的な二元的異端が根強く蔓延し、それが実は「ディープステート」の陰謀を云々するような反知性的な心性に連なっているのではないか。穢れたものと見なす俗世間から隠遁して野蛮な反知性的修行で「神化」を目指す隠修士のような在り方は、イエスが説いた「隣人の愛」と本質的にまったく関わりがなく、「個としての個」にモナド的に引きこもる退廃した姿ではないのか。
まあそういう疑問を差っ引いても、非常に面白く、勉強になる本である。
【今後の研究のための備忘録】人格、ペルソナ
本書で鍵となる概念はラテン語の「ペルソナ」とギリシア語の「ヒュポスタシス」だが、それを日本語に敢えて置き換えると「個」とか「人格」という言葉で表現される。似たような言葉に「独」とか「孤」もあるが、圧倒的に「個」という感じがふさわしいのは間違いないだろう。
「純粋な個としての個、かけがえのない、一回かぎりの個の尊厳、そういったものが思想的・概念的に確立したのは、近代よりはるか以前のことだったと思われる。遅くとも紀元五、六世紀の、あのローマ帝国末期の教義論争のなかで、それははっきりとした独自の顔をあらわし出している。中世を通して生き続けたその顔を、近代はふたたび新たなかたちでとりあげたのである。」36頁
「今まで目に映らなかった「人格」というもの、「個の存在」というものが、見えてくるということは、やはり人の世界や他人への関わりを変える。」37頁
「そしてキリスト教の教義も、キリスト教の哲学化・思想化・体系化も、イエスが単純な「隣人の愛」ということばで語ったことのいわばパラフレーズであり、この単純な理想に、できるかぎり普遍的で透明で共時的なかたちを与えようとする努力にほかならなかった。その努力の中で人びとは、実はヨーロッパの思想・哲学にとって基本的に重要な新しい概念、新しい存在論を生み出していったと思われる。それが後に詳しく述べるような、個としての個の概念であり、純粋存在性の存在論であり、それが人格の絶対性とか尊厳とかなどに根拠を置く人権思想や民主主義体制をも支える一端となっていると思われる。」48頁
「純粋な「個」「ペルソナ」の概念が明確なものとなるのは、カルケドンのキリスト論のみならず、その前段階をなす三位一体論があってはじめて可能だったのだ。」51頁
「しかし末期ローマのこの社会の状況においては、この問題は起らざるをえない問題だった。この宗教は、この戦いを戦い抜いて、この宗教の本質の少なくとも重要な一部を、この社会・文化なりのかたちに造りあげ、救いとったのだと思われる。そこで救われ、現れてきたのが「ペルソナ=個としての個」を基盤に置く思想のかたちである。」71頁
ここまでの記述で本書の主張が既に明らかになっている。「個」という概念を生んだのがキリスト教で、特に4~6世紀の教義論争が極めて重要という立論である。しかしキリスト教の教義論争の分析に入る前に、ギリシア哲学の話を丁寧に進める。しかもローマ帝国でヘレニズム化したギリシア哲学(具体的には新プラトン主義)の話が延々と続く。
「神とキリストの関係の問題は、イエス自身の問題ではけっしてなかったが、すでに福音記者や使徒たちにとっては問題であった。それは、古代哲学が現象の根底に見いだそうとした一なる原理と、現象の多との間の関係への問いと同質の面を持つ。感覚に触れてくる多のうちに一を求めるのは、人間理性の本能とでもいうべきものだろう。」75頁
「キリスト教の教義が問題となった「教義論争」の時代以前に、すでに現象のすべてのうちに「一なる善」を見る視線がとぎすまされてきていた」78頁
「この一元論的なピタゴラス的・プラトニズム的体系ではじめて、かっきりした理性の対象でないもの、その意味で「普遍」ではないものが、存在的・価値的に優位に立つことが、理性的に確立される。個の個性、隣人の核心をなすもの、などもそういった種類のものであるから、隣人愛を説くキリスト教とこの思想が結び付くことになっていくのは、理由あることだった。」81頁
「三位一体論の背理は、個としての個なる人を論理的にも救いとる要求のためだった。」111頁
新プラトン主義とキリスト教の教義の親和性そのものについては、特に本書が明らかにしたわけではなく、古代教父アウグスティヌス本人が証言しているので疑いようがない。
しかしところで、「一なる原理」「一なる善」についてはプラトンやアリストテレスなど古代ギリシア哲学が徹底的に追求したものだし、東洋でも道教や朱子学が「太一」として追求しているわけだが、ここで本書がその営為を「人間理性の本能」と呼んでいるのは、なんというか、「多のうちに一を求める」というメカニズムがはたして「本能」なのか何なのかがそもそも哲学的に追求すべき究極の問題であって、それを「本能」と言ってすませられるのなら大半の問題は簡単に解決してしまうので、私個人としてはあまり軽率に「本能」という言葉に還元したくないところではある。まあ、そう言いたくなる傾向があることを仄めかしたいときには、ありがたく本書を引用させていただくということで、言質がとれているのはありがたい。
また、「三位一体」という現代的な感覚では圧倒的にどうでもよい論理を、「個としての個なる人を論理的にも救いとる要求」と理解しているのは引っかかる。確かにそういうストーリーも成り立つだろうし、そのストーリーで全体を構成する本書の論理に対して異論を差し挟むつもりはない。しかし個人的には、「三位一体」なる屁理屈はただただ単純にグノーシス主義的二元論への現実的な対抗策として強弁しただけで、当時の現場としては個としての個なる人なんかどうでもよかったが、意図しない副作用として偶然にそれを救いとった、というストーリーも捨てがたいところだ。
ともかく古代ギリシアの「一」にまつわる思想を整理したところで、続いて「ペルソナ」とその周辺概念の整理を行う。
「神の一性と、それにもかかわらず厳存する父と子の区別を、すでにラテン世界ではテルトゥリアヌスが、実体(substance)の一性とペルソナ(personaいわば基体)の二性として表現し分けていたが、このペルソナにあたる語を、アタナシウスはまだ確立していなかった。」103頁
「「ペルソナ」は法律上の人格・役割を意味する、もともと非形而上学的なことばであって、社会的人間の持つ多面性を表現し得ることばであった。法律家テルトゥリアヌスは、ひとりでありつつ多くの役を矛盾なく演じ、しかもその際他人になるわけでもない具体的人間のあり方との類比で、この概念を柔軟に、それゆえ矛盾につきあたって困惑することもなく、用いることができたのであろう。いかにもラテン的なことばであり、概念である。
しかし、これがギリシア的な自同律と矛盾律を基本に持つ形而上学的概念と結びつき、転化し、その体系のうちに組み込まれようとするとき、現実感覚の柔軟さは論理的矛盾として姿を現すことになる。」115頁
「中世末から近代にかけてのいわゆる「アリストテレス批判」「実体概念の解体」は、すでにここに、ビザンツ初期の白熱した数世紀の議論の中に準備されている。人びとは信仰上の情熱から、このきわめて基本的な問題に執拗なまでに取り組まざるをえなかった。この議論を「自然」のうちに移しさえすれば、そこに、近代科学の基本的考え方への一歩の寄与があることがわかるだろう。十三世紀スコラの盛期に、トマス・アクィナスが、ペルソナは「自存するものである関係」だという衝撃的なことを平然と言うのを見るとき、もうこれら実体とか関係とかいう概念がそれほど「いわゆるアリストテレス的」に明白なものではなく、変質してきていることがよくわかる。」128-129頁
「論理性・秩序・組織というロゴス原理は西洋の強みであり、それによって「人格」「愛」「精神(霊・プネウマ)」というような、とらえがたく柔らかい価値をも守るという、逆説的な仕事をある程度なしおおせたということが、西欧文化のもっとも大きな強みであったように思う。しかし、その場合、「愛」や「精神」はやはりともすれば内実を失って空洞化しなかったろうか?
(中略)たとえばレヴィナスとか、バフチンなどの人びとに、私は東方思想の血筋を見る気がする。そこでは人間性(という呼び方が妥当かどうかわからないが)、人間のいきいきとした姿、人間の芯にある火――おそらくそれが、ペルソナとか人格とか呼ばれるものだろうが――そういったものへの感受性が、まだ西欧思想におけるように解体・枯渇してしまわずに残っているような気がする。」140-141頁
「その一つの答えは、ラテン語では、このヒュポスタシスがペルソーナ(persona 以下慣例に従って短くペルソナとする)と翻訳されたからである。personaは近代ヨーロッパ語のperson、Person、personeなどとなり、日本語でも「人格」などと訳されている。これが西欧思想の一つの中核語であることに異論をとなえる人はないだろう。
しかし、ペルソナが本来はヒュポスタシスとはまったく異なった意味の語であることは明らかである。いわば、もともとギリシア語ではじまったキリスト教の思想化の努力が、西方ラテン世界に翻訳され、移行するときに、このもっとも中核的な概念が迷子になり、脱落して別のものとすりかわったかに見える。しかも、「ペルソナ」の語にしても、これからの叙述で見えてくるように、これは当時は独自の存在論の中核をなす語であった。それが西欧の中世から近代の歴史の中では、次第に単なる人間論の術語としてしか意味をもたなくなっていく。せっかく四世紀から六世紀に至る政治と理論の白熱のうちで姿を現してきたこの独自の存在性が、少なくとも西ヨーロッパでは次第にまた消滅してゆくのである。これは、「個」にきわめてよく似るが単なるギリシア的「個体存在(individium)」ではなく、おきかえのきかない純粋個者、しかも、つねに他者との文脈のうちにあることを本質とする単独者である。西欧はこの概念を失ったことによって、多くのものを失いはしなかったろうか。」150-151頁
「ヒュポスタシスは、実体・本質と区別された神の位格(父・子・精霊)を表示し、この「位格」が西方のラテン語ではペルソナと呼ばれるものである。したがって、ヒュポスタシスはまさに神のペルソナ的な、いわば人格的(正しくは位格的)な面を示すことばと言えるのである。この区別は、あるいは西方で先に確立したという面もあるかもしれない。ニカイア公会議がまだウシアとヒュポスタシスの区別をどうつけてよいかわからないでいた一方で、西方ラテン世界のテルトゥリアヌスは、そのほぼ百年も前に、父・子・精霊という古い呼びかけと神の一性を、一つの実体(essentia)と三つの位格(persona)というかたちで両立させていたのだから。」154頁
「ニカイアの公会議自体は、キリストが、また精霊も、父なる神と実体(ウシア)を同じくする「神からの神」、つまり父とまったく同一の神であることを語っただけで、「ヒュポスタシス」とか「ペルソナ」とかいう、三位格の共通名を出していない。しかし、およそ四、五十年後に、カパドキアの教父たちは明瞭にヒュポスタシスとウシアについて論じているし、さらにその四十年後にアウグスチヌスは、先に引用した『三位一体論』五巻八章のくだりで、明らかに三位格にペルソナ(persona)という共通名を与え、ギリシア語ではそれをヒュポスタシスと言うと語っている。」171頁
「まったく本来は意味の違うペルソナとヒュポスタシスという二語が、どうして対応語として用いられつづけたのか。」171頁
「カルケドン信経は、プロソーポン(ペルソナに対応するギリシア語、原義は顔、そこから個人)とヒュポスタシスを同義として列挙し、ラテン語はペルソナとスブステンチアを列挙している。この四語のうちからなぜ、ヒュポスタシスとペルソナだけが残って等値されることになったのか。」172頁
「テルトゥリアヌスが早くに用いていたペルソナという語は、この混乱を避けて、神の本質と区別された、ある種の存在性(父・子・精霊という)を指し示すために便利だったのである。」173頁
「紀元前二百年前後、第二ポエニ戦争のころに、すでにペルソナの語は、(1)劇場の仮面、(2)劇での人物、(3)たぶん役割、(4)たぶん文法での人称、などの意味をすでにもっていたと思われる。そしてこの語の意味を一挙に広めたのは(ほかの多くのラテン語のヴォキャブラリーにおけると同様)、やはりキケロだった。」177-178頁
「ローマ人の法的思考のうちで、ペルソナの語は、ギリシア語プロソーポンよりもはるかに豊かに発達し、かえってプロソーポンの語義を広めるのに影響したことが指摘される。ただ、法的発展をのぞいても、それ以前に仮面と劇の人物という意味から、タイプ、性格、社会的・道徳的役割という意味への移行は、日常言語のうちで行われていた。また劇のヒーローの尊厳やユニークさのニュアンスも、この期に与えられていた。ペルソナとはこのように豊かな社会的・法的・道徳的意味を含む語として、キリスト教成立以前にラテン語のうちに確立していたのである。」178-179頁
「「沈殿」「基礎」が、「仮面」と訳されるという奇異な事態が起こったのは、既述のような歴史的経緯の中で、おのおのの語の多様な意味のひろがりの中にある「個存在」という共通項・媒介項を介してであった。ラテン語のペルソナには、徹頭徹尾社会のうちなる個人というニュアンスがあり、役割、人に与える影響、印象、尊厳といった含意がある。ヒュポスタシスには、元来そうした意味合いはまったくない。そのかわり、ヒュポスタシスにはまた、ペルソナにはまったくなかった宇宙的視野と連関とがある。ヒュポスタシスは自然学的・形而上学的な存在論のことばであり、ペルソナは劇場と法律と日常社会生活のことばである。この両者が等値されて、一つの同じ対象を指すとされるとき、その対象には複雑な交響が生じ、多様な倍音が生じる。キリスト教思想の中核となったペルソナ=ヒュポスタシスは、このようにしてきわめて豊かな概念となった。」180頁
「ここで注目すべき重要なことは、両概念に共通する一つの性格である。それは、この両者いずれにおいても、個存在性と流動性・関係性という一見矛盾した二要素が密接に共存しているということである。ヒュポスタシスは、流動きわみない、一者からの存在の流出のうちの束の間の留まりとしての純粋存在性であった。宇宙的流動と因果関連の網なしには、ヒュポスタシスは存在しえない。ペルソナはまた、劇場という演劇的場のうちの一要素であり、そこから転じて法体系のうちでの要素、社会的関係のうちで役割をもつ個人であった。
(中略)ヒュポスタシスは宇宙的循環の一要素であるし、劇全体の構成や社会全体の依存関係と関連性なしにはペルソナはペルソナたりえない。劇は成立しない。この両概念がそのまわりにひろげる関連の場は、異質なものである。しかし、両者とも個存在性と関係性の両面をにらみ、両面を必須とする概念であることは共通している。そして、この両者が等値されるとき、結合された概念のもつ場は、宇宙的かつ人間的、自然的かつ法的・社会的、非人間的かつ日常人生的なものが重なり合い。混じり合い、対位法的に関わり合う不思議な場となった。」181-182頁
「それはやはりもとをただせばローマ帝国というものの広大さ、多民族・多文化の交響であったのだ。互いに異質なものをもつギリシア語圏、それもヘレニズムの小アジア、シリア・エジプトなどの文化を含みもつギリシア語圏の文化と、ラテン語圏の文化と、東方の思弁と神秘と超越に対する西方の現世と人間の現実へのたしかな眼ざし。形而上学と宗教に対する歴史と法とレトリック。その出会いがこのヒュポスタシスとペルソナの出会いであった。キリスト教思想が豊かな種子をもったとすれば、それは、多文化混淆のローマ帝国の豊かさであった。」183頁
うーむ、なるほどだ。このあたりの話は類似のテーマを扱う論文や概説書でも読むところではあるが、いまのところ本書がいちばん丁寧に分析しているように思う。「ペルソナ」概念の整理については、今後の研究でありがたく引用させていただきたい。というか、こういう優れたまとめ研究があるにもかかわらず、今でも「ペルソナの原義は仮面です」と言って分かった気になっている概説書が多いのは如何なものか。
ただしかし、この概念が中世ヨーロッパで欠落した(そして本書では強調されないが、ルネサンス以降に復活する)と繰り返し主張しているところは、眉に唾をつけておきたい。この西欧中世をディスる見解は、西洋中世が遅れた暗黒時代で、その時期の東方(ビザンツとイスラーム)のほうが進んでいたというブルクハルト的な歴史観に合致する。しかし近年では、こういうブルクハルト的な歴史観を乗り越えて西欧中世の知的水準を再評価しようとする動きが盛んだ。本書は「個としての個」に対する感受性をレヴィナスやバフチンなど現代の東方思想家に見出し、それに対する憧憬を隠そうとしない。私もレヴィナスやバフチンの現代的な思想が独創的で魅力的だと認めることについては同意するものの、ただしかし個人的な感想では、西洋中世に劣らず東方中世でも「ペルソナ」概念は忘れ去られていたように思うのだった。実際、本書でも東欧中世についての実証的な資料は提出されず、レヴィナスやバフチンなど現代的な人物名(あるいは近代以降のロシア文豪)が散発的に傍証として上がってくるだけだ。仮にブルクハルトの衣鉢を継いで西欧中世をディスるのは結構だとしても、だからといって返す刀で東欧(そしてあるいは日本など)を持ち上げることには慎重でありたい。
さてともかく下準備が終わったので、いよいよ本格的にキリスト教教義論争の中身に入っていく。
「もっとも決定的だったのは、東方ではキュリルス風の一本性説が、キリストという特殊な例のうちで人間性がいわば神化されるさまを表現していると思われていたことだろう。上昇と神化への欲求は、プラトニズム的・ギリシア的東方の宗教性の根づよい憧憬であった。キリストという範型的な人間の神化は、人間全体の神化の可能性を示し、モデルを与え、道を開くものと解されていた。これは「全く人」の現実性にあくまでも執し、仲介者についてもその現実的人間性を尊いものと思い、その受苦の現実性によってこそ罪の贖いと人類全体の買い取りが可能であると考える西方の、人間主義的で法律的匂いがしないでもない見方とは、同じキリストという存在の理解の上でも大きなへだたりがあった。」244頁
本書の立論からすれば傍証の位置に当たる文章ではあるが、ここで言及されている東方の「神化」という概念は気に留めておきたい。というのは、西欧中世でもグノーシス主義的二元論異端や、あるいはエックハルトのような神秘思想家が目指しているのが、明らかにこの「神化」だからだ。あるいは対抗宗教改革としてイグナチオ・ロヨラが打ち立てたイエズス会の修行の在り方も想起していいのかもしれない。だとすれば、この西欧中世の「神化」思想は、ビザンツからもたらされたものなのか。そしてそれはルネサンスや宗教改革以降の「個」の思想になにかしらのインパクトを与えているのか。だとしたら1453年のビザンツ帝国に伴う知識人や宗教家の流出にどれほどの意味を見出すべきなのか。こういう問題系が関わってくるところだ。
「三位一体論とキリスト論は、プラトン-アリストテレス風の、普遍を実体とし、真実在とする存在論を逆転する構図を人びとにつきつけてきたのである。その先駆はストアやネオプラトニズムにあったと思われるが、ここまで先鋭に、非妥協的に正面から対決するに至ったのは、このきわめて抽象的な存在論的差異が、実は何よりもごくふつうの人びと心情と希求の差であり、政治的党派の差でもあったからだ。存在論はここでは希み、愛し、生き、党派と体制をつくり、またそれに反抗し、利害と権力を争う人間のあり方をまるごと受肉しているのである。
ヒュポスタシス=ペルソナというかたちでここに姿を見せてきたこのものは、まさにあの透明な、いかなる属性をも顧慮しない、神の愛・隣人愛の向うもの、その対象でもあり、またその愛を与える源泉でもある。」291-292頁
「ギリシアがものの神髄として、本質として見たものが何といっても共通的なものだったのに対し、キリスト教がもっとも尊貴なものとして、その意味での本質として見るものは、個の個たるところである。トマスがアリストテレスをうけつつ、例の鋭さで「働きは単独者のものである」と語っていたのが思い出される。キリスト教があらゆる出来事と存在の神髄として説くのは、個々の人間の心の救いであり、そのために一回一回独自の仕方で、つまりいわば単独者として働く、神の行為と愛である。その神への愛と隣人への愛である。」315頁
ここが本書の一番の肝になる部分だ。この論証が成功しているかがどうかが、本書全体の説得力を決定する。そして、それは極めて難しい。なぜなら、これこそ普遍的なことばに変換して他者と「共約」することが不可能な部分だからだ。
そしておそらくそのことを一番わかっているのは著者自身で、だからこそ本書全体の構成が本書のようになったのだと思う。本書の書き出しと書き終わりは、他者と共約不可能な極めて個人的なエピソードとなっている。まさに「一回一回独自の仕方で、つまりいわば単独者として働く」ような感情と行為が書き連ねられている。そういう共約不可能なものを共約しようと努力を重ねる「単独者」としての行為こそが、おそらく本書の一番の見どころなのだ。そう思ってみれば、レヴィナスやバフチンに対する偏りが表明されようが、東方に共感を寄せようが何だろうが、そんなものを論理的に難詰する必要などないわけだ。隣人としてできることは、この本書の仕事を私自身が「一回一回独自の仕方」で受け取るだけであり、それがいままさにこのような私自身の単独者としての感想として現れているということだ。不遜にもいろいろ疑問点を書き連ねてはいるが、著者をディスっているのではなく、私自身の研究を進める橋頭保とするための備忘録であることは独り言として言っておきたい。そしてこういう読書が「交流」として成立するのであれば、それに越したことはない。
「アリストテレスの場合はピュシスをひき去ってしまった基体は無性質無形の、ほとんど無にひとしい「質量」であったが、レオンチウスで姿をあらわす純粋のヒュポスタシスはまったく逆である。これはネオプラトニズムの系統をひく、むしろ非質量的な、活動的統一原理、つまり「一者」の流れをひく能動的な個的存在性そのものである。」322頁
「アウグスチヌスはまた、さきに三位一体論のところで述べたように、この「個」の問題への、まったく独特のアプローチを西欧に与えた。それは、外界、自己の肉体などのすべてがそこから証明されてくる「心(cor)」という場の探求であった。自己の心の奥深くへ沈潜することが、すべての自己の意識、記憶、思考、意志、感覚を統合する一なるもの、あのプロチヌスのはるかな「一者」につらなる真我の体験に至ることを、アウグスチヌスは私たちに具体的にかいま見させてくれた。彼は東方でレオンチウスたちがうちたてた、人を統合し、またはキリストという存在を統合するペルソナ=ヒュポスタシスの存在論を、いわば内面から、内的体験として証明してみせてくれたのである。」329-330頁
「このようなことはすべて、受肉のロゴスのヒュポスタシスについて言われることである。この個こそが、もっとも範型的な個、個の内の個であることは明らかだろう。この強烈な凝集力、無限の包容力、無限の多様性は、あらゆるヒュポスタシス-ペルソナの範型であり、キリスト存在の類比者として語られる人間存在にも弱められたかたちで似姿的に存在するわけである。それゆえ、人間の心と身体を集めるヒュポスタシス=ペルソナも、同様に「統合されたヒュポスタシス」と呼ばれる。」341-342頁
ここは丁寧に論証を求めたいところだが、やはりこういうふうにしか書けないことを認識させられたところだ。私個人の関心は「人間の人格」にあるわけだが、それはやはり神の「類比者」とか「似姿」という形でしか表現できないものだった。ともかく、私自身はとてもではないがここまでの論証はできないので、巨人の肩に乗せていただくような気持ちで、ありがたく引用させていただく。
「ハルナックはまったく正しくも、この概念の中にすでに「自然と区別された〈人格(Personlichkeit)〉という近代的概念が、もとより影のようにではあるが、姿を現わしている」と書く。ただし、私はこれが近代の人格概念の影であるというよりは、むしろアウグスチヌスーデカルトという線を辿ってひたすら意識的内省へとその場を移していった近代の人格概念の方が、もとのヒュポスタシスにあった存在の意味を見失っているのではないかと思う。」347頁
「この思想の中心であるヒュポスタシス=ペルソナは、知、情、意、身体的なもの心的なもの、すべてをひとしなみに集め、かけがえない個として形づくるものである。しかもそれは、それら多なる要素を束ね、集め、覆い、あるいは生み出す純粋な働きであり、他のそのような純粋な働きたちと、根において連なり、交流している純粋存在である。
そのモデル、範型は、もとより神の性質をも人の性質をも、これほど相容れないものどもを、集め、束ね、一つにしている受肉した神の第二の位格、キリストである。彼はまた、神としても、三位の交流関係によってはじめて存在する、関係者にして存在者、とでも言うべきものである。存在が関係においてはじめて成り立つことのモデルでもある。」353頁
「東方でスコラ的に精錬されたヒュポスタシス=ペルソナ思想の概括を、ペルソナの定義というかたちで西方中世に伝えたのは彼(ボエティウス)であった。しかしその「功績」には多少の疑義もある。彼の定義「理性的本性の個的実体」は、アウグスチヌスが賢明にも注意深く避けた実体(substance)という語を、ペルソナの定義の中心にふたたび導入してしまった。そのことによって、個なるペルソナの中核は、ネオプラトニズム系・セム系の動性を失って、アリストテレス風の静的に閉じた個になりはしなかったか?」356頁
「キリスト論は古代に現われた種々な存在論を、ほとんど不可能な仕方で一つに結び合わせる。それは、キリストという存在が、もともと不可能な存在だったからである。全く人・全く神。つまり人としては私と種的に同一なもの。しかし個なる私にとっては他者。神としては私と絶対に異であり他であるもの。しかも創造者として種的にも個としても、私の存在の根源であり、私を包み、あらしめているもの。私にとって絶対に他であり私と非連続であり、しかも私とある意味で絶対に同一なもの。物質的・人間的存在であり非物質的・非人間的な神存在。――それはこの世界と絶対者が一つに結合する場所であり、絶対者が自らを世界のために失うところであり、逆に世界が自らを失って絶対者に参与するところでもある。しかもまた、両者が自己を失わずに差異と区別を保ちつづける場とも考えなければならない。」364-365頁
畳みかけるような論述で、圧倒される。ナルホドと頷くしかない。世間には「キリスト教は一神教だから個の概念を生んだ」などという粗雑でいい加減な思い付きで分かったようなことを言う文学者もいたりするわけだが、つまらないことこの上ないので、こういうクザーヌス的な「対立物の一致」くらいの技は見せてもらいたいところだ。
■坂口ふみ『〈個〉の誕生―キリスト教教理をつくった人びと』岩波現代文庫、2023年<1996年
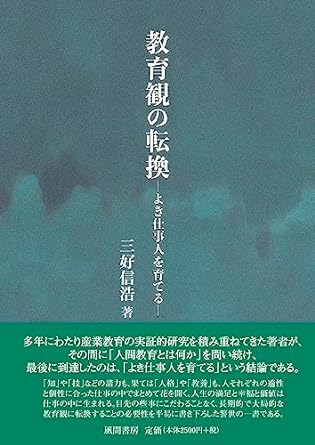 【要約】伝統的な講壇教育学は「教育」の目的を人格や教養という概念で語ってきましたが、それは現実と噛み合っておらず、様々な問題を引き起しています。江戸以来の日本人の仕事観を踏まえ、これまで傍系として軽視されてきた職業教育や産業教育を見直し、教育の目的を「よき仕事人を育てる」という観点から組み替えましょう。明治以降の工・農・商・医などの実業教育が担ってきた人作りの成果を踏まえ、現代の高等専門学校や専修学校や各種学校、あるいは企業内職業訓練等も含めて文科省管轄学校以外の人材育成機関が担っている大切な役割に改めて注目すると、現代の教育問題を解決するための様々な可能性が見えてきます。
【要約】伝統的な講壇教育学は「教育」の目的を人格や教養という概念で語ってきましたが、それは現実と噛み合っておらず、様々な問題を引き起しています。江戸以来の日本人の仕事観を踏まえ、これまで傍系として軽視されてきた職業教育や産業教育を見直し、教育の目的を「よき仕事人を育てる」という観点から組み替えましょう。明治以降の工・農・商・医などの実業教育が担ってきた人作りの成果を踏まえ、現代の高等専門学校や専修学校や各種学校、あるいは企業内職業訓練等も含めて文科省管轄学校以外の人材育成機関が担っている大切な役割に改めて注目すると、現代の教育問題を解決するための様々な可能性が見えてきます。



