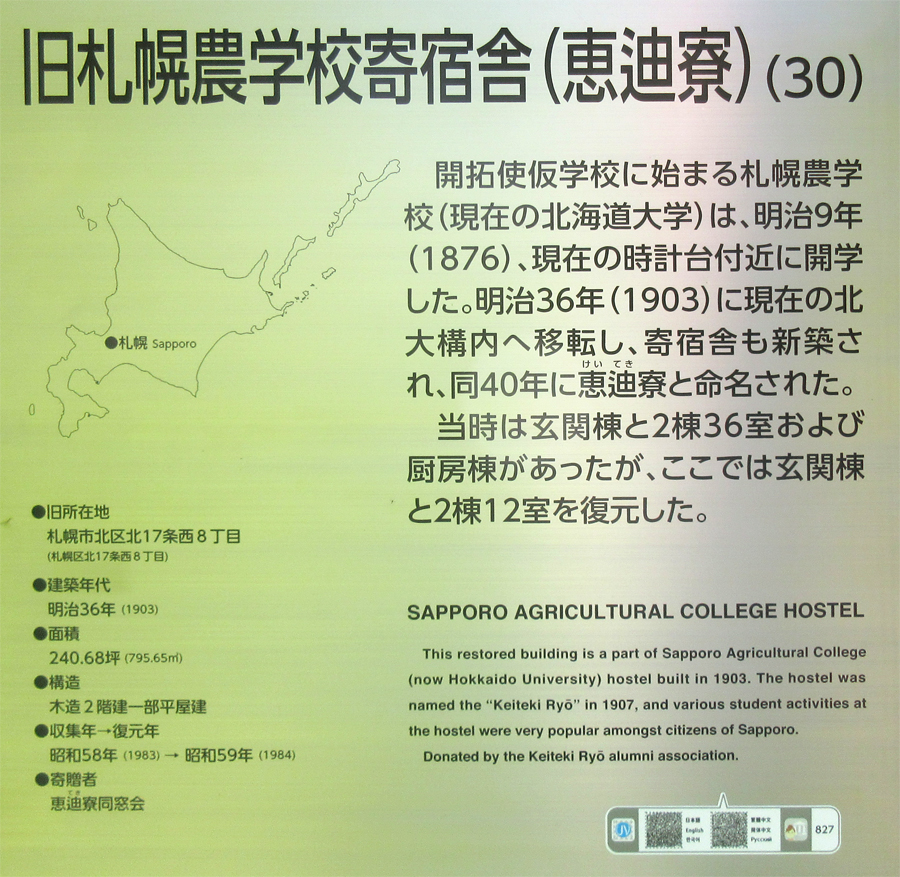【要約】子どもたちは、学校で死んだ魚のような目をして、退屈な時間を過しています。学校は、社会の役に立っていません。社会が変化した以上、学校も変化しなければなりません。
【要約】子どもたちは、学校で死んだ魚のような目をして、退屈な時間を過しています。学校は、社会の役に立っていません。社会が変化した以上、学校も変化しなければなりません。
これからの新しい学校は、理想的な家庭を延長した、理想的な小さな社会とならなければいけません。子どもたちは生活で得た経験を学校に持ち込み、その経験は学校の中で豊かに磨き上げられて、人生の洞察に不可欠な科学的知識へと結びつきます。
そのためには、小学校から大学までの学校システムを統一的に整備し、「教える内容」と「教える方法」を統一しなければいけません。それは子どもの「生活」を中心としたときに初めて可能になります。私が作った実験学校での取り組みの結果、確信を持って言うことができます。
【感想】「児童中心主義」を高らかに宣言する、新教育のマニフェスト的な本だ。背景となる社会理論も心理学理論もしっかり整備されている上に、実験学校における実践も伴っており、説得力あることこの上ない。100年以上前の本であるにも関わらず、「最新の学習指導要領の解説として出た」と言っても違和感がないほど、理論的には古びていない気がする。まあ、個々の具体的事例はもちろん古びているんだけれども。逆に言えば、現代の教育がデューイの議論をちゃんと乗り越えているのか、不安になるところでもある。
【個人的な研究のための引用とメモ】
コペルニクス的転回と児童中心主義
本書では、児童中心主義をわかりやすく説明するためにコペルニクスの地動説を例に挙げている。いわゆる「コペルニクス的転回」である。
「旧教育は、これを要約すれば、重力の中心が子どもたち以外にあるという一言につきる。重力の中心が、教師・教科書、その他どこであろうとよいが、とにかく子ども自身の直接の本能と活動以外のところにある。(中略)。いまやわれわれの教育に到来しつつある変革は、重力の中心の移動である。それはコペルニクスによって天体の中心が地球から太陽に移されたときと同様の変革であり革命である。このたびは子どもが太陽となり、その周囲を教育の諸々のいとなみが回転する。子どもが中心であり、この中心のまわりに諸々のいとなみが組織される。」49-50頁
非常に分かりやすい喩えで、教育にとって「子どもの生活」が決定的に重要であることを明快に示している。
社会に開かれた教育課程
本書の構成は8章から成っているが、最初の演説では3章構成だったという。その3章が、現在の学習指導要領の構成と極めて近接しているのは、興味深い。すなわち、
第一章 学校と、社会の進歩
第二章 学校と、子どもの生活
第三章 教育における浪費
という構成なのだが、これはそれぞれ最新学習指導要領と、
(1)社会に開かれた教育課程
(2)主体的・対話的で深い学び
(3)カリキュラム・マネジメントと学校経営
というふうに対応している。
たとえば第一章「学校と、社会の進歩」では、デューイは産業社会の急激な進展によって家庭における子どものあり方が根本的に変化したことを指摘し、それに伴って学校の役割も変わるべきことを主張する。
「明白な事実は、社会生活が徹底的な、根本的な変化を受けたということである。もしわれわれの教育が生活にとってなんらかの意味をもつべきであるならば、それは同様に完全な変形をとげねばならぬ。」43頁
「知識基盤社会」に対応して教育が変わらなければいけないと訴える現今学習指導要領の言い分と、とてもよく似ている。まあ、デューイの言う社会の変化が機械化である一方、学習指導要領の言う社会の変化はIT化、という中身の違いはある。とはいえ、社会の急激な変化を背景とした教育改革の必要性という点では、状況は極めて似ていると言える。
そしてデューイは、そういった社会変化に、学校がまるでついていけていないと指摘する。
「倫理的側面からみるならば、こんにちの学校の悲劇的な弱点は、社会的精神の諸条件がとりわけ欠けている環境の中で、社会的秩序の未来の成員を準備することにつとめていることである。」27頁
「しかるに、学校はこれまで生活の日常の諸条件および諸動機から甚だしく切離され、孤立させられていて、子どもたちが訓練を受けるために差し向けられる当のこの場所が、およそこの世で、経験を――その名に値いするあらゆる訓練の母である経験を得ることが最も困難な場所となっている。」30頁
上に引用した100年以上前の言葉は、ただの一個所の改変も必要とせず、そのままそっくり現代日本の教育に適用できてしまう。これはかなり恐ろしい事実である。「社会に開かれた教育課程」という合い言葉は、最近になって言われ始めたわけではない。100年前から叫ばれ続けていたにも関わらず実現しなかったのだと、認識しなければならない。学校という組織を変えることは、そう簡単ではない。
では、デューイはこれからの学校をどうしようと言うのか。
「学校はいまや、たんに将来いとなまれるべき或る種の生活にたいして抽象的な、迂遠な関係をもつ学科を学ぶ場所であるのではなしに、生活とむすびつき、そこで子どもが生活を指導されることによって学ぶところの子どもの住みかとなる機会をもつ。学校は小型の社会、胎芽的な社会となることになる。」31頁
ここでは、「生活指導」という概念が見られることに注目しておきたい。
主体的・対話的で深い学び
続いて、第一章で示された理念を、子どもの発達の側面から見るのが第二章「学校と、子どもの生活」の狙いである。一人ひとりの子どもの個性を重視し、興味を足がかりとして、生活のなかの活動をとおし、自然と社会の本質をつかませる。児童中心主義の本領発揮である。いわゆるアクティブ・ラーニングというものが100年以上前から実践されていたことは、踏まえておいていいかもしれない。
この章では、「言語」というものに対する考え方と扱い方も注目ポイントである。
「言語本能は子どもの社会的表現の最も単純な形式である。だから、言語はあらゆる教育的手段のなかで重要なもの、おそらくは最も重要なものであろう。」60-61頁
「旧制度のもとにおいては、子どもたちに自由にのびのびと言語をつかわせることは、疑いもなくきわめて困難な問題であった。その理由は明白であった。言語にたいする自然な動機がほとんどあたえられなかったのである。教育学の教科書においては、言語とは思想を表現する手段であると定義されている。なるほど思考的に訓練されたおとなにとっては言語は多かれ少なかれそういうことになるが、しかし、言語はまず第一に社会的なものであり、それによってわれわれが自己の経験を他人にあたえ、逆に他人の経験を受け取るための手段であることは、あらためていうまでもないことであろう。もしも言語をこの自然な目的からひき離してしまうならば、言語の教授が複雑で困難な問題になることは、怪しむに足りない。」68-69頁
ここでは、言語というものが「思想を表現する手段」としてよりも、他者とコミュニケーションを図る手段として、より重要な地位をあたえられている。「主体的・対話的で深い学び」を実現する際、あるいは「言語活動」というものを重視する際にも、参考となる言語観だろう。
カリキュラム・マネジメントと学校経営
以上の「社会に開かれた教育課程」および「主体的・対話的で深い学び」を踏まえた上で、デューイは第三章「教育における浪費」の中で、学校制度改革とカリキュラム構成について言及する。これは最新学習指導要領では、いわゆる「カリキュラム・マネジメント」に相当する部分だ。
デューイはまず現今のカリキュラムに統一が欠けていると批判する。
「しかしながら、根本的な統一が欠けていることは、次の事実に徴してあきらかである。すなわち、ある学科は依然として訓練に役立つものと考えられ、他の学科は依然として教養に役立つものと考えられていることである。たとえば、算術の或る部分は訓練に、他の部分は実用に役立つものである、文学は教養に、文法は訓練に、また地理は一部分は実用に、他の部分は教養に役立つものと考えられている、など。ここでは教育の統一などということはかげもなく、諸々の学科は勝手な方向をむいてばらばらである。」88頁
これまた一文字の変更もなく現在の教育に適用されて違和感のない文章である。この分断的・散漫的なカリキュラムを変えるために、デューイは「生活」による統一を提言する。
「子どもがこの共通の世界にたいする多様な、しかし具体的で能動的な関連のなかで生活するならば、かれの学習する学科は自然に統合されるであろう。そうなれば諸学科の相関というようなことは、もはや問題ではなくなるであろう。教師は、歴史の課業にわずかばかりの算術をおりこむために、あれこれと工夫をめぐらすといったような必要もなくなるであろう。学校を生活と関連せしめよ。しからばすべての学科は必然的に相関的なものとなるであろう。(中略)。さらにまた、もし全体としての学校が全体としての生活と関連せしめられるならば、学校の種々の目的や理想――教養・訓練・知識・実用――は、もはやこの一つの目的ないし理想にたいしてはこの一つの学科を選び、他の一つの目的ないし理想にたいしては他の一つの学科を選ばねばならぬというような個々ばらばらなものではなくなるであろう。」107頁
デューイは様々な実例も挙げるのだが、それらはいわゆる「総合的な学習の時間」を彷彿とさせるものだ。というか、「総合的な学習の時間」はデューイの構想を土台として出来ているわけだから、当たり前なのだが。
が、この部分は、最新学習指導要領と袂を分かつ点かもしれない。デューイは統合の原理を「子どもの生活」に求めているが、最新学習指導要領は統合の原理を「求められる資質・能力」に求めている。デューイはあくまでも一人ひとりの子どもの個性を大事にしようとするが、すべての子どもが共通して身につけるべき「資質・能力」については何も言わない。一方、学習指導要領はすべての子どもが共通して身につけるべき「資質・能力」を想定する。ここが決定的に違う。この学習指導要領の姿勢が、果たしてデューイ理論を基礎とする戦後教育改革に対して加えられた「這い回る経験主義」という批判を乗り越える可能性を持つのかどうか、学習指導要領自身は何も述べていない。
ともかく、最終的で現実的な制度設計において、学習指導要領はデューイを離れてブルーナーに近づいていくのであった。新学習指導要領の狙いが当たるかどうかは、「理念としてのデューイ、手段としてのブルーナー」というあり方が適切かどうかにかかっているように思うのだった。
問題解決学習
また本書の注目点は、「問題解決学習」についての言及にもある。
「かつまた、前の第一期の特徴である子どもと学習される社会生活との全身的・劇的な同一化に加えて、いまや知的同一化がおこってくる――すなわち、子どもは遭遇せねばならぬ問題の見地に自己を置き、それらの問題を解決する方法をおよぶかぎり再発見するのである。」129頁
「かかる注意はつねに「学習」用のもの、いいかえれば、他人が尋ねるであろうところの問題にたいする、すでに出来上っている解答を記憶することのためのものである。いっぽう、真の、反省的な注意は、常に判断・推理・熟慮をふくんでいる。すなわちそれは子どもが自分自身の問題をもっており、その問題を解決するための関係材料を探求し選択することに能動的に従事し、その材料の意義と関係を――すなわちその問題が要求するような解決の道を考察することを意味する。問題は自分自身のものなのである。であるからして注意への動因・刺激もまた自分自身のものである。それゆえにまた、得られた訓練も自分自身のものである。――それは真の訓練、すなわち統制力の獲得であり、またいいかえれば問題を考察する習慣の獲得である。」180頁
問題解決学習は、子どもの興味と社会および科学を結びつける重要で決定的な媒介物となることが期待されている。問題解決学習の論理がデューイの発達心理学理論に根拠を置いていることは、知識として知っておいて損はしないかもしれない。
■ジョン・デューイ『学校と社会』宮原誠一訳、岩波書店、1957年