魂の世話
このページでは、ソクラテスの教育について考えていきます。
結論から示すと、ソクラテスの教育が目指しているのは、人々が「魂の世話」を心がけるようになることです。
プラトンが描いたソクラテス
ということでさっそく内容の検討に入りたいところですが、しかしまず困るのは、ソクラテス自身が自分の教育について何も書き残していないことです。いちおう弟子のプラトンがソクラテスを主人公とした素晴らしい対話編をたくさん書き残してくれたおかげで、ソクラテスの言動を知る手がかりは豊富に与えられています。ただ、このプラトンの才能がありすぎて、むしろ困ってしまうわけです。才能がありすぎるプラトンは、師匠であるソクラテスの思想をさらに自分で突き詰めて考察を深め、最終的にオリジナリティ溢れる独創的な高みにまで上りつめます。逆に言えば、どこまでがソクラテスのオリジナルで、どこからプラトンが付け加えたものかが、分からなくなってしまっているわけですね。
そんなわけで、私としては完全にオリジナルなソクラテスの再構成は最初から断念し、プラトンが書き残した対話編を通じて、大雑把にソクラテスの教育を捉えることに務めていくことにしたいと思います。
で、「魂の世話」の中身を総合的に理解する上で重要な4つのキーワードがあります。「無知の知」「産婆術」「汝自身を知れ」「エロス」を順番に検討していきます。
無知の知
まずは「無知の知」から確認していきましょう。「無知の知」とは、簡単に言えば、「自分が知らないということを自覚している」という意味です。が、もちろん「自分が勉強できないの、知ってる」なんて意味で「無知の知」と言っているわけではありません。『ソクラテスの弁明』の記述を参考に、「無知の知」について見ていきましょう。
「何」を知らないのか
 いちばん誤解していけないのは、「無知の知」と言った場合の「知らない」とは、「1+1=2」を知らないとか「ドラえもんの声優は大山のぶ代」を知らないとか、そういうクイズ的な知識を知らないという意味などではない、ということです。知識がなくて学校のテストの点が悪いとか、そういうレベルの無知をテーマにしているわけではありません。ここを見誤ると、ソクラテスの主張が最初からまったく分からなくなります。
いちばん誤解していけないのは、「無知の知」と言った場合の「知らない」とは、「1+1=2」を知らないとか「ドラえもんの声優は大山のぶ代」を知らないとか、そういうクイズ的な知識を知らないという意味などではない、ということです。知識がなくて学校のテストの点が悪いとか、そういうレベルの無知をテーマにしているわけではありません。ここを見誤ると、ソクラテスの主張が最初からまったく分からなくなります。
ソクラテスが言う「知らない」とは、「命を賭けてでも知りたい価値のあるものについて、残念なことにそれが本当に何なのかを絶対に知ることができない」という意味です。「1+1=2」とか「ドラえもんの声優は大山のぶ代」という知識は、他人から教えてもらえれば知ることができます。ソクラテスが取り組む知識とは、そういうふうに自分の外部から他人によってもたらされる知識ではありません。
彼の言う知識とは、「自分の生き様」が間違っていないかどうか、確認できるような知識です。たとえば「正義とは何か」が本当に分かっているなら、自分の生き様が正義にかなっているかどうか、正確に判断することができるでしょう。しかし、この肝心の「正義とは何か?」が分からないから、自分の生き様が間違っていないかどうか、確認することができません。これがソクラテスの言う「知らない」という意味です。
世界一の賢者ソクラテス

 ソクラテスは、自分がどんな生き方をするべきか絶対的に示してくれる確実な知識を「神の知」と呼び、求め憧れました。「1+1=2」とか「ドラえもんの声優は大山のぶ代」のような、誰か他人から教えてもらえれば獲得できるような知識は、言ってみれば「人間レベルの知」です。ソクラテスは、いま自分が持っている知識など所詮は人間レベルのものであって、自分が心から求めている絶対的な「神の知」には指先すらかかっていないということを自覚していました。自分が「無知」であることを強烈に自覚して、自分なんて大したことがない奴だと思っていたわけです。
ソクラテスは、自分がどんな生き方をするべきか絶対的に示してくれる確実な知識を「神の知」と呼び、求め憧れました。「1+1=2」とか「ドラえもんの声優は大山のぶ代」のような、誰か他人から教えてもらえれば獲得できるような知識は、言ってみれば「人間レベルの知」です。ソクラテスは、いま自分が持っている知識など所詮は人間レベルのものであって、自分が心から求めている絶対的な「神の知」には指先すらかかっていないということを自覚していました。自分が「無知」であることを強烈に自覚して、自分なんて大したことがない奴だと思っていたわけです。
が、ある日、友達のカイレポンがデルフォイの神殿に行って、ソクラテスこそが世界一の賢者であるというお告げを得てきます。それを聞いたソクラテスは、「ありえない」と思います。日頃から「神の知」を求めさまよい、見つからず、自分自身のことを「無知」だと自認しているソクラテスにとって、「世界一の賢者」のお告げは不可解極まりないものでした。しかし他ならない神様からいただいたお告げですから、「神の知」を求めてやまないソクラテスとしては無視するわけにもいきません。自分が世界一の賢者などとは信じられないものの、神様の言葉である以上は何かしら重大な意味があるだろうということで、ソクラテスはお告げが正しいのかどうか確かめようと試みます。
バカばっかり
 お告げが真実かどうか確かめるために、ソクラテスは頭がいい人たちと話をすることにしました。というのは、自分が知らないようなことを知っている人が一人でもいれば、少なくとも自分は二番目以下ということで、「世界一の賢者」ではないことが明らかになります。世間には「自分は何でも知っている」と豪語している人がたくさんいるので、一人くらいは本当に「神の知」を持っている人がいてもいいかもしれません。そしてさらに、そういう智者と話ができれば、自分が知りたいと願っている「神の知」を教えてもらえるかもしれない。ソクラテスはそう期待に胸を膨らませて、「自分は何でも知っている」という自称賢者たちと話をしに行きました。
お告げが真実かどうか確かめるために、ソクラテスは頭がいい人たちと話をすることにしました。というのは、自分が知らないようなことを知っている人が一人でもいれば、少なくとも自分は二番目以下ということで、「世界一の賢者」ではないことが明らかになります。世間には「自分は何でも知っている」と豪語している人がたくさんいるので、一人くらいは本当に「神の知」を持っている人がいてもいいかもしれません。そしてさらに、そういう智者と話ができれば、自分が知りたいと願っている「神の知」を教えてもらえるかもしれない。ソクラテスはそう期待に胸を膨らませて、「自分は何でも知っている」という自称賢者たちと話をしに行きました。
が、実際に話をしてみて分かったことは、賢者を自称する人々が、実は何も知らなかったということでした。「自分は何でも知っている」と豪語している人が本当に「神の知」を持っているのか、ソクラテスがあれこれ質問しながら吟味してみると、たちまち馬脚を現して、実際には何も知らなかったことが明らかになるのでした。
確かに自称賢者たちは、「人間レベルの知」はたくさん持っているようでした。が、ソクラテスが求めていたのはそんな「人間レベルの知」ではありません。確実な生き様を認識できる絶対的な「神の知」こそが問題なのです。自称賢者たちは、誰一人として「神の知」を持っていないどころか、それを持っていないということすら自覚していないことが発覚するのでした。
所詮は人間の知
 「神の知」を示してもらえるのではないかと密かに期待していたソクラテスは、「人間レベルの知」で満足している相手のバカさ加減にガッカリしながら帰途につきます。帰り道で、ふと気がつきます。自分も相手も、「神の知に辿り着いていない」という点についてはまったく違いがありません。ただ、相手は「自分が知らないということすら知らない」のに対し、自分は少なくとも「自分が知らないということを知っている」のです。このわずかな自覚の違いで、自分は彼らより一歩先を行っているのだと、ソクラテスは気がつきます。デルフォイの神殿のお告げは、きっとこのことを言っていたのだなと、ソクラテスは思いました。
「神の知」を示してもらえるのではないかと密かに期待していたソクラテスは、「人間レベルの知」で満足している相手のバカさ加減にガッカリしながら帰途につきます。帰り道で、ふと気がつきます。自分も相手も、「神の知に辿り着いていない」という点についてはまったく違いがありません。ただ、相手は「自分が知らないということすら知らない」のに対し、自分は少なくとも「自分が知らないということを知っている」のです。このわずかな自覚の違いで、自分は彼らより一歩先を行っているのだと、ソクラテスは気がつきます。デルフォイの神殿のお告げは、きっとこのことを言っていたのだなと、ソクラテスは思いました。
しかしそれはもちろん、自分は本当に「世界一の智者」なのだと自信を持ったという意味ではありません。仮にお告げの言うとおり自分が「世界一の智者」であったとしても、そんな自分は相変わらず「神の知」に届いていません。ちっとも嬉しくありません。神様がお告げによって本当に伝えたかったことは、「人間界最高の智者ですら、神の知には指先すらも届かない」とういうことなんだとソクラテスは理解します。そして神様がわざわざ自分にお告げを与えたのは、「神の知に届いているなどと自称している人々が、実はまるで無知である上に、自分が無知であることにすら気づいていない大馬鹿野郎だ」ということを暴いて自覚させる、そういう使命を与えるためだったのだと理解します。自分の使命を自覚したソクラテスは、自称賢者たちの無知を次々と暴いていくことになります。
そういうわけで、「無知の知」という言葉の意味は、単に「知らないことを知っている」ということにとどまりません。「人間の力では絶対に神の知に手が届かない」という理解が伴って、初めて意味を持つような言葉なのです。「自分が勉強ができないことを自覚しているから、無知の知」などという「人間レベル」で理解したつもりにならないようにしましょう。
産婆術

 さて、そんなふうに自分は何も知らないと公言しているソクラテスなのですが、なぜか若者たちは喜んでソクラテスと話をしました。ソクラテスと話をすると、自分が成長したように感じるからです。それまで自分が知らなかったような知を獲得できた気になるからです。
さて、そんなふうに自分は何も知らないと公言しているソクラテスなのですが、なぜか若者たちは喜んでソクラテスと話をしました。ソクラテスと話をすると、自分が成長したように感じるからです。それまで自分が知らなかったような知を獲得できた気になるからです。
これはとても不思議な現象です。なぜなら、ソクラテスは「何も知らない」からです。常識的に考えれば、何も知らない人が、相手に「知」を与えることなどできません。自分の持っていないものを相手に与えることなど不可能です。それにも関わらず、ソクラテスの対話相手は、知を獲得することができました。知を持っていないソクラテスが誰かに知を与えられるはずがないのに、ソクラテスと対話している相手がいつの間にか知を獲得してしまう。このような技術を「産婆術」と呼びます。
産婆術については、『テアイテトス』という本に詳しく書いてあります。こちらを参照しながら、産婆術について見ていきましょう。(ちなみに『テアイテトス』に記述された産婆術は、現代的な視点から見るとちょっとグロいのと、プラトンの数学偏重的立場が混入されてオリジナルを歪めているように思えるので、以下の祖述には私なりのアレンジが相当程度加えられていることをあらかじめお断りしておきます。)
「知」はどこから来るのか
 さて、ソクラテスは知を持っていないにも関わらず、対話を続けているうちに、いつのまにか対話相手の若者は知を獲得します。この「知」は、いったいどこからやってきたのでしょうか?
さて、ソクラテスは知を持っていないにも関わらず、対話を続けているうちに、いつのまにか対話相手の若者は知を獲得します。この「知」は、いったいどこからやってきたのでしょうか?
何も存在しないところから「知」がいきなり出現するわけはありません。「知」はどこかにあったはずです。そしてソクラテスは「知」を持っていません。だとしたら、残る可能性はただ一つ、対話相手の若者がもともと持っていたのだと考える以外にありません。しかしそうだとしたら、若者は「知」を持っていたにも関わらず、それを自分自身では自覚できていなかったということになります。きっと「知」は若者自身から見えないところにあったはずです。たとえば、お腹の中にあったとしたらどうでしょう。もしも自分のお腹の中に「知」があったとしたら、自分の目からは見えないので、自分が持っていることに気がつかなくても仕方ありません。しかし持っていることに気がつかなくとも、お腹の中に何かあったら、なにかしら違和感が生じます。お腹がもぞもぞして、気分が悪くなります。出産したくなります。自分のお腹に異変を感じた若者は、なんとかそれを処理しようと、助けを求めてソクラテスのもとにやってきます。ソクラテスは若者を診てやります。ソクラテスが診てやると、若者は自分のお腹の中にあった「知」を産み出します。いったん産んでしまえば、自分の体の外に出た「知」は、自分の目で見えるようになります。「あ、知だ!」と分かります。そしてその「知」はもともと自分のお腹の中にあったものであって、ソクラテスから与えられたものではありません。ソクラテスは、ただ診てやっただけです。
産婆は出産の手伝いをするだけ
このソクラテスの対話技術が「産婆」の技術とよく似ているので、この一連の行為を「産婆術」と呼んでいます。「産婆」とは、女性が子供を出産するときにサポートする人のことです。近年は病院で出産することが増えたので「産婆」の出番はなかなかありませんが、かつては自宅で出産することが多く、妊婦さんが産気づくと産婆さんを呼んで手伝ってもらっていました。
子供を産むのは、あくまでもお母さんの行為です。当たり前のことですが、産婆自身が子供を産むわけではありません。産婆さんは出産の「お手伝い」をするだけです。産婆さんの仕事は、お母さんのお腹をさすったり、お母さんの息を整えたり姿勢を直してやったり、洗い桶や綺麗な布など環境を整えたり、生まれた赤ん坊を綺麗に拭いてやったりすることです。産婆さんの手助けがあって、お母さんは無事に子供を産むことができます。こうやって産婆さんが妊婦さんを励ましたり応援したりしながら出産を手伝う様子が、ソクラテスの教育法によく似ているわけです。
というのも。知を産むのは、あくまでも若者の行為です。当たり前のことですが、ソクラテス自身が知を産むわけではありません。ソクラテスは出産の「お手伝い」をするだけです。ソクラテスの仕事は、若者が何か言いたいのを励ましてやったり、発言に適切な質問を加えて議論を展開させたり、考察に必要な概念や具体例を持ってきてやったり、生まれた知識を綺麗に拭いてやったりすることです。ソクラテスの手助けがあって、若者は無事に知を産むことができます。
こうして若者は、自分自身の中にもともとあった知を産み出すことができたのですが、いま一度確認すると、若者がソクラテスから知を分け与えてもらったわけではありません。というか、そもそも「無知」であるソクラテスが誰かに知を与えることなど最初からできるわけがありません。彼は「対話」の力によって、若者の内部から知を引き出します。
対話
若者の内側から知を引き出す際、ソクラテスが実際に行っている作業は「対話」です。巧妙な「対話」を通じて、若者の内側から知が湧き上がってきます。産婆術とは、具体的には「相手の内部から知を引き出す対話の技術」と言い直すことができるでしょう。対話相手から知を引き出すためには、相手の言葉に辛抱強く耳を傾け、断片的な言葉と未熟な論理から相手が本当に主張したい論点を把握し、間違っている論理は間違っていると指摘したり、有望な論理が出てきたら褒めて励ましてさらに思考の展開を促したり、言いたいことを的確に表現するための適切な言葉を見つけるのを手伝ったり、気づきのきっかけを作ったり、議論の筋道を整理したり論点や到達点をまとめたりするなどの様々な手助けが必要となります。
しかし、この姿勢がなかなか難しいわけです。まず難しいのは、相手の話を「傾聴」するということかもしれません。いわゆる「先生」と呼ばれる職業に就いている人たちは、なにかと教えたがる傾向にあり、なかなか相手の話を黙って聴くことがありません。まず、対話相手をバカにせず、しっかりと話を聴いて、相手の主張を尊重すること、これが産婆術の基本中の基本になるでしょう。そしてソクラテスが極めて謙虚に相手の話を聞くことができるのは、根底に「無知の知」があるからだということは言うまでもありません。自分が何も知らないと自覚しているからこそ、相手の話を先入観なしで聞いたり、忌憚なく質問したり確認したり、正しく理解し論理的に判断したりすることができるわけです。
汝自身を知れ
さてところで、そうやって対話相手から引き出される「知」の中身とはどのようなものでしょうか。もちろん、「1+1=2」とか「ドラえもんの声優は大山のぶ代」というような知識であるはずがありません。産婆術でもたらされる「知」の中身については、デルフォイ神殿の入口に刻まれていたという標語、「汝自身を知れ」が重要な手がかりとなりそうです。以下、ソクラテスの言う「知」の中身を検討していきます。(ただし、プラトンのテキストそのものから読み取れる内容からは大きく逸れて、私個人の見解を反映した記述に向かうことはあらかじめお断りしておきます。)
自分のお腹の中にある「知」とは何か?

 さて、ソクラテスが産婆術で引き出したのは、対話相手のお腹の中に潜んでいた知でした。外から与えてもらわないのに、もともと自分のお腹の中に潜んでいた知とは、具体的にはどのようなものでしょうか? もちろん「ドラえもんの声優は大山のぶ代」という知識のはずがありません。そういう知識は、もともと自分の中に潜んでいるわけがなく、外から与えてもらわないと身につけることができないようなものです。
さて、ソクラテスが産婆術で引き出したのは、対話相手のお腹の中に潜んでいた知でした。外から与えてもらわないのに、もともと自分のお腹の中に潜んでいた知とは、具体的にはどのようなものでしょうか? もちろん「ドラえもんの声優は大山のぶ代」という知識のはずがありません。そういう知識は、もともと自分の中に潜んでいるわけがなく、外から与えてもらわないと身につけることができないようなものです。
が、「1+1=2」という知はどうでしょう? まあ確かに「1+1=2」なら教えてもらわないと分からないかもしれませんが、たとえば「53+69=122」ならどうでしょうか? おそらく「53+69」の答えが「122」だと教えてもらったことがなくとも、「53+69=122」が正しいことは分かると思います。数学の正解というものは、外から教えてもらわなくとも、基本的な原理原則さえ押さえていれば自分の中から引き出すことができます。
数学に限らず、論理的な手続きを経て結論に至るような知識であれば、確かに外から新しい知識を付け加えなくとも、自分の内部で適切な情報処理を繰返していけば最終的に正しい結論に辿り着くことができます。この様子は『メノン』に鮮やかに描かれています。『メノン』に示されたプラトンの記述をそのまま受けとめれば、産婆術とは論理的な手続きを正確に踏んでいく対話の技術です。
理性によって知る
数学に典型的に見られるように、論理的な手続きを正確に踏めば、外部から新しい知識を付け加えなくとも最終的に正しい結論に辿り着けるのは何故かというと、すべての人間が平等に「理性」を備えているためです。数学など論理的な問題に対しては、「理性」を正確に働かせることさえできれば、すべての人間は間違いなく共通の結論に辿り着きます。逆に言えば、生まれたときから自分の内部に備わっている「理性」を正確に運用できるなら、外部から知識を与えてもらう必要などないということです。プラトンの記述に従えば、産婆術が目指しているのは、理性を正確に運用して確実な知識に辿り着く手続きです。
ここまでくると、デルフォイ神殿に刻まれた標語「汝自身を知れ」とは、「すべての人間に平等に備わった理性を追究せよ」という意味であると解釈することができそうです。「汝」とは、神様がわれわれ人間に向けて呼びかけた複数二人称ということになります。プラトン『メノン』や『テアイテトス』の記述を辿る限りは、そう解釈できそうです。
理性の限界を知る
しかし、プラトンの初期著作に登場するソクラテスの言動を見ると、簡単にそう断言していいかどうか疑問も生じます。というのは、ソクラテス本人が数学を重視していた形跡がまったく見当たらないからです。実はプラトンは、中期対話篇を書く頃にピュタゴラス派と接触し、数学に傾倒したと考えられています。ですので、中期対話篇である『メノン』や『テアイテトス』にはオリジナルなソクラテスの姿が描かれているというより、ピュタゴラス派に影響を受けたあとのプラトンの思想が反映していると見るほうがよさそうに思われます。
初期の対話篇でソクラテスが関心を示していたのは、数学ではなく、「善く生きる」とはどういうことか?というテーマでした。ただ単に「生きる」のではなく、「善く生きる」ということがテーマでした。そのために、「善い生き方とは何か?」を徹底的に追究しました。この「神の知」に数学が関わってくる余地は、あまりなさそうな気がします。
そもそも思い返してみれば、ソクラテス自身が確実に知っていたのは、「自分は何も知らない」ということでした。そして様々な自称賢者たちと話をして確認できたのは、「自分だけが何も知らない」のではなく、「人間であれば誰もが絶対に知ることができない」ようなものがあるということでした。人間というあり方に本質的につきまとう「絶対的な無知」について知ることが「無知の知」です。単に「自分は知らないが、他の誰かは知っている」ようなものを「無知の知」とは絶対に呼んではいけません。
そういうわけで、ソクラテスの言動に即して考えれば、「汝自身を知れ」とは「すべての人間に平等に備わった理性を追究する」ことなどではなく、まったく逆に、「人間理性では絶対に到達できないものがあることを知り、理性の限界を自覚する」ということであり、「神の知の前では謙虚になるしかない」ということになります。プラトンとソクラテスでは、言っていることがまるで違ってくるわけです。
(ただし、プラトンも数学的理性の限界には気がついていました。数学的理性の限界を超えて真の知識に辿り着く手段として、プラトンは「哲学的対話法」を持ち出しています。そして「哲学的対話法」の中身は、厳密には分かっていません。ひょっとしたら、プラトンの「哲学的対話法」も、ソクラテスが言うような「人間理性では絶対に到達できないものがあることを知り、理性の限界を自覚する」ための手続きかもしれません。が、今となっては、プラトンが本当に何を考えていたかは、謎のままです。)
わたしはどう生きるか?
さらに、教育学に携わる者の関心が、テキストには書いていないところにまで飛躍することを許してもらえれば。ソクラテス本人が人間に共通する「理性の限界」を問題にしていたとしても、ソクラテスに話を聞いてもらっていた若者の受け取り方は、また違っていたかもしれません。
たとえば。ソクラテスは実際の対話では、「正義」や「美」や、そして「善」を問題としました。ソクラテスにとっては、これらは共通して「理性の限界」を超えているものだったのでしょう。実際にソクラテス初期対話編では、問いに対する答えが出ずに消化不良のまま対話が終了し、「理性の限界」が示されます。ソクラテス本人にとっては「いちおう頑張ってみたけど、やっぱり人間の理性では答えは出ないよね。そりゃそうだよね」というふうに、改めて「無知の知」を確認した機会ということでいいでしょう。しかし対話を聞いていた若者たちに対しては、おそらくまったく違う効果があったと思われます。というのは、確かに、「正義」や「美」や、あるいは「善」というものには、一つの決まった答えがあるわけではありません。逆に言えば、「正義とは何か?」という問いは、「正義とはこういうもの」などと客観的な答えを出すべき数学的な問いではなく、ひとりひとりの主観的な「生き様」を問うような倫理的な問題として迫ってくることになります。評論家的な態度では絶対に答えは出ないけれども、当事者として必ず何かしらの見解を示さなければならないような、そういう人生観が問われるものとして迫ってきます。他人事ではなく、「わたしはこう考える」とか「わたしはこう生きる」とか、自分事としてどう「生きる」かが問われているような、そういう問題として迫ってきます。自分の外部に答えがあるのではなく、自分の内部にしか答えがないような、そういう問いとして迫ってきます。
若者ひとりひとりが「どう生きるか」は、ソクラテスにとっては知ったことではありません。というか、ソクラテスが知るわけもありません。「無知」です。若者が「どう生きるか」については、ソクラテスが外側から何なかの「知」を若者に付け加えてやることはできません。若者が「どう生きるか」は、自分の内側から産み出さなければならない知です。そしてそれこそが、他の何よりも重要な知であるはずです。「わたしはどう生きるべきか」という問いに対する答えは、「1+1=2」だとか「ドラえもんの声優は大山のぶ代」などという知よりも、圧倒的に決定的に重要な、人生に関わる知です。
わたし自身を知る
「わたしはどういう人間か?」とか「わたしには何ができるか?」とか「わたしは何をしなければならないか?」とか「わたしはどうしたら幸せになれるか?」とか、つまり「わたしはどう生きるか?」という問いは、自分にとって最も重要な問いです。そして、自分以外の人間からは絶対にもたらされない知です。自分自身の内側から産み出さなければならない知です。しかし、こんなに難しいことはありません。「1+1=2」だとか「ドラえもんの声優は大山のぶ代」のように、他人から正解が与えられるような知識であれば、身につけることは簡単です。知っている人に聞けばいいだけです。しかし自分がいちばん知りたいこと、「私はどう生きるべきか」という問いに対する答えを他人が与えてくれることは、絶対にありません。どうしても自分自身で産み出さなければなりません。他人から与えられることが絶対にないのに、どうしても自分自身の内側から産み出さなければらない知。それこそが「汝自身を知れ」という箴言の本当の意味なのかもしれません。
だとすれば、実はソクラテスの「産婆術」は、どう生きればいいのか途方に暮れて悩んでいた若者たちが「自分を知る」ために、大きな手助けとなっていたのではないでしょうか。悩んで、迷って、苦しんで、話を聞いてもらいたくてソクラテスのもとにやってきた若者に対し、ソクラテスは外部から知識を与えてやるわけでもなく、ただ若者の話に耳を傾け、間違っているところは間違っていると指摘し、議論を整理し、よかったところは褒め、到達点をまとめてくれるだけです。あくまでも答えは若者自身が出さなくてはなりません。が、ソクラテスのように真摯に対話相手になってくれる人がいるだけで、どれだけ救いになることでしょうか。ソクラテスとの対話を通じて、自分の内側に自分なりの答えを見つけた若者もいたことでしょう。
(以上の見解は、プラトンが残したテキストから直接に読み取れるものではありません。教育学的想像力の産物とでも言えるものだということは、いちおう記しておきます。)
エロス
そうやって、迷って、悩んで、苦しんだ若者たちがソクラテスのもとにやってきて、ソクラテスも喜んで若者たちの話に耳を傾けて、ひとりひとりがそれぞれの「生き方」を見つけていく。それはそれで美しい光景です。が、そうやってソクラテスのもとにやってくる若者はいいのですが、やってこない人たちはどうなるのでしょうか?
陣痛を起こす力
プラトンはそういう事情を「陣痛」という言葉で表現しています。陣痛が起った若者は、自分の内側にある何者かを産み出す必要に迫られて、産婆術の達人ソクラテスのもとにやってきます。しかし陣痛が起こっていない者には、そもそも産婆は必要ありません。産婆術の出番もありません。
が、『テアイテトス』の中でソクラテスはなかなか凄いことを言っています。彼には対話相手に「陣痛」を引き起す力があるようなのです。つまり、相手の内側に何かを生じさせる力があるようなのです。『テアイテトス』では、プラトンの数学趣味によって本来のソクラテスの姿が失われている恐れがあるので、他の著作も合わせて総合的にソクラテスの「陣痛を起こす力」を考えてみましょう。たとえば『饗宴』と『パイドロス』に記されたエロスの話は、このテーマを考える上で、なかなか興味深いものです。
恋愛の達人ソクラテス

 『パイドロス』の中で、ソクラテスは恋愛についてよく知っていると言っています。何も知らないと自称している割には、恋愛については自信があるようです。結論だけ先に示すと、ソクラテスは恋愛を「美しいものの内部で出産を願う」ことだと言っています。この「出産」という言葉に注目しましょう。「出産」するためには、そのまえに「陣痛」が起こらなければいけません。逆に言えば、陣痛さえ起これば、あとは産婆術の領域です。恋愛→陣痛→産婆術→出産という順番を踏まえると、産婆術の領域に相手を引き込むには、相手を「恋愛」に巻き込めばいいことが分かります。ソクラテスの「陣痛を起こす力がある(テアイテトス)」という証言と「恋愛はよく知っている(パイドロス)」という証言を合わせて解釈すれば、彼には相手の心の中に恋心を引き起すことで結果的に産婆術の世界に引き入れる技術があったと考えてよさそうです。
『パイドロス』の中で、ソクラテスは恋愛についてよく知っていると言っています。何も知らないと自称している割には、恋愛については自信があるようです。結論だけ先に示すと、ソクラテスは恋愛を「美しいものの内部で出産を願う」ことだと言っています。この「出産」という言葉に注目しましょう。「出産」するためには、そのまえに「陣痛」が起こらなければいけません。逆に言えば、陣痛さえ起これば、あとは産婆術の領域です。恋愛→陣痛→産婆術→出産という順番を踏まえると、産婆術の領域に相手を引き込むには、相手を「恋愛」に巻き込めばいいことが分かります。ソクラテスの「陣痛を起こす力がある(テアイテトス)」という証言と「恋愛はよく知っている(パイドロス)」という証言を合わせて解釈すれば、彼には相手の心の中に恋心を引き起すことで結果的に産婆術の世界に引き入れる技術があったと考えてよさそうです。
恋の対象
 とはいえ、もちろんソクラテスが言う恋愛は、世間一般で言う「恋愛」とはかなり意味が違っています。特に重要なのは、ソクラテスの言う「恋愛」には肉体的な欲望が伴っていないということです。実際に『饗宴』では、肉体的な欲望を強靱な精神力で押さえつけるソクラテスの姿が描かれています。
とはいえ、もちろんソクラテスが言う恋愛は、世間一般で言う「恋愛」とはかなり意味が違っています。特に重要なのは、ソクラテスの言う「恋愛」には肉体的な欲望が伴っていないということです。実際に『饗宴』では、肉体的な欲望を強靱な精神力で押さえつけるソクラテスの姿が描かれています。
ソクラテスの言う「恋愛」とは、「精神的な恋愛」を意味しています(世間的にはこれを「プラトンの恋愛=プラトニック・ラブ」と呼んでいるようです)。われわれは、美しく、素晴らしい、価値あるものに対して、心惹かれます。そしてその美しいものとは、目に見える美しさもあるでしょうが、心の目で見えるような美しさにはよりいっそう魅力を感じます。そういう価値あるものに、われわれは近づきたいと願い、求め、行動します。そうやって人々を価値ある美しいものに向かわせる動きを、ソクラテスは「エロス」と呼んでいます。エロス自身は美しいものではありません。なぜなら自分自身が完全に美しいものであったら、自分自身に留まって、敢えて外部の美しいものに向かおうとはしないだろうからです。自分自身が美しいものではないから、美しいものに惹かれるわけです。そしてまた完全に醜いものではありません。完全に醜いものは、美しいものの素晴らしさに気がつかないだろうからです。だからエロスとは、美しいものと醜いものの中間(メディア)です。
ソクラテスは、究極に美しいものは「神」だけだと言います。そして「エロス」の働きによって、われわれのような不完全な人間が完全なる神に憧れるのだと言います。われわれは何も知らない無知な存在ではあるけれども、エロスの働きによって完全な美である神に向かっていきます。ソクラテスが人間の身でありながら「神の知」を求めてやまないのも、エロスの働きによるものです。
マニア=狂気こそが神に到達する
ソクラテスが「エロス」というものを完全なる神と不完全なる人間の「中間=メディア=媒介物」だとしていることは、教育学的に重要な示唆だと思います。完全性への憧れを芽生えさせる「媒介物」は、ソクラテスの文脈で言えば「美しいもの」となるわけですが、おそらく人の興味関心をかき立てるようなものであればなんでも構わないに思われます。たとえば、「鉄道」でも、「切手収集」でも、「アニメ」でもいいでしょう。
というのは、ソクラテスが言うには、人間の身でありながら神の領域に到達する奇跡を起こすには、尋常の常識的努力では絶対不可能で、「狂気」に陥って人間を超える必要があります。そしてこの「狂気」とは、ギリシア語では「マニア」です。「マニア」になった者だけが、人間の常識を遙かに超えて、神の領域へと到達することができます。「鉄道マニア」も「切手収集マニア」も狂気=マニアに陥っているという点では同じわけですが、このとき鉄道マニアや切手収集マニアは、その「媒介物=メディア」を通じて、憧れの「神の領域=真善美そのもの」に到達しているということです。
逆に言えば、「媒介物=メディア」を工夫することによって、人々を「狂気=マニア」の世界へと誘い、「神の領域=真善美そのもの」への憧れを掻き立てることができるということです。子供たちを「狂気=マニア」に陥らせるような「教材=メディア」を提供できれば、子供たちの中に「神の領域=真善美そのもの」への憧れを生み出せるかもしれません。
そうやっていったん「神の領域=真善美そのもの」への憧れ=エロスさえ芽生えれば、時間が経てば自然に陣痛が起こり、あとは産婆術の領域の話になります。逆に言えば、この憧れが生じなかった者には、陣痛が起こらず、産婆術は何の役にも立ちません。「エロス」は、教育を可能とするエネルギーなのです。
【まとめ】魂の世話
こうしてソクラテスは、「無知の知」の自覚のもと、若者たちの「エロス」を芽生えさせ、「産婆術」を駆使して、「汝自身を知れ」という神の教えを実践するために、「魂の世話」を勧めて回りました。
ソクラテスの処刑
ソクラテスが見るところ、人々は、人生で大切なものについて大きな勘違いをしていました。お金とか、名誉とか、そんなものを皆が大事にしています。しかし「無知の知」の自覚のもとで吟味してみれば、お金や名誉などというものが人生で最重要なテーマになるわけがないことが分かります。大事なことは、「神の知」に辿り着くことができなくとも、それに憧れて向かって行くことです。それは、自分自身の中にたったひとつだけある「魂」を大事にすることです。しかしその最も大切なものであるはずの「魂」を、誰もがないがしろにしています。ソクラテスは、そんなことでは絶対に幸せになることができないと確信し、人々に「魂の世話」をするように説いて回りました。人生で本当に大切な「汝自身」に気づくための「産婆術」であり、手助けを可能とするための「エロス」なのです。
しかしそんなソクラテスが、裁判にかけられ、処刑されます。紀元前399年のことです。ソクラテスは町の有力者たちから憎まれていました。町の有力者たちは、「自分は何でも知っている」と豪語していましたが、ことごとくソクラテスによって「実はバカ」だったことを暴かれていました。恥をかかされた有力者たちは、ソクラテスを憎むようになっていたのです。ソクラテスを亡き者にしてやろうと狙っていた人々は、ついにデタラメな言いがかりをつけて、処刑に追い込んだのでした。
死ぬことは怖くない
しかし死刑に処されるソクラテスの態度は、極めて堂々としていました。まるで「死」を恐れていないようでした。実際、ソクラテスは「死」を恐れていませんでした。なぜなら、ソクラテスが言うには、死んだ後のことは誰も知らないからです。「死」が本当に嫌なものかどうか、確かめた人は一人もいないのです、それを知っているのは「神」だけです。自分が知らないようなものについて考えても仕方ありません。ひょっとしたら、「死」というものはとても素晴らしいものかもしれません。「知らないものは知らない」と認める、だから「死」は怖くない。これこそがソクラテスの「無知の知」の真骨頂です。
いやまあ、理屈はそうかもしれません。が、実際に自分が処刑されるまさにその瞬間ですら、そういう態度でいられるなんて、ちょっと信じられない凄さです。凄い。発言と行動が一致している様子を表す「言行一致」という言葉がありますが、まさにソクラテスは言行一致の人物でした。いや、言行一致なんて言葉でも生ぬるい気がします。「言」と「行」がまったく分離していない、そういう本物の「神の知」を最後の最後まで追究し続けた人物でした。
この態度こそが、彼の言葉に圧倒的な説得力を持たせています。彼は本当に最後まで自分の「魂」の世話を大切にしていたのでした。
→参考:研究ノート『プラトンの教育論―善のイデアを見る哲学的対話法―』

【要約】能力主義的な価値観の下での「主体的な学習」は、江戸時代半ばから始まりました。


 ■田中耕治・水原克敏・三石初雄・西岡加名恵『新しい時代の教育課程 第4版』有斐閣、2018年
■田中耕治・水原克敏・三石初雄・西岡加名恵『新しい時代の教育課程 第4版』有斐閣、2018年 ■細尾萌子・田中耕治編著『新しい教職教育講座教職教育編6 教育課程・教育評価』ミネルヴァ書房、2018年
■細尾萌子・田中耕治編著『新しい教職教育講座教職教育編6 教育課程・教育評価』ミネルヴァ書房、2018年 ■松尾知明『新版 教育課程・方法論 コンピテンシーを育てる学びのデザイン』学文社、2018年
■松尾知明『新版 教育課程・方法論 コンピテンシーを育てる学びのデザイン』学文社、2018年 ■木村元・汐見稔幸『アクティベート教育学01教育原理』ミネルヴァ書房、2020年
■木村元・汐見稔幸『アクティベート教育学01教育原理』ミネルヴァ書房、2020年 ■佐々木司・熊井将太編著『やさしく学ぶ教育原理』ミネルヴァ書房、2018年
■佐々木司・熊井将太編著『やさしく学ぶ教育原理』ミネルヴァ書房、2018年 ■寺下明『教育原理 第2版』ミネルヴァ書房、2012年
■寺下明『教育原理 第2版』ミネルヴァ書房、2012年 ■川口洋誉・古里貴士・中山弘之『新版 未来を創る教育制度論』北樹出版、新版2020年
■川口洋誉・古里貴士・中山弘之『新版 未来を創る教育制度論』北樹出版、新版2020年 河野和清『現代教育の制度と行政(改訂版)』福村出版、2017年
河野和清『現代教育の制度と行政(改訂版)』福村出版、2017年 ■稲垣忠編著『教育の方法と技術Ver.2 IDとICTでつくる主体的・対話的で深い学び』北大路書房、2022年
■稲垣忠編著『教育の方法と技術Ver.2 IDとICTでつくる主体的・対話的で深い学び』北大路書房、2022年 ■山本正身『日本教育史:教育の「今」を歴史から考える』慶応義塾大学出版会、2014年
■山本正身『日本教育史:教育の「今」を歴史から考える』慶応義塾大学出版会、2014年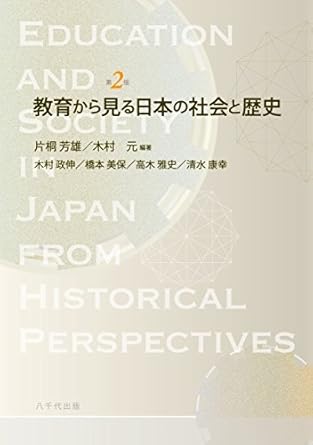 ■片桐芳雄・木村元編著/木村政伸・橋本美保・高木雅史・清水康幸著『教育から見る日本の社会と歴史』八千代出版、第二刷2017年
■片桐芳雄・木村元編著/木村政伸・橋本美保・高木雅史・清水康幸著『教育から見る日本の社会と歴史』八千代出版、第二刷2017年




