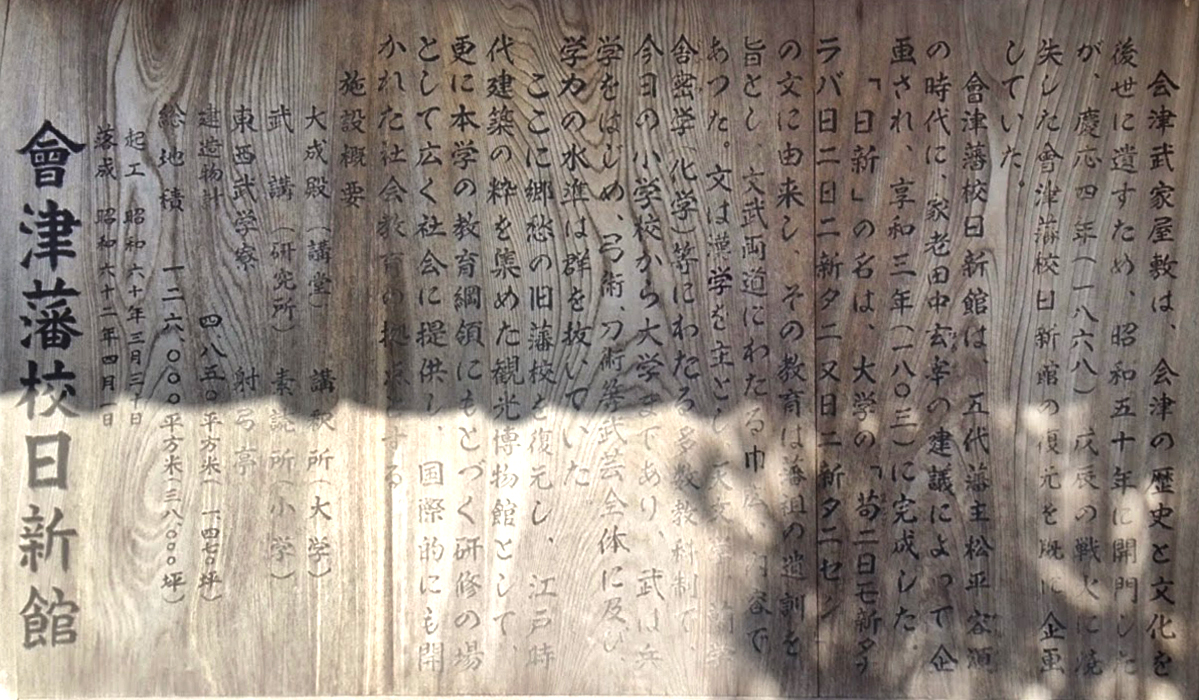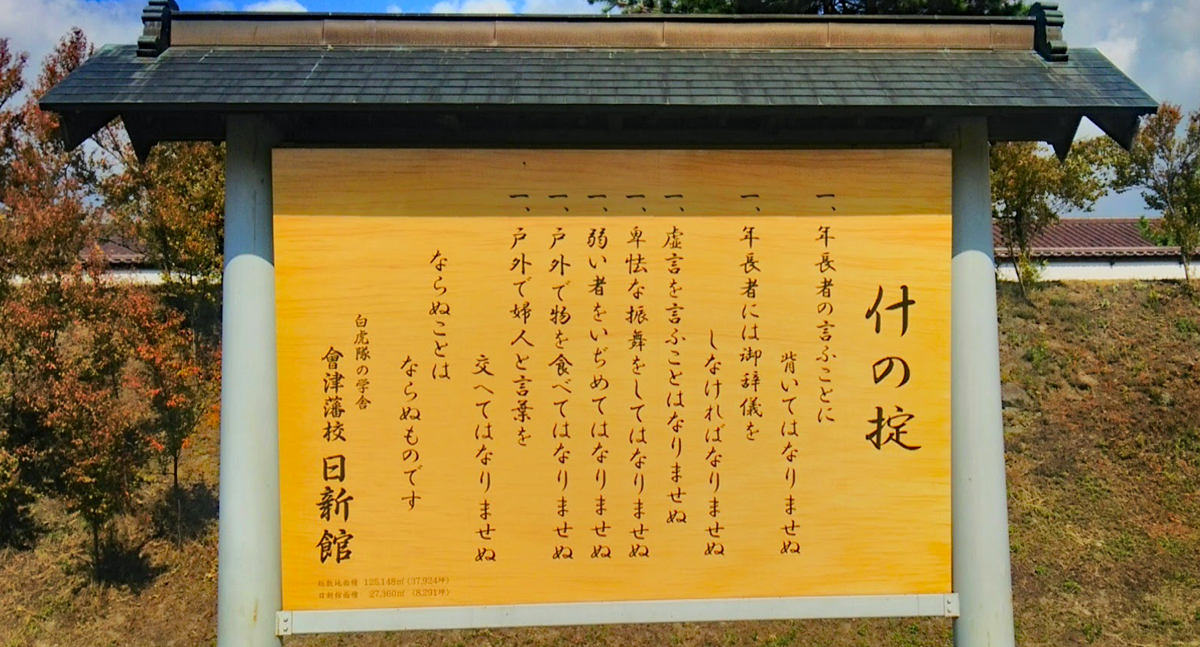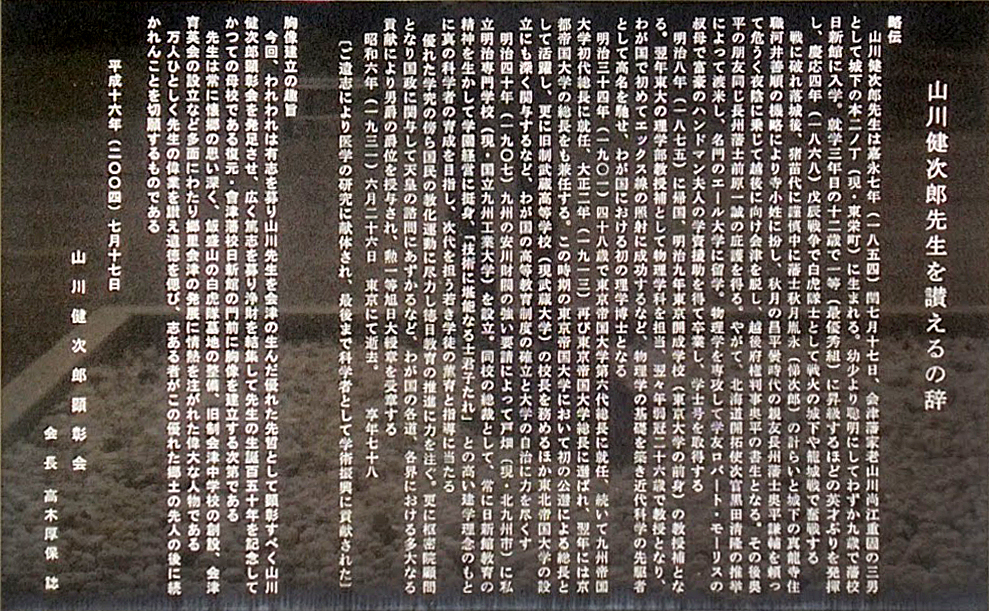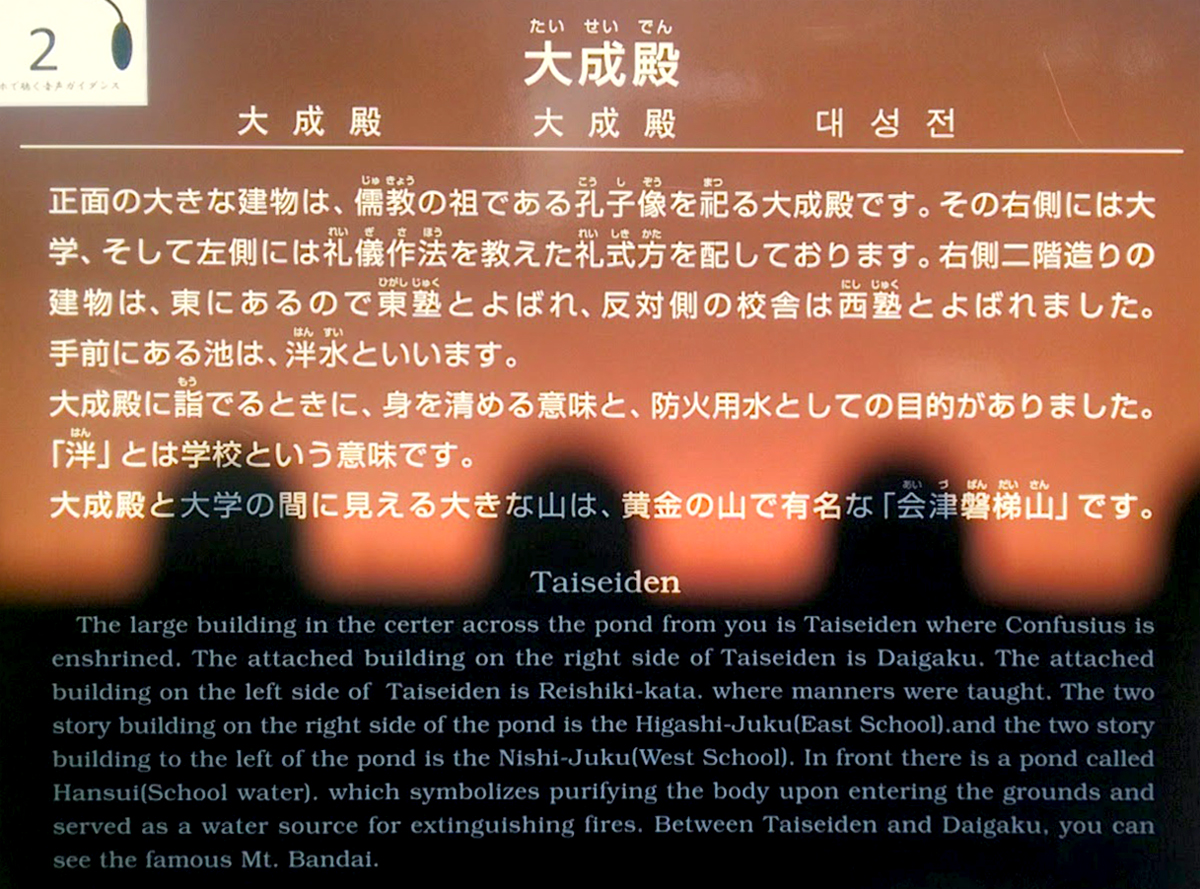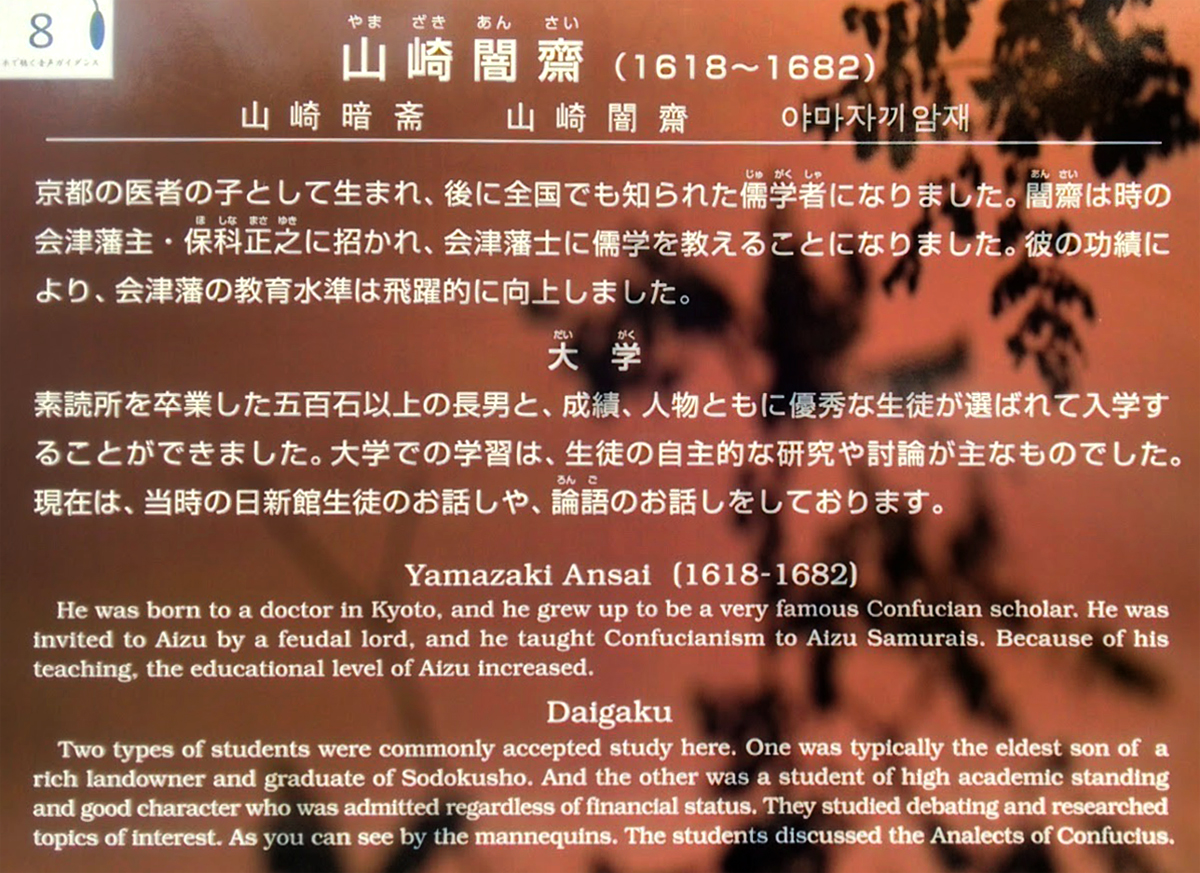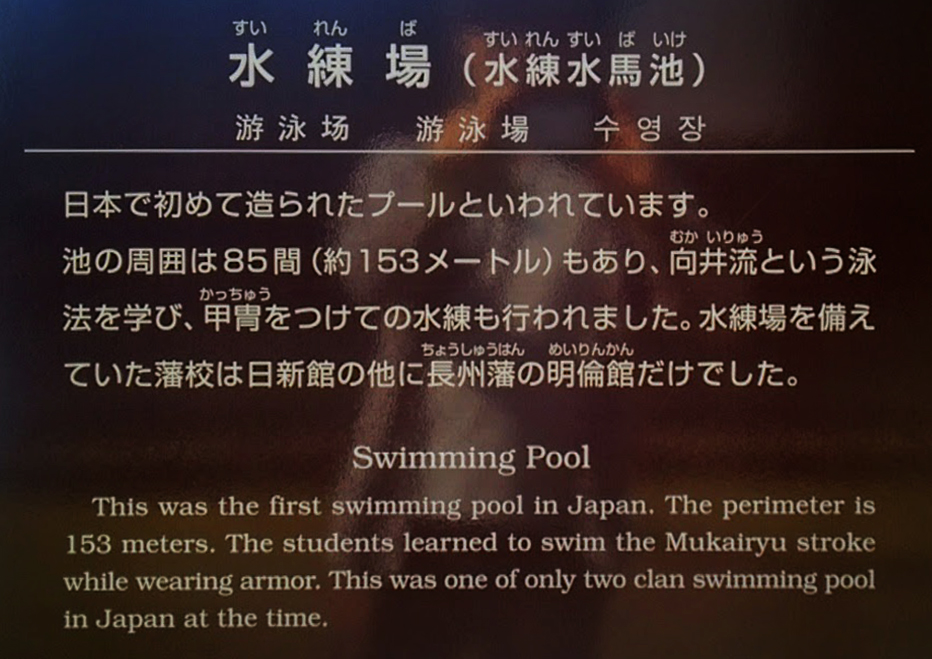【紹介】コミュニティ・スクールと一口に言っても、その実態は地域と時代によってバラバラです。現代日本のコミュニティ・スクールには二つの源流があります。一つは学校のガバナンスに重点を置いて地方分権を志向する行政的な発想で、教育改革国民会議など規制緩和論者が推進するような、校長の権限を強化するアメリカのチャーター・スクールをモデルにしたものです。もう一つはソーシャル・キャピタルとの連携に重点を置くもので、地域と学校の連携を実践する現場から立ちあがって来たような、カリキュラム論など教育学的な発想から生じた流れです。現在の制度は、この2つの流れが交錯したところで成立しています。本書では東京都足立区の事例を取り上げていますが、こちらは学校のガバナンスを比較的重視した制度設計となっています。
また、本書はアンケート等を利用した統計調査の分析が充実しており、教育委員会や校長の本音が垣間見えるなど、現在のコミュニティ・スクールの実像がよく分かります。
さらに「Q&A」が充実していて、委員会規則の傾向や委員の人数・任期など具体的な方針が分かり、これからコミュニティ・スクールを立ち上げようとする行政関係者や教育関係者にとっても大いに参考になりそうです。
【感想】コミュニティ・スクールの論理、現状と課題、これから立ち上げを考えている人々に向けての指針など、全方位に渡ってコンパクトに分かった気にさせてくれる、よくまとまったいい本だと思った。特に現在のコミュニティ・スクールの制度が、2つの異なる発想が組み合わさってできていることに関しては、とても分かりやすかった。教育改革国民会議で発議された時にはそこそこ過激な規制緩和論だったコミュニティ・スクールが、中央教育審議会の議論を経てそうとう骨抜きになって、現在の形に落ち着いたのだろうことが伺える。規制緩和論者からしたら中教審はさぞかし保守的で頑固な「抵抗勢力」に見えることだろうが、現状の日本社会にチャーター・スクールをそのまま導入したら既存の公立学校どころか地域社会そのものを破壊しかねないことを考えると、まあ、落ち着くべきところに落ち着いた感じはしなくもない。
とはいえ、現在はもの凄い速度で教育行政改革と教育課程改革が進んでおり、この2つがクロスしたところでコミュニティ・スクールが要となって抜本的な大変革に至る可能性はあるだろうと思う。たとえば新学習指導要領で「カリキュラム・マネジメント」が前面に打ち出され、各学校が自律的な教育課程編成を行なうように方向付けがなされたわけだが、現状ではこの教育課程編成の主導権を握るのが校長だとしても、今後は学校運営協議会が積極的に教育課程編成に関与することがあり得るだろう。あるいは学校運営協議会が率先して教育課程編成をリードしていくことを見越して、「学校評価」と一体となった「カリキュラム・マネジメント」が打ち出されたとも見えるわけだ。そしてそれが向かう先には、学校運営協議会が自らの教育方針に従って校長人事(民間人校長含む)を決定づけるような、実質的にはチャーター・スクールとして機能するような制度が見える。そしてその傾向は、本書で示された教員人事に対するアンケートで、校長としては学校運営協議会が人事に介入することに反対の姿勢を示しているのに対し、一方地域の保護者たちは関与することを積極的に望んでいるという事実に垣間見える。地域の保護者たちが望む教員人事の最たるものは、「校長人事」に他ならない。地域の意向で校長人事が左右されることになれば、それは実質的にはチャーター・スクールだ。
現在のところ、地域住民もチャーター・スクール等の制度設計を知らないせいもあるだろう、校長人事に介入しようという動きは表面化していない。現状のコミュニティ・スクールでは穏健な「ソーシャル・キャピタルの調達」という機能が前面に打ち出されている。しかし今後、地域社会の崩壊がより一層進行し、新自由主義的な傾向を示す保護者が増加し、公立中高一貫校が定着し、規制緩和論者がチャーター・スクールの知識の普及に成功するような状況が重なれば、現在のコミュニティ・スクールは容易にチャーター・スクール的なものに変貌するのではないかとも思えてくる。それはそれで時代の趨勢であって抗うものではないのかもしれないが、さてはて。今後のコミュニティ・スクールの行方に対して、教育学者としては着目せざるを得ないのだった。