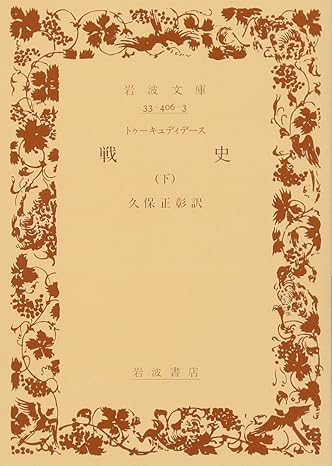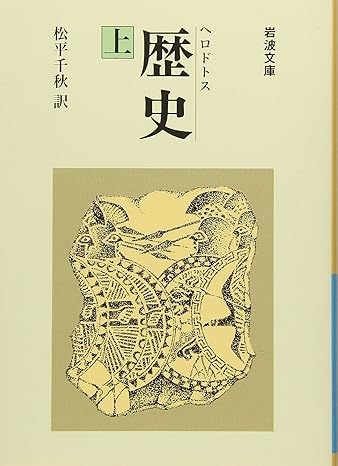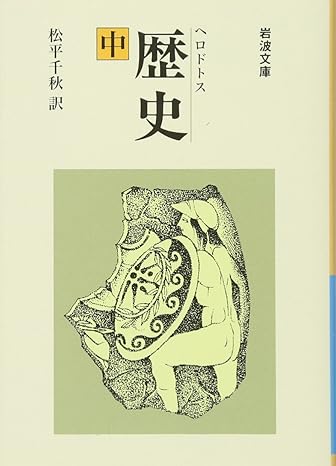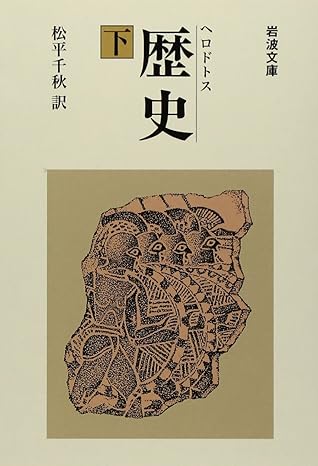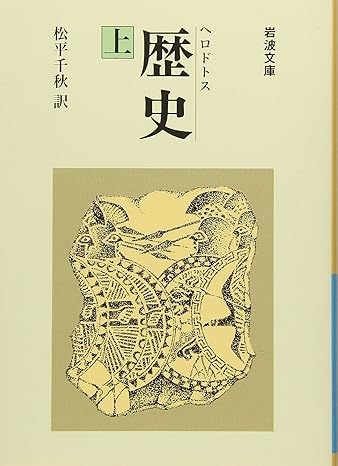
 【要約】「歴史の父(キケロー談)」とも称されるヘロドトスの作品です。題材は紀元前5世紀前半にアケメネス朝ペルシアとギリシア連合軍との間で起こった戦争で、その原因と経緯について記しています。ところが、単に一連のペルシア戦役そのものを記すだけではなく、ペルシアを始めとする様々な民族の生活習俗に加え、人文地理や自然生態系についての情報も事細かく記しています。扱われる諸民族は、東は小アジアや黒海周辺の遊牧民族から、果てはウラル山系へ至り、南はエジプトを超えてナイル川奥地まで及びます。現代の感覚で言う「歴史」というよりは、戦争を中心的な題材としつつも、総合的な「地誌学」となっています。
【要約】「歴史の父(キケロー談)」とも称されるヘロドトスの作品です。題材は紀元前5世紀前半にアケメネス朝ペルシアとギリシア連合軍との間で起こった戦争で、その原因と経緯について記しています。ところが、単に一連のペルシア戦役そのものを記すだけではなく、ペルシアを始めとする様々な民族の生活習俗に加え、人文地理や自然生態系についての情報も事細かく記しています。扱われる諸民族は、東は小アジアや黒海周辺の遊牧民族から、果てはウラル山系へ至り、南はエジプトを超えてナイル川奥地まで及びます。現代の感覚で言う「歴史」というよりは、戦争を中心的な題材としつつも、総合的な「地誌学」となっています。
戦争そのものは、第一次ペルシア戦争(ダレイオスⅠ世)ではマラトンの戦いでギリシア連合軍が勝利し、第二次(クセルクセスⅠ世)ではアテナイが一時的に占領されるもののサラミス海戦でギリシア連合軍が逆転勝利、さらに第三次(マルドニオス将軍)でもプラタイアの戦いでギリシア連合軍が勝利します。
著者ヘロドトスは、「自由」を求めるギリシア精神の勝利であったことを強調しています。
 【感想】読み始める前は、がっつりペルシア戦争の記述があるものだと思い込んでいたけれども、戦争自体の記述はかなりアッサリ風味だった。戦闘シーンのボリューム自体が、かなり少ない。戦闘シーンで分量がたくさんあったのは、テルモピュライの戦いの経緯くらいかなあ。一方で、戦争に至るまでの外交などの心理的な駆け引きや、神に犠牲を捧げる儀式の段取りや、神託を求める経緯や、下された神託に対する多様な解釈や、両陣営の作戦会議の記述等が、めちゃくちゃ長い。まあ、クラウゼビッツも言っているとおり、戦争というのは戦闘行為そのものよりも、そこに至るまでの準備で勝負が決まっているということなんだろうけれども。
【感想】読み始める前は、がっつりペルシア戦争の記述があるものだと思い込んでいたけれども、戦争自体の記述はかなりアッサリ風味だった。戦闘シーンのボリューム自体が、かなり少ない。戦闘シーンで分量がたくさんあったのは、テルモピュライの戦いの経緯くらいかなあ。一方で、戦争に至るまでの外交などの心理的な駆け引きや、神に犠牲を捧げる儀式の段取りや、神託を求める経緯や、下された神託に対する多様な解釈や、両陣営の作戦会議の記述等が、めちゃくちゃ長い。まあ、クラウゼビッツも言っているとおり、戦争というのは戦闘行為そのものよりも、そこに至るまでの準備で勝負が決まっているということなんだろうけれども。
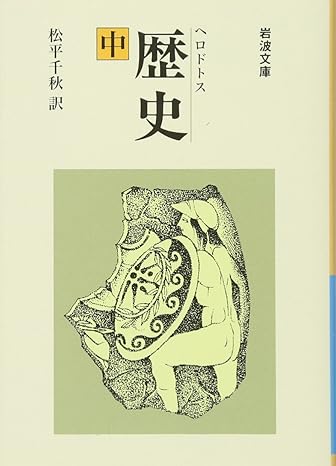 それから戦争そのものに関して、てっきりペルシアとギリシア連合軍が真正面から戦ったものだと思い込んでいたら、いやいや、実際の経緯はそんなに単純なものではなかった。
それから戦争そのものに関して、てっきりペルシアとギリシア連合軍が真正面から戦ったものだと思い込んでいたら、いやいや、実際の経緯はそんなに単純なものではなかった。
まずギリシア連合軍が、全然一枚岩ではない。裏切りだらけ。印象に残ったのは、たとえばアテナイを追放されてペルシア王の庇護を求めたギリシア貴族が、故郷に逆恨みして大王に入れ知恵をしてギリシアを攻めさせるエピソードだ。またあるいは、テバイ(ボイオティア)がライバルであるアテナイをやっつけるためにペルシア方に積極的に荷担する姿だ。ペルシア王に積極的に協力する姿勢には、ギリシア人であるという自覚は微塵も感じない。また最終的には協力するアテナイとスパルタにしても、事あるごとにお互いを出し抜こうという駆け引きを繰り返す。ペルシア軍が通過するギリシアの町々からもペルシア軍に参加する兵士が続出したりと、現在の「国民国家」の感覚で戦争をイメージすると、まったく意味が分からなくなる。まだ「国民意識」の欠片すら存在しなかった段階での古代戦争であったことをしっかり押さえて読む必要がある。
またペルシア方も、インドからアフリカ大陸、あるいは黒海周辺の諸民族の連合軍となっている。そして戦闘行為に突入すると、これら周辺諸民族がまさに烏合の衆で、まったく役に立っていない。数がどれだけ多かろうが、勝負の帰趨には影響を与えない。ヘロドトスはギリシア連合軍の勝利を「自由精神の勝利」であることを強調しているけれども、確かに「隷従」で集めた軍隊は、戦闘時にまったく役に立っていないことが分かる。戦争においては兵士たちの「帰属意識」の有無が極めて重要なことが分かる。
ペルシア対ギリシアという1対1の勝負ではなく、たくさんのプレイヤーが様々な思惑を持って戦争に参加している様子を見て、「ディプロマシー」というボードゲームを思い出した。本書の世界観を土台にして「ディプロマシー・紀元前5世紀版」を作ったら、けっこうおもしろくなるんじゃないかという気がした。プレイヤーは、アテナイ(アッティカ)・スパルタ(ペロポネソス)・テバイ(ボイオティア)・イオニア・スキュタイ・エジプト・ペルシアの7勢力がいいように思うのだが、如何か。今度ためしに作ってみようかな。
で、当時の国と国の違いは、現在の「国民国家」的な帰属意識とは違い、生活習俗の違いが決定的なものとして意識されているように見えた。食事や、服装や、葬式や、婚姻形態などで、敵と味方の区別がつけられているようだった。周知の通りプラトン=ソクラテスの議論では自然法と慣習法の相違が大問題となるわけだが、本書では「慣習」の持つ力がかなり強調されている(上巻355頁など)。
多少気になるのは、宗教の特徴については言及されるものの、信仰形態によって敵と味方が区別されているような感じがしないところだ。多神教的な世界観からだろうか、敵の神も尊重する姿勢が見える。というか、まったく違う文脈から出てきているはずの相手の神様を、著者が知っているギリシアの神様に当てはめて理解しているところに、現代的感覚からすると、たいへんな違和感がある。
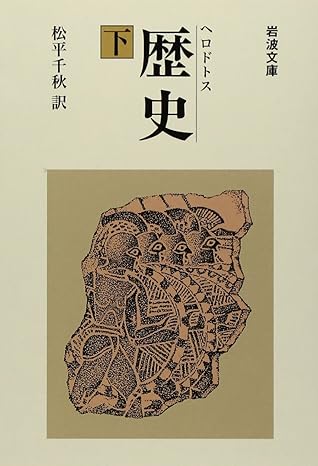 それから面白かったのは、いろいろなところで見て知っている事柄のモトネタが確認できたことだ。
それから面白かったのは、いろいろなところで見て知っている事柄のモトネタが確認できたことだ。
たとえば、「マラトンの戦い」の記述は本書6巻(中巻299頁)にあるのだが、巷で流布されているような戦捷報告のエピソードは、実はいっさい記されていない。実際は、アテナイからスパルタへ派遣された伝令の話が記されているに過ぎない。マラトンからアテナイへ走って絶命した兵士など記録されていないのに、間違って伝わっているのは、どうしてなんだろう? いちおう考えられるのは、すぐあとの記述で登場する、マラトンで勝利したアテナイ全軍がすぐさまアテナイ市内に帰還して市街防御にあたったエピソードだ(中巻307頁)。全軍が全力で帰還した話が、一人の伝令の疾走ネタと混同されてしまったのかもしれない。アテナイ軍のマラトンからの帰還は、秀吉の中国大返しも想起されて、それ自体がなかなか興味深い。
またホメロス『イーリアス』に登場する、トロイア戦争の原因となる女性ヘレネについて、実は本物の彼女はエジプトにいたのだというエピソードが本書に記録されている(上巻268-271頁)。そして著者ヘロドトスは、本物のヘレネはトロイアではなくエジプトにいたと考えればトロイア戦争の経緯を合理的に理解できると言う。当時から、一人の女をめぐって戦争が勃発したというのは不合理だと考えられていたことが分かる。
寓話で有名なイソップが奴隷だった話についても記されている(上巻284-285頁)。
それから、藤子・F・不二雄のSF短編集で「カンビュセスの籤」という話があるのだが、モトネタは本書にあった(上巻342-343頁)。いやしかし、私はすっかりギリシアに侵攻する途中の話だと思い込んでいたのだが、実際にはペルシア戦役とはまったく関係なく、カンビュセスが気の迷いでエチオピアに遠征する話だったとは。本書を読んで、改めて知った。
また、スパルタの300人がペルシア兵百万人を相手にするのも、本書がモトネタだ。テルモピュライの戦いは、本書の中では随一といっていいほどの戦闘描写だ。映画にしたくなるのも、よく分かる。
あと、RPGやライトノベル等で、強大なラスボスを倒すとき、味方の一人がラスボスを押さえつけながら「俺ごと剣で刺し貫け」と言うシーンを散見することがあるわけだが、そのモトネタは本書にあった(上巻391頁)。ダレイオスⅠ世が王位に就くエピソードで、味方のゴブリュアスが「構わぬからその剣で二人ごと突き刺せ。」と言っている。
さらには「背水の陣」を彷彿とさせるエピソードも記されている(中巻225頁)。
笑ってしまったのは、「ヨーロッパ」の語源となっているエウロペに言及したところだ。ヘロドトスは以下のように言っている。
「ともかくエウロペなる女がアジアの出身であることは明らかで、この女が今日ギリシア人がヨーロッパと称している土地へきたことはなく、せいぜいフェニキアからクレタ、クレタからリュキアまでしかいっていないことも明白である。」中巻35頁
いやあ、なんとなく私も「エウロペがヨーロッパの語源って、変だぞ?」と思っていたけれども、既に2500年前からおかしいと思われていたということが確認できて、よかった。
で、当然のことだけれども、「歴史の父」と言われているが、近代歴史学とはまったくの別物だ。伝聞に基づいたいい加減な記述も多く、「歴史」というよりは、人文地理学的(あるいは地誌学的)な教養を縦横無尽に駆使した戦記文学と言ったほうがいいような気がする。まあ、本書固有の価値がそれによって損なわれるわけでもないだろう。
【要確認事項】
異民族の習俗を記すところで、「妻を共有して自由に交わっている」(中巻71頁)ということが記されているが、こういう民俗学的な知識がプラトン『国家』で主張されるような妻や子どもの共有というアイデアへ影響を与えているかどうか。
処女を尊重する民族についての記述も出てくるが(中巻117頁)、アテナやアルテミス崇拝とも関係して、古代の処女尊重をどのように理解したらよいか。
【今後の研究のための備忘録】
本書には「自由平等」の概念に関して、興味深い記述がある。
「かくてアテナイは強大となったのであるが、自由平等ということが、単に一つの点のみならずあらゆる点において、いかに重要なものであるか、ということを実証したのであった。というのも、アテナイが独裁下にあったときは、近隣のどの国をも戦力で凌ぐことができなかったが、独裁者から解放されるや、断然他を圧して最強国となったからである。これによって見るに、圧制下にあったときは、独裁者のために働くのだというので、故意に卑怯な振舞をしていたのであるが、自由になってからは、各人がそれぞれ自分自身のために働く意欲を燃やしたことが明らかだからである。」中巻191頁
自由平等に関するこのような功利的な理解は、古代東洋には一般的に見られないような気がする。東洋専制と西洋自由の対比が鮮やかに浮かび上がってしまうところだ。この古代ギリシアの自由平等に関する観念が、近代西洋にどのような影響を与えたかは、やはり大きな論点になる。たとえば16世紀の半ばには、ラ・ボエシ(モンテーニュの親友)が言及している。
「これほどの勇気をもたらしたのは、ペルシア人に対するギリシア人の戦いというよりむしろ、支配に対する自由の、征服欲に対する自立への欲求の勝利であったと考えられまいか。」
ラ・ボエシ『自発的隷従論』17頁
そして自由な民は戦争でも有能だが、隷従する民は烏合の衆だという記述を確認できる。ラ・ボエシの言う「自由」は近代的な個を前提とした自由とは少々異なっているような気はするが、近代西洋への繋がりがゼロだと決めつけるわけにもいかない。
それから近代の「国民国家」を考えるための参照軸として、本書に見られる「ギリシアの実体化」に関して。アテナイからスパルタ使節団への言葉に以下のようなものがある。
「第二にはわれわれが等しくみなギリシア人同胞であり、血のつながりをもち言語を同じくし、神々を祀る場所も祭式も共通であるし、生活様式も同じであることで、アテナイ人がこの同胞を敵に売るようなことは許されることではあるまい。」下巻272-273頁
ここには、アテナイとスパルタという政体の相違を乗り超えて、ギリシア人全体を同胞として捉え、ギリシア人という「想像の共同体」を実体化する思考が確認できる。そして想像の共同体を実体化する理屈として、(1)血(2)言語(3)宗教(4)習慣という4つの要素が確認できる。「国民国家」は近代の産物であると言われるが、実は「想像の共同体」を実体化する理屈は古代から連綿と存在しているのではないか。
またたとえばテバイ人からペルシア人の言葉として以下のように記録されている。
「彼らはマルドニオスに、ギリシア人は過去に置いても協力一致する実を示してきたが、心を一にして団結したギリシア人を制圧することは全世界の兵力をもってしても困難であることを説き…」下巻275頁
周辺の諸民族に存在せず、ギリシアだけが持っているものこそ、「自由平等」であり、「協力一致」であった。そしてそれこそがギリシアの戦争での優位を担保した。想像の共同体が生み出す「協力一致」や「心を一にして団結」という「実」が戦争遂行に当たって極めて強力に働くことは、教育勅語が目指すところでもあった。想像の共同体に関する理論は、近代を待つまでもなく、古代ギリシアに用意されていたのかもしれない。
■ヘロドトス『歴史(上)』岩波文庫、1971年
■ヘロドトス『歴史(中)』岩波文庫、1972年
■ヘロドトス『歴史(下)』岩波文庫、1972年
 【要約】プラトン『国家』は長きにわたって誤読されてきました。これは「人間とは何か」について書かれている本です。
【要約】プラトン『国家』は長きにわたって誤読されてきました。これは「人間とは何か」について書かれている本です。