
 【要約】給食について、貧困・災害・運動・教育・世界史の5つの観点から多角的に考えることで、給食の歴史と思想の実相を捉えます。すると、給食とは「境界」にあるものだということが分かります。給食を通じて、日本や世界の姿がはっきりと見えてきます。
【要約】給食について、貧困・災害・運動・教育・世界史の5つの観点から多角的に考えることで、給食の歴史と思想の実相を捉えます。すると、給食とは「境界」にあるものだということが分かります。給食を通じて、日本や世界の姿がはっきりと見えてきます。
【感想】事前の予想に反して(と言ったら失礼で恐縮だけれども)、非常に情報量が多いにも関わらず論理的に明快で、読み応えがあって、勉強になり、様々なインスピレーションを与えてくれる本だった。おもしろかった。意表を突かれるような記述も多かったが、それだけ私の視野が狭かったということだ。目から鱗が何枚か落ちた。
本書の論理的な柱である5つの観点それぞれがいずれも重要な論点を提出している。たとえば「貧困」に関しては、私も個人的に地域の「子ども食堂」に少し噛んでいるわけだが、貧困対策の本丸は給食にあるという本書の記述には、激しく納得する。表面上はどれだけ「飽食」を叫ぼうとも、貧困は見えないところに確実に存在する。現在は、ますます貧困の実相が見えにくくなっている。その貧困を掬い上げるのが福祉の仕事のはずだ。ところが小さな子ども食堂ですら「教育/福祉」の境界をどう調整するかで悩ましい問題がたくさん生じているなか、給食ではさらに大変な問題に直面しているであろうことは想像に難くない。その問題を解くには、おそらく「教育/福祉」を一体化した理念を提出できるかどうかがポイントになるのだろう。やはり児童の権利条約の精神が鍵を握っている気はする。
そして「教育」に関しては、大学で栄養教諭養成に関わっていることもあって、多少は勉強して知っているつもりではあったものの、改めてその重要性を認識し直した。授業では学生に対して「食育基本法」の精神だとか「教科等横断的な視点」における食育指導について話をしているわけだが、やはりまずは給食に関する根本的な理念を土台に据えることが決定的に重要なのだと感じた。表面上の条文やカリキュラム規定を暗記しても、土台となる精神を理解していなければ、何の意味もない。
また、教育学者が給食に対して関心を持ってこなかったという告発には、頭が下がる思いがした。確かに教育学の世界では「学力」に関する論争は盛んに行なわれる一方で、「食」に関しては周辺的な領域に追いやられがちなのだ。単に「食」を学習の題材にするという意識では、おそらくいつまでも周辺的な要素に留まり続ける。既存の常識に固執するのではなく、「生活」という広い観点から本質的に発想を組み換える論理が必要とされているように思った。
また「世界史」に関して、アメリカの影響と新自由主義の波がこれほどダイレクトに給食に表れていることは、言われてみればナルホドではあるが、普段はさほど気にしないところではあった。給食ほど日常生活の中に「世界史」が組み込まれている例は、確かにあまりないかもしれない。一点突破全面展開の材料として、給食がこれほど実り豊かな成果を出し得るポテンシャルを持っていたものだったとは、不覚にも認識していなかった。著者の着眼点の鋭さと、着実な成果を挙げる研究手法の確かさには、かなり感じ入った。いい本だった。
個人的には「遅刻しそうになって食パンを加えながら学校へ急ぐ」という戯画的なエピソードが極めてアメリカ的な心性の反映であり、象徴であるという仮説を持っていたわけだが、本著の成果と研究スタイルは私の仮説を裏付けるのに何かしらの意味を持っているように感じた。
【今後の個人的研究のための備忘録】
教育という営みが本質的に抱え込むアポリアに対して誠実に向き合っている本は、実はそんなに多くないだろうと思った。だいたいは、アポリアを抱え続ける不安定な緊張に耐えられず、どちらか一方の立場から論を進めてしまうものだ。以下の記述は、なかなか感慨深く読んだ。
「給食は、国家に依存しない自立した人間をつくる、という考えは、当然、冷戦体制が急速に構築されていくなかで生じたものであるが、それ以上に、給食とは何かを根源的に問うものだ。なぜなら、学校とは社会の力で子どもを守るところであるとともに、一人の自立した人間として育てるところでもあり、厳守すべき社会のルールを学ばせつつ自己の独創性を育てなければならない、という、決して簡単には調和しない課題を引き受けており、日本の給食はまさにその教育の二面性の象徴だからである。」(123頁)
教育を仕事にするということは、この本質的なアポリアをアポリアとして断念したまま、それでも前に進む意志を持ちつづけるということだ。すぱっと割り切れないモヤモヤしたものをいつまでも抱え続ける勇気と根性が必要なのだ。いやはや。
本書が示した「境界」という言葉は、どちらか一方に倒れ込むことなく緊張感を保つための、よい戒めの言葉だと思った。境界に立っていることを自覚できれば、軽率に一方に決め込む愚を避けられる。
■藤原辰史『給食の歴史』岩波新書、2018年
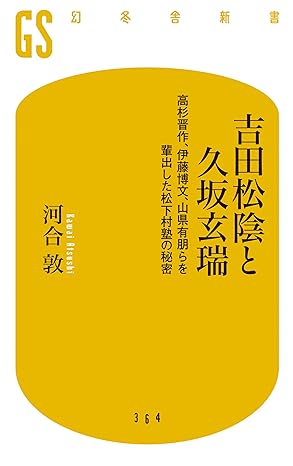
【要約】吉田松陰の人となりが、松下村塾の塾生たちに大きな影響を与えました。



