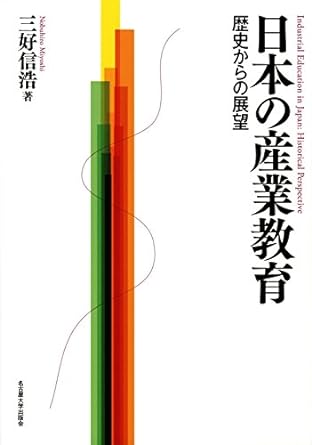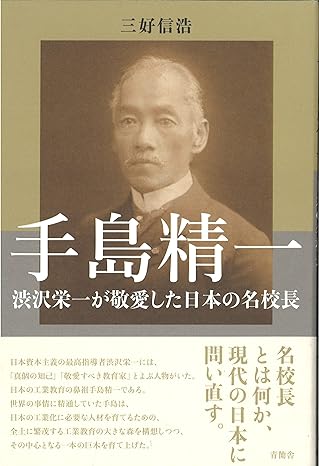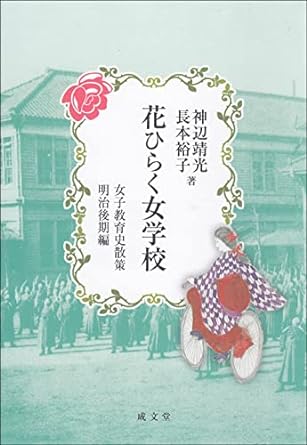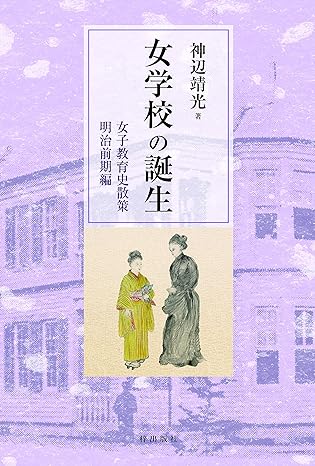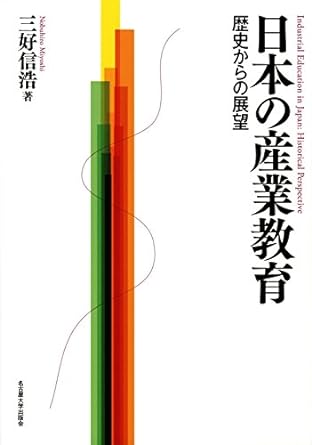 【要約】明治期から昭和戦前期にかけての産業教育(工学・農学・商学)の全体像を、学校数や生徒数などの統計、時代背景、学校沿革史、校長などキーパーソンの教育思想などの分析を通じて多角的に示した上で、現代の産業教育(あるいは日本の教育全体)が抱える課題の核心と解決への見通しを示します。
【要約】明治期から昭和戦前期にかけての産業教育(工学・農学・商学)の全体像を、学校数や生徒数などの統計、時代背景、学校沿革史、校長などキーパーソンの教育思想などの分析を通じて多角的に示した上で、現代の産業教育(あるいは日本の教育全体)が抱える課題の核心と解決への見通しを示します。
【感想】さすがに長年の研究の蓄積があり、教育史的に細かいところまで丁寧に神経が行き届いているのはもちろん、本質的な概念規定についても射程距離が長く、とても勉強になった。概念規定に関しては、いわゆる「普通教育」と「専門教育(職業教育)」の関係に対する産業教育の観点からの異議申し立てにはなかなかの迫力を感じる。本書でも触れられているとおり、総合高校などの改革にも関わって極めて現代的な課題に触れているところだ。この問題をどう考えるにせよ、本書は必ず参照しなければならない仕事になっているだろう。
【個人的な研究に関する備忘録】人格
個人的には「人格」概念の形成について調査を続けているわけだが、人格教育に偏る講壇教育学に対する産業教育思想からの逆照射はかなり参考になった。大雑把には、明治30年代以降は産業教育界でも「品性の陶冶」とか「人格形成」などが唱えられるようになった姿が描かれていたが、おそらくそれはヘルバルト主義の影響(本書ではヘルバルトの「へ」の字も出てこないが)で間違いないと思う。しかし昭和に入ると、「人格形成」という概念に対して疑義が呈せられるようになっていく。そして敗戦後はいったん「人格」が再浮上するわけだが、1970年代以降にまた説得力を失っていく。さて、この「人格」の浮沈をどう理解するか。
針塚長太郎(上田蚕業学校初代校長)『大日本蚕糸会報』第154号、1905年3月
「教育の期するところの主たる目的は、其業務に関する諸般の事項に就き綜合的知識を授け、業務経営の事に堪能ならしめ、兼て人格品性を育成し、以て社会に重きを致し、健全なる常識に富むみたる者を養成するにあり」
尾形作吉(県立広島工業学校初代校長)『産業と教育』第2巻10号、1935年10月
「産業と教育といふ題目は余りに大きな問題で、我々世間知らずに只教育といふ大きな様な小さな城郭に立籠つて人格陶冶や徳性涵養一点張りの駄法螺を吹いて居つた者の頭では到底消化し切れないことである。」
【個人的な研究に関する備忘録】instruction
また、教育(education)と教授(instruction)に関して、ダイアーの言質を得られたのも収穫だった。
「私がまず第一に申したいことは、日本では教育の中心的目的がまだ明確に自覚されなかったことであります。それが単なる教授(instruction)と混同されることがしばしば見られます」(Veledictory Address to the Students of the Imperial College of Engineerting)ダイアー1882年の離別の演説。
VeledictoryとあるのはValedictoryの誤植だろうか。ともかく、ここでダイアーが言う「教育」とは「education」のことだろう。本書では特にeducationとtrainingの違いに焦点を当てて話が進んだが、より理論的にはeducationとinstructionの違いが問題になるはずだ。ダイアーもそれを自覚していることが、この離別の演説から伺うことができる。乱暴に言えば、educationのほうは品性や倫理などを含めた全人的な発達を支える営みを意味するのに対して、instructionは人格と切り離された知識や技能の伝達を意味する。ダイアーの言う「教育=education」の意味は、もっと深掘りしたらおもしろそうだ。
【個人的な研究に関する備忘録】女子の産業教育
そして女子の産業教育についても一章を設けて触れられていたが、全体的なトーンとしては盛り下がっている。
「これまでの日本の近代女子教育史の研究物は、高等女学校の教育を中心にしてきたうらみがある。しかし、産業教育の指導者たち、例えば工業教育の手島精一、農業教育の横井時敬、商業教育の渋沢栄一らは、高等女学校に不満を抱き、よりいっそう産業社会に密着した教育を求めてきた。」p.287
「日本の職業学校がこのように産業から遠ざかった理由は多々あるであろうが、その一つとして共立女子職業学校の先例がモデルにされたことも考えられる。同校は、一八八六(明治一九)年という早い時期に宮川保全を中心とする有志によって各種学校として設置された。岩本善治の『女学雑誌』のごときはその企図を美挙として逐一紹介記事を載せた。」pp.271-272
「日本の女子職業学校の先進校である共立女子職業学校が裁縫と並んで技芸を重視したこと、中等学校の裁縫科または裁縫手芸家の教員養成をしたことは、戦前期の女子の「職業」の範囲を区画したものと言えよう。」p.272
どうだろう、問題の本質は学校の有り様どうこうというよりは、「裁縫」の技能が家庭内に収まるだけで産業として成立しなかったところにあるような気がするのだが。実際、学校の有り様如何にかかわりなく、ユニクロが栄えだしたら裁縫学校は衰えるのである。
■三好信浩『日本の産業教育―歴史からの展望』名古屋大学出版会、2016年
 【紹介】近世から近現代まで、教育史に関わる人物の簡単なプロフィールと思想を簡潔に紹介しています。それぞれその道の専門家が書いており、簡にして要を得た内容となっています。人物とその仕事を通じて、その時代の教育の特徴や課題も分かるようになっています。
【紹介】近世から近現代まで、教育史に関わる人物の簡単なプロフィールと思想を簡潔に紹介しています。それぞれその道の専門家が書いており、簡にして要を得た内容となっています。人物とその仕事を通じて、その時代の教育の特徴や課題も分かるようになっています。