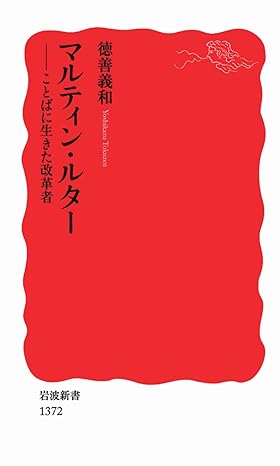【要約】16世紀西洋に始まった「第一の近代」は、20世紀には「第二の近代」へと変容しました。第一の近代が揺らいでいる現在、新しいデモクラシーの形が必要とされています。その鍵が「討議」です。
■確認したかったことで、期待通り書いてあったこと=近代の始まりと終わりについての簡潔な見解。近代への道は中世後期(10世紀)から徐々に用意されていたが、16世紀に初期近代が開始され、18世紀半ばに本格的に確立した。まあ、教科書的にはこれで特に問題ない見解と言えますよね、という確認。ルネサンスに近代性を見るか中世性を見るかなんて、マニアックな関心だよなあ。
「ポストモダン」論のように近代が完全に終焉したと極論するのではなく、「第二の近代」というふうに近代を段階的な展開過程として捉える見方。注目する事象そのものは諸々のポストモダン論とそう変わらないけれど、断定口調で時代の断絶を煽るようなポストモダン論とは異なっていて。「第二の近代」と理解する方が、漸進的に議論を積み重ねていこうとする実践的な知恵に優れているように思う。
■図らずも得た知識=日本において「市民社会」概念が議論されていたこと。市民社会論の系譜を辿りつつ、「私」とも「公」とも異なる「公共」という第三の領域を際立たせるという論の運びっぷりは、抽象的に鮮やかで、とても参考になった。真似する。
【感想】今から13年前に出版された本だけど、ものすごく古く感じてしまうのは、現実の変化が早すぎるからなのか。イギリスのEU離脱とトランプ大統領誕生を目の当たりにすると、本書の内容は残念ながら牧歌的に見えてしまう。仕方ない。
筆者が推奨している「討議的デモクラシー」の概念にしても、twitter等でろくに相手の文章も吟味せずに短絡的に「敵-味方」感覚だけで条件反射で吹き上がっている人々を見ると、異なる価値観の人々の間での合理的な討議なんてものが可能かどうか、つい短絡的に悲観してしまう。いや、言葉を発せるだけ、まだマシなのかもしれない。誰の視界からも消えているような、左にも右にもなれない声なき人々の残念な姿を見ると、デモクラシーなんて言っている場合か、と意気消沈してしまう。日本はサバルタンだらけですよ。
短絡的には悲観的になっちゃうにしても、10年スパンで大局的に見たときには、まだ本書が言うところの「楽観主義」は有効であり得る。それを信じて、少なくとも自分の声が届く範囲では、合理的かつ誠実な言葉を吐き続けるしかない。