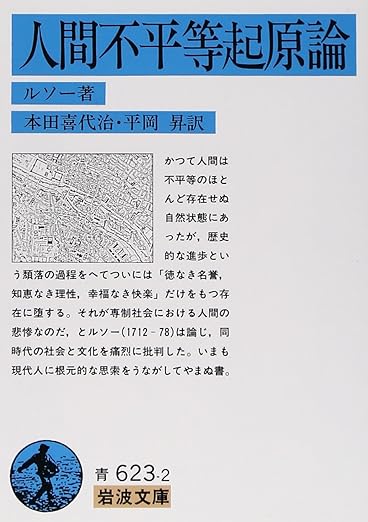【要約】人間はもともと自由で平等なものとして生まれたので、あらゆる社会秩序は自然にできたものではないし、力に基づくものでもなく、約束で成立しているものです。社会秩序を作るには、それがどういう形(君主制・貴族制・民主制)になるにせよ、まず人々がバラバラの烏合の衆ではなく、ひとかたまりの人民になっている必要があります。この、社会秩序が形成される前提として人々同士が結合する最初の約束が「社会契約」であり、それは共同体に属する構成員すべての人格と財産を守るための約束です。これを実現する条件は、すべての人間が一切の権利を共同体に譲渡したうえで、一人一人が共同体全体にとって切り離せない不可欠な一部となることです。それによって自我と生命を持つ一つの集合的精神が誕生し、主権者となります。各構成員は主権者の一般意志に従うことで、契約締結以前の自由と平等をそのまま受け取ります。しかし権利だけ主張して義務を果たさない個人の不正は共同体を破壊するので、一般意志への服従は絶対強制です。こうして自然状態で自然的に自由だった人間は、社会状態で市民的に自由となり、道徳的自由も手に入れて、初めて自分の主人となることができます。
【要約】人間はもともと自由で平等なものとして生まれたので、あらゆる社会秩序は自然にできたものではないし、力に基づくものでもなく、約束で成立しているものです。社会秩序を作るには、それがどういう形(君主制・貴族制・民主制)になるにせよ、まず人々がバラバラの烏合の衆ではなく、ひとかたまりの人民になっている必要があります。この、社会秩序が形成される前提として人々同士が結合する最初の約束が「社会契約」であり、それは共同体に属する構成員すべての人格と財産を守るための約束です。これを実現する条件は、すべての人間が一切の権利を共同体に譲渡したうえで、一人一人が共同体全体にとって切り離せない不可欠な一部となることです。それによって自我と生命を持つ一つの集合的精神が誕生し、主権者となります。各構成員は主権者の一般意志に従うことで、契約締結以前の自由と平等をそのまま受け取ります。しかし権利だけ主張して義務を果たさない個人の不正は共同体を破壊するので、一般意志への服従は絶対強制です。こうして自然状態で自然的に自由だった人間は、社会状態で市民的に自由となり、道徳的自由も手に入れて、初めて自分の主人となることができます。
一般意志は個別の案件に口を出すことはなく、常に全員に関わる公の利益だけ考えるので間違うことは絶対にありませんが、しかし啓蒙されていない民衆の議決は個人の利害に左右されて間違うことがあります。特に部分的団体が影響力を持ち始めたり、国が大きすぎたり小さすぎたり、代議制に頼ったり、人々が金儲けばかりに関心を持ち始めるとおかしくなりやすく、憲法制定は人民の成熟度合いや隣国との関係など極めて厳しい条件を満たしていなければ不可能です。
執行権を持つ政府は、主権とは異なる単なる仲介団体であり、一般意志に従うべき公僕です。政府の適切な大きさや種類(民主制・貴族制・君主制)は主権者が置かれた状況や環境によって異なります。良い政府か悪い政府かを決めることは一概にはできませんが、目安としては、人口が増えているときは良く、減っているときには悪いと考えていいでしょう。政府が堕落すると国家が解体します。
社会契約が成立した以上、健全であれば投票によって過半数で決まったことは一般意志の決定と前提できるので、少数者も従いましょう。もしも一般意志が過半数の側になければ、反対側の意見も一般意志ではなく、国内に別々の国(つまり一般意志)があったというだけのことです。行政官の選出は抽籤によるのがいいでしょう。実際の選挙制度や行政の仕組みについては古代ローマを参考にしましょう。最後に宗教について、これはもともと主権者にとっては国家の法に結びついたもので問題になりませんでしたが、世俗的な権力と切り離されて反俗世(反社会)的な権力となったキリスト教は様々な問題を生じさせます。そこで主権者はキリスト教も含めた既存の宗教とは異なる「純粋に市民的な信仰告白」を決めて、それを信じない者は追放したり、信じたふりをした者は処刑するべきです。そうできないなら、市民生活と矛盾しないあらゆる宗教に対して寛容であるべきです。
【感想】自然状態から社会状態に移行する条件についての記述は、極めてアッサリ風味で、訳文では4行で説明される。このあたりは別著『人間不平等起原論』で説明したということなのだろう。本書は社会状態を実現する前提と条件について掘り下げている。
社会状態の記述は、解説が指摘するとおりホッブズの論理を換骨奪胎したものだろう。たとえば一般意志へ絶対服従を説く点など、リヴァイアサンの絶対性とまったく変わりがない。ただしもちろん決定的に異なるのは、ルソーにおいては主権者が人民自身という点にあり、ホッブズにおいて同じものであった主権者(国)と政府をルソーは厳密に峻別する。ホッブズにおいては絶対的権力者であった行政のトップ(君主)は、ルソーにおいてはただの公僕(政府)だ。そして国と政府はそれぞれ違うものだという洞察から、国にとって都合の悪い政府は取り替えてもよいという革命的な結論が導かれる。また、原理的に自由を否定して必然性を強調するホッブズが普遍的な「自然法」を前面に打ち出しているのに対し、ルソーのほうはいったんすべての共同体に通底する原理的な社会契約を結んだあとは個別の一般意志(必ずしも自然法に従わない)による自由で個性的なルール作りを認めている(57頁「法について」)。ただし自由なルール作りと言ってもその集団固有の慣習や世論というものに従うことになるので、現実的にはモンテスキューに近い感じか。
いっぽうロック『統治二論』と異なるのは、ロックが「服従契約」を祖述したのに対し、ルソーがそれ以前の「社会契約」の段階を前面に打ち出した点にある。ロック理論で抵抗権の根拠が曖昧になるのは、単なる服従契約では政府への抵抗が被支配者の側からの契約解除という形をとってしまうからだ。しかし社会契約に基づくルソーの論理では、政府が主権者(国家)と完全に切り離された別の法人格として扱われるので、単に政府を覆しただけでは主権者(国家)の側の契約不履行とはならない。つまり「主権」の所在を人民主権と明確に規定したことで理論上の紛れがなくなっている。
具体的に憲法を制定して政府を作るところでは、明治維新後の日本の歩みが自然と想起される。明治15年から伊藤博文が西欧各地を巡って憲法調査を行うが、どこに行っても誰に聞いても日本人民の未熟さを指摘されて憲法制定など時期尚早と諭される羽目に陥る。その際、伊藤を諭した法学者がルソーを意識していたかどうかは分からないが、憲法を制定する前提として人民が成熟していなければならないという認識は共有されている。伊藤はプロイセンでシュタイン国家学に出会って憲法制定への道筋を見出すことになるが、それはやはり人民主権を前提するルソー流ではなく、家産国家の延長として行政を理解する官房学(ポリツァイ)の系譜に連なる。
また「市民宗教」の下りは、露骨に教育勅語を想起させる。ひょっとしたら井上毅はルソーを読み込んでいたかもしれない。自由民権運動の論理的支柱であったルソーの名前を井上毅があからさまに前面に打ち出すことはなくても、社会契約論の論理については当然勉強しているはずだし、「市民宗教」の理屈に何かしらの光明を見出していても不思議はない。
そんなわけで、本書は確かに徹底的な人民主権論に立ち、後の市民革命を正当化する理論的支柱となった民主主義のバイブルに違いないのだろうが、やはり一方で(ルソーは本書内で気を使って書いてはいるものの)全体主義に利用されてしまう空気も纏っているように思える。私が思うところでは、本書の限界は一国内民主主義に留まり、グローバルな視点に欠けている点にある。どれだけナショナルな単位で人民主権が成立しようとも、いやむしろナショナルな単位で人民主権が成立してしまうがゆえに、国際秩序は剥き出しの「力」が支配するホッブズ的な闘争世界に陥る。大日本帝国を想起するまでもなく、目の前で繰り広げられるロシアによるウクライナ侵攻とかイスラエルによるガザ破壊とかアメリカの独善的な振る舞いを見れば、一国単位の人民主権の限界は明らかだ。そしてそれはルソーが結論において「残されている問題」と記述したものに他ならない。
またあるいは国内に二つの国が分裂するという問題については、ジェンダー論や世代論、あるいはアメリカの分裂などが想起される。これを単に本書のように「2つの国がある」と切って捨ててよいのか。ルソーは通分可能な人々の間で成立する社会契約で押し通したが、もはや同類項を想定できない通分不可能な多様性において「共存」が成立する原理を考えなくてはいけないのではないか。
ただ本書を民主主義の聖典としてありがたがっている場合ではなく、人類はその限界を認識して次のステージに進まなければいけない時期に来ていると思う。
【要検討事項】身体
本文中の訳語で「身」とか「身体」となっているところは、原文を確認しておきたい。というのは、それがフランス語ではpersonneであり、実質的には「人格」と理解するべきものである可能性がある上に、本文中に「一般意志」という言葉が最初に使われる文章にも関わってくるからだ。
「各構成員の身体と財産を、共同の力のすべてをあげて守り保護するような、結合の一形式を見出すこと。」29頁
原文:Trouver une forme d’association qui défenfe et protége de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s’unissant a tous, n’ovéisse poutrant qu’a lui-même, et reste aussi libre qu’aparavant.
「われわれの各々は身体とすべての力を共同のものとして一般意志の最高の指導の下に置く。そしてわれわれは各構成員を、全体の不可分の一部として、ひとまとめとして受け取るのだ。」31頁原文:Chacun de nous met en commun sa peronne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale; et nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout.
「臣民は公けの平穏を、市民は個々人の自由を誇る。一方は、財産の安全を、他方は、身体の安全を欲する。」118頁
「政治体は、人間の身体と同様に、生まれたときから死にはじめ、それはみずからのうちに、破壊の原因を宿している。」125頁
「最下層の市民の身体も、最上級の行政官の身体と同じく神聖で不可侵なものになる。」130頁
「市民たちが自分の身体でよりも、自分の財布で奉仕するほうを好むにいたるやいなや(後略)」131頁
で、少し調べたところでは、予測通り訳文で「身体」とか「身」となっている原語の多くはフランス語でpersonneとなっていた。そしてそうだとすると、「身体」よりも「人格」と理解した方がルソーの趣旨が徹底する場面も多いように思う。というのは、ルソーは単に物理的に身柄を云々したいわけではなく、自由や道徳性や尊厳も含めた「人格」を対象としたかっただろうからだ。
【個人的な研究のための備忘録】人格
ということで、本書ではpersonneという単語が連発され、訳書でも「人格」という言葉が使われるが、注目したいのはそれが有機体論的に使用されている点だ。「人格」の用法という観点から見ると、ホッブズに近く、ロックから遠い。
「この結合行為は、直ちに、各契約者の特殊な自己に代って、一つの精神的で集合的な団体をつくり出す。その団体は集会における投票者と同数の構成員からなる。それは、この同じ行為から、その統一、その共同の自我、その生命およびその意志を受けとる。このように、すべての人々の結合によって形成されるこの公的な人格は、かつては都市国家という名前をもっていたが、今では共和国(Republique)または政治体(Corps politique)という名前をもっている。それは、受動的には、構成員から国家(Etat)とよばれ、能動的には主権者(Souverain)、同種のものと比べるときには国(Puissance)とよばれる。構成員についていえば、集合的には人民(Peuple)という名をもつが、個々には、主権に参加するものとしては市民(Citoyens)、国家の法律に服従するものとしては臣民(Sujets)とよばれる。」31頁
「外部のものにたいしては、この団体は、単なる一存在、一個人となるのだから。」33頁
「そして彼は、国家を構成する精神的人格を、それが一個の人間ではないという理由から、頭で考え出したものとみなし、臣民の義務をはたそうとはしないで、市民の権利を享受するであろう。」35頁
こうして国家に「精神的人格」を見出したルソーは、有機体論的な記述を次々と繰り出す。
「彼らは、主権者をば、いろいろな部分をよせ集めて作られた架空の存在にしている。それは多くのからだ――眼だけしかもたない、腕だけしかもたない、あるいは足だけしかもたないところの、からだから人間を作るようなものである。」44頁
「もし、国家または都市が精神的人格にほかならず、その生命が構成員の結合のうちに成りたつとすれば、また、国家の配慮のうちで一番大切なものは、自己保存の配慮であるとすれば、国家は各部分を、全体にとって最も好都合なように動かし、配置するために、普遍的な、また強制的な力をもたなければならない。ちょうど、自然が、各々の人間に、その手足のすべてにたいする絶対的な力を与えているように、社会契約も、政治体に、その全構成員にたいする絶対的な力を与えるのである。そしてこの力こそ、一般意志によって指導される場合、すでにいったように、主権と名づけられるところのものなのである。
しかし、われわれは、この公の人格のほかに、これを構成している私人たちを考えねばならない。そして後者の生命と自由とは、本来、前者とは独立のものである。そこで、市民たちと主権者との、それぞれの権利を区別し、また市民たちが臣民として果さねばならない義務を、人間としてうくべき自然権から、十分に区別することが問題となる」49頁
「政治体の生命のもとは、主権にある。立法権は国家の心臓であり、執行権は、すべての部分に運動を与える国家の脳髄である。脳髄がマヒしてしまっても、個人はなお生きうる。バカになっても、命はつづく。しかし心臓が機能を停止するやいなや、動物は死んでしまう」126頁
そして国家と同様に、その公僕としての「政府」に対しても精神的人格を見出す。
「政府は、政府を含む大きな政治体の縮図である。それは、いくつかの属性をそなえた精神的人格であり、主権者のように能動的であり、国家のように受動的でもあって、他の同じような関係に分解することもできる」88頁
「しかしながら、政府という団体が、国家という団体から区別されるところの一つの存在、つまり現実の一つの生命をもつためには、また、政府のすべての構成員が一致して行動し、それがつくられた目的に応じうるためには、特殊な「自我」、その構成員に共通の感受性、自己保存に向おうとする一つの力、一つの固有の意志、が政府に必要だ。」88-89頁
「統治者と主権者とが、全く同一人格でしかないので(後略)」95頁
「貴族政には、二つのはっきり違った精神的人格、つまり政府と主権者とがある。」98頁
「これまで、われわれは統治者を、法の力によって結合され、国家のなかで執行権を委任された精神的にして集合的な人格として考えてきた。しかし今、われわれは、この権力が、法律にしたがって権力を行使する権利をもったただ一人の自然人、実在の人間の手に統合された場合を考えねばならぬ。これが、君主あるいは王と呼ばれるところのものである」101頁
ここで言う「人格」とは法学的には「法人格」ということになるが、この時点でルソーが現代法学的な意味での人格を考えていたかどうか定かではない。とはいえ、国家に人格を認め、さらに政府にもそれと異なる人格を認めるという論理構成は、あらゆる団体に擬制的に人格を付与しようという発想と紙一重だ。そしてそうなると、自然人と社会人を鋭く峻別したルソー理論にあっては、「人=自然人」と「人格=社会人」の峻別まであと一歩である。
「社会的権利を侵害する悪人は、すべて、その犯罪のゆえに、祖国への反逆者、裏切者となるのだ。彼は、法を犯すことによって、祖国の一員であることをやめ、さらに祖国にたいして戦争をすることにさえなる。だから、国家の保存と彼の保存とは、両立し得ないものとなる。二つのうちの一つが、ほろびなければならない。そして、罪人を殺すのは、市民としてよりも、むしろ敵としてだ。彼を裁判すること、および判決をくだすことは、彼が社会契約を破ったということ、従って、彼がもはや国家の一員ではないことの証明および宣告なのだ。ところが、彼は、少なくともそこに住んでいるということによって、自分をその国家の一員と認めていたのだから、彼は、契約を破った者として、追放によって切りはなされるか、あるいは公衆の敵として、死によって切りはなされるか、されなければならない。なぜなら、そういう敵は、道徳的人格ではなく、[たんなる]人間なのであって、そういう場合には、戦争の権利は、負けた者を殺すこととなるからだ。」55頁
「われわれは、行政官の人格のなかに、本質的に異なった三つの意志を区別することができる。第一は個人の固有意志であり、それは自己の特殊な利益のみを求める。第二は、行政官の共同意志であって、もっぱら、統治者の利益にのみかかわりをもつ。それは団体意志とも呼ぶことができるもので、政府にたいしては一般的であるが、政府をその部分とする国家にたいしては、特殊的である。第三は、人民の意志、または主権者の意志であり、それは全体として考えられた国家にたいしても、全体の部分として考えられた政府にたいしても、同様に一般的である。」90-91頁
ここでは、ルソーが「道徳的人格」と「たんなる人間」を区別していることを確認しておきたい。自然状態における人と、社会状態における人格は、論理的に異なる存在だ。
【個人的な研究のための備忘録】社会契約
本書の論理的なかなめは服従契約と社会契約の違いにあるので、該当箇所をサンプリングしておく。
「多くの人々は、この設立行為は、人民と、人民が自らにあたえた首長たちとの間の一つの契約であるとあえて主張した。すなわち、一方は支配する義務をもち、他方服従する義務をもつという条件を、両当事者の間に定める契約だという。」137頁
「国家には、ただ一つの契約しかない。それは結合の契約だ。これがただ一つあるというだけで他のすべては排除される。前者[社会契約]を破壊しないような、他のいかなる公共の契約をも、考えられないであろう。」128頁
「政府をつくる行為は、決して契約ではなく、一つの法であること。執行権をまかされた人々は、決して人民の主人ではなく、その公僕であること。」140頁
ホッブズについては、自然状態に対する理解の相違の他、キリスト教(特にカトリック教会)に対する態度に関しても批判をしている。
「すべてのキリスト教徒の著者のうちで、哲学者のホッブズのみが、この悪とその療法とを十分に認識した唯一の人であって、彼はワシの双頭を再び一つにすること、またすべてを政治的統一へつれ戻すことをあえてとなえたのであった。この統一がないかぎり、国家も政府も決して良く組織されることはないであろう。」183頁
ただしホッブズが『リヴァイアサン』の大部分をカトリック批判と俗世的権力の優位の弁償に費やしたのに対し、ルソーは最後の最後でちょいと付け足しをしているだけだ。この態度の違いが何に由来するかは、少々気になるところではある。
【個人的な研究のための備忘録】自由と平等
自由について、近代のアポリアの焦点を突くような発言がまとまって見られる。
「自由であるように強制される」35頁
「政治体の本質は、服従と自由の合致にあり、「臣民」と「主権者」という言葉は、盾の両面であって、この言葉の意味は、「市民」という一語の下に結合している」129頁
これが近代の特徴を端的に言い表すアポリアであり、近代教育の根源を規定しているテーゼである。これを表面的に解こうと思ったら、まずは自然状態における「自然的自由」と社会状態における「市民的自由」の区別(36頁)が不可欠だ。実質的に強制されるのは、「自然的自由」を奪われる代わりに「市民的自由」を与えられることだ。そしてルソーはさらにこれに「道徳的自由」(37頁)の獲得も付け加えたうえで、こう言う。
「たんなる欲望の衝動[に従うこと]はドレイ状態であり、自ら課した法律に従うことは自由の境界である」37頁
まさにこれが近代的な自由と自律であり、カントの言う立法能力であり、近代教育が「人間を人間とする」とか「人格の完成」というときに目指す境地である。自然的自由を享受する子どもから、市民的自由を享受する大人へと成長を促すことが、近代教育の使命なのだ。教育の役割は「自由(自然的に)なものを自由(市民的に)にする」ことだ。またそれは同時に「平等(自然的に)なものを平等(法的あるいは道徳的に)にする」ことでもある(41頁)。ルソーは立法の最大の目的は自由と平等だと明言している(77頁)。人は生まれながらに自由であり平等であるが、それは自然に与えられたものではなく、約束(根源的な社会契約)によって保障されたものだ。だから教育の出番がある。
【個人的な研究のための備忘録】教育
ちなみに教育について真正面から語る本ではない(その課題は『エミール』で果たされる)が、父権に絡む記述はサンプリングしておく。
「あらゆる社会の中でもっとも古く、またただ一つ自然なものは家族という社会である。ところが、子供たちが父親に結びつけられているのは、自分たちを保存するのに父を必要とする間だけである。この必要がなくなるやいなや、この自然の結びつきは解ける。子供たちは父親に服従する義務をまぬがれ、父親は子供たちの世話をする義務をまぬがれて、両者ひとしく、ふたたび独立するようになる。もし、彼らが相変わらず結合しているとしても、それはもはや自然ではなく、意志にもとづいてである。だから、家族そのものも約束によってのみ維持されている。」16頁
「人間は、理性の年齢に達するやいなや、彼のみが自己保存に適当ないろいろな手段の判定者となるから、そのことによって自分自身の主人となる。」16頁
「子供たちは、人間として、また自由なものとして、生まれる。彼らの自由は、彼らのものであって、彼ら以外の何びともそれを勝手に処分する権利はもたない。彼らが理性の年齢に達するまで、父親は彼らに代って、彼らの生存と幸福とのために、いろんな条件をきめることはできる。しかし、とりかえしのつかぬ仕方で、無条件で彼らを他人にあたえてしまうことはできない。」22頁
ロックは親子間で成立する愛情についてそうとう詳細に記述を凝らしているが、ルソーは極めてアッサリ風味である。それはロックのほうにフィルマーの父権論を論駁する必要があったという事情を加味するとしても、やはり態度の違いは明白なように思える。『エミール』においても父親の出番は限りなく少ない。
ちなみにフランス語原文ではéducationという言葉が2箇所にだけ現れるが、いずれも君主が支配者にふさわしいものとして育成されることに何の意義も認めないという否定的な文脈で使用されている。
【個人的な研究のための備忘録】人物評
マキアベッリに対しては好意的な記述が残っている。ルソーはマキアベッリを君主主義派ではなく逆説を余儀なくされた共和派と理解している。
「マキャベルリの『君主論』は共和派の宝典である。」103頁
「マキャベルリは、誠実な人、よき市民であった。」103頁
一方、キケローに対しては厳しい。まあ私としても「ですよね」という感じではあるが。
「彼自身は、ローマ人でありながら、自分の祖国よりも自分の名声を愛していたから、国家を救うためのもっとも合法的でもっとも確実な方法をさがすよりは、むしろ、この事件に関するすべての名誉を自分がにぎる方法を求めた。」174頁
■ルソー/桑原武夫・前川貞次郎訳『社会契約論』岩波文庫、1954年
 【要約】スピノザ作品の翻訳者として知られる畠中尚志が本人名義で公表した全ての文章を収めた作品集に、御令嬢とスピノザ研究者による解説が付されています。各翻訳書付設の解説では、スピノザの思想内容や執筆の背景の要点が簡潔に示される他、ボエティウス、アベラールとエロイーズ、フランダースの犬について詳説しています。エッセイでは、自身の病状や交友関係に関わる記述を通じて、困難な状況の中で真摯に研究に取り組む姿勢や不屈の人柄を垣間見ることができます。
【要約】スピノザ作品の翻訳者として知られる畠中尚志が本人名義で公表した全ての文章を収めた作品集に、御令嬢とスピノザ研究者による解説が付されています。各翻訳書付設の解説では、スピノザの思想内容や執筆の背景の要点が簡潔に示される他、ボエティウス、アベラールとエロイーズ、フランダースの犬について詳説しています。エッセイでは、自身の病状や交友関係に関わる記述を通じて、困難な状況の中で真摯に研究に取り組む姿勢や不屈の人柄を垣間見ることができます。