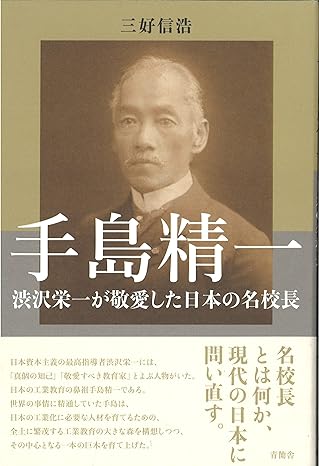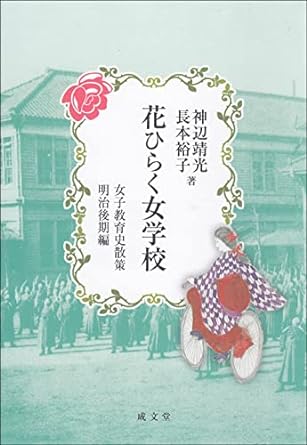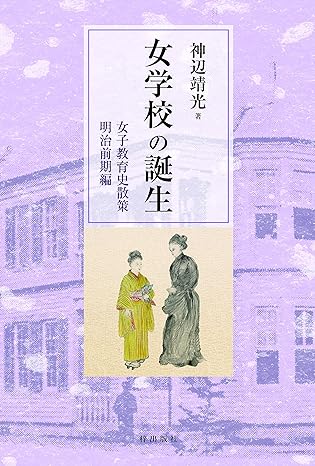【要約】教育が変われば社会が変わります。人口増加時代の成功体験を引きずった賞味期限切れの教育(暗記中心・前例主義・集団主義・学歴主義)をおしまいにし、人口減少時代に対応した新しい形の教育(主体性・好奇心・チャレンジ精神・失敗上等・個別最適化)に取り組みましょう。
【要約】教育が変われば社会が変わります。人口増加時代の成功体験を引きずった賞味期限切れの教育(暗記中心・前例主義・集団主義・学歴主義)をおしまいにし、人口減少時代に対応した新しい形の教育(主体性・好奇心・チャレンジ精神・失敗上等・個別最適化)に取り組みましょう。
【感想】工藤先生はいつも通りの工藤節で安心するわけだが、対談相手の植松氏のキャラが立っていて、時折工藤先生を圧倒しているように見えるところがすごい。面白く読んだ。ロケットを飛ばす実践の話には、感動した。実は似たような経験は私にもあるが、こういう奇跡的な瞬間に立ち会うことができる(かもしれない)のが教育という仕事の醍醐味だ。
個人的には、ときどき学生指導に対して自信を喪失するようなタイミングもなくはないのだが、そういうときに思い返したい本だ。もう一度子どもたちが本来的に持っている力を思い出すことができる。
【個人的な研究のための備忘録】人格の完成
工藤先生が他の本でも主張しているところで、だから単なる思い付きなどではなく確固とした持論であるところの教育基本法一条批判をサンプリングしておく。
まあ仰る通りで、教育基本法が誕生した1947年の時点ではある程度解説なしでも理解できたことのはず(とはいっても旧制高等学校の教養主義の文脈において)だが、おそらく1960年代の天野貞祐や高坂正顕など京都学派あたりの策動を最後に、もはや理解するための文脈が途絶えている。現在、主に道徳教育関連の研究者や実践者が「人格の完成」について分かったかのような解説をすることもあるが、法制当初の精神のかけらも残っていない、頓珍漢なタワゴトになってしまっている。工藤先生が時代に合わせて法律をアップデートさせるべきだと主張する気持ちも分からなくもない。