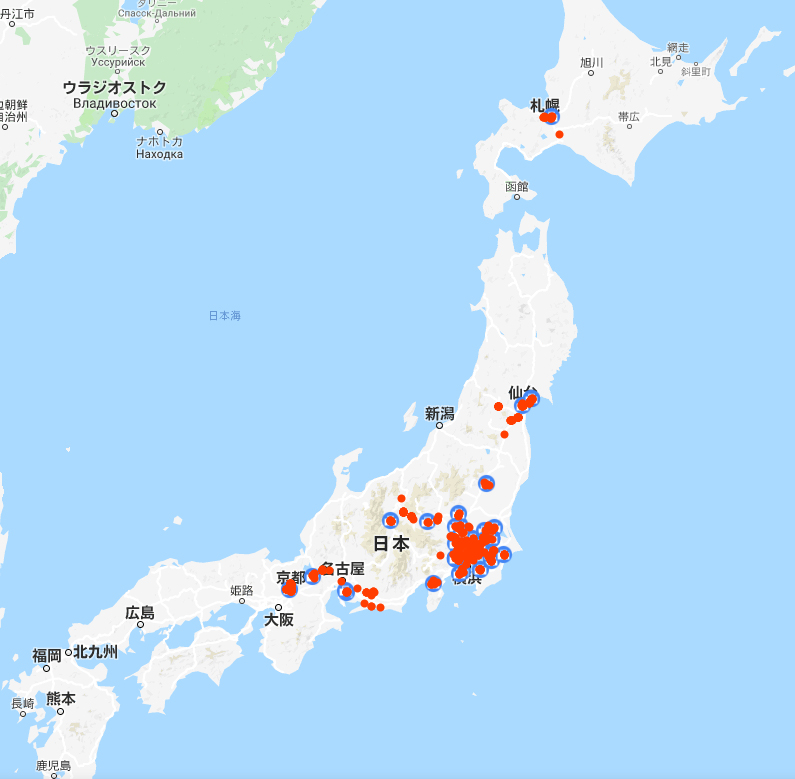日刊スポーツが「堀江氏、小学校は「刑務所通わされてるようなもん」」という記事をネット配信した(2019年5/10)。彼の価値観云々に対してではなく、このような言説を含めた状況全体について、思ったことがあるので、備忘録がてらコメントを残しておく。
まず「学校が刑務所のようなもの」という見解には、学問的なモトネタが存在する。ホリエモンのオリジナルではない。フーコー『監獄の誕生』(1975年)やイリッチ『脱学校の社会』(1971年)等で、40年以上前から学問的に示されてきた見解だ。それらの著書では、学校と刑務所(さらには病院)を、単に比喩的な意味ではなく、人間性を強制的に作り替えるものとして、本質的に同じ作用を持つ権力装置として議論している。そこには「近代」という時代の本質に対する透徹した洞察が示されている。
そもそも昔は、人々の大半は学校に行っていなかった。平安時代や鎌倉時代には、99.99%の人間は学校に行かなくても、生活上なんの問題もなかった。ヨーロッパでも事情は同じだ。大半の人間は学校なんかに行かなくても、普通に暮らすことができた。
しかし現在は逆に99.99%の人間が学校に行く。学校に行かなくては普通の生活ができないと、多くの人が思っている。どうして昔は学校に行かなくても平気だったのに、現在は行く必要があるのか? 本当に学校に行かなくてはいけないのか? この疑問を突き詰めていくと、学校や教育のみならず、「近代」に対する洞察へと至ることとなる。
結論だけ言えば、「資本主義で歯車となる人間」を供給するためには、人々を学校にむりやり収容し、生活習慣を強制的に組み替え、工場労働に適合する習慣形成を行う必要があるのだ。たとえば工場が期待する優秀な労働者とは、無断欠勤しない、遅刻しない、上司の命令はどんなに理不尽でも聞く、密告するなどの習慣を身につけた人間だ。
そして人間は、学校に通わなかったら、こういう習慣を身につけない。家庭学習で頭が良くなるだけでは、ダメなのだ。あらゆる人間をむりやり学校に収容し、長年にわたって工場労働に適合するためのトレーニングを積ませる必要があるわけだ。
資本主義を発展させるためには、こういった「歯車」が大量に必要であった。そしてその期待に、学校はしっかり応えた。日本が資本主義国へと成長できたのは、学校教育制度が機能したおかげと言える。これが「近代」という時代の特徴だ。
しかし、いったん資本主義が成長しきって成熟段階に入ると、実はこういった「歯車」が必要なくなってくる。単純作業は機械やAIがやってくれるし、会社が必要とするのはイノベーションを起こせるような創造的な人間だ。どちらにしろ「歯車」の需要はなくなる。このあたりの事情は、宮台真司が90年代から「成熟した近代」という言葉で主張している。たしか上野千鶴子も同じような主張をしていた。というか、80年代後半から、だいたいみんなが「近代は終わった」という議論をしていた。
こうして「近代」が終わると、「歯車」を世の中に大量供給していた学校の必要度も下がってくる。人々から学校へ通うモチベーションが失われていく。学校に行く必要を感じなくなる人々が増えてくる。不登校が増える。佐藤学が「学びからの逃走」と呼んだ事態が広がっていく。
ホリエモンが記事内で主張していることは、90年代から既に議論し尽くされた話を、「分かりやすい極論」として示したもののように読める。
さて、議論として必要なのは、「学校は必要だ」とか「必要ない」という主観的な意見ではない。「近代という時代がどういう特徴を持った時代で、どうして学校は近代では有効に機能して、そして21世紀ではそのままで機能するのかしないのか?」という問いの立て方が重要なのだ。
私個人としては「学校は機能しなくなる」とまでは言いたくないが、「このままの学校では、遅かれ早かれ機能しなくなる」という危機感は共有すべきだと思っている。ホリエモンの発言は教育界に1ミリたりとも影響を与えないわけだが、しかしそのイロニーに込められているものから学校の危機を感じておくのは、無駄ではないと思う。
個人的には、ホリエモンとは誕生日が20日ほどしか違わない同年代で、同じ時期に駒場や本郷にいたことから、動向が気になる人物の一人ではあるのだった。