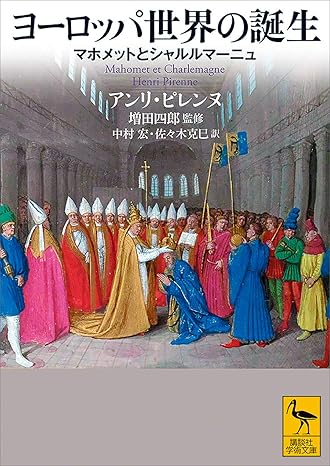【収録論文】
【収録論文】
(1)ヴェルジェーリオ(1370-1444)「学芸について」
(2)ブルーニ(1370-1444)「諸学問ならびに文学について」
(3)アルベルティ(1404-72)「家庭教育論」
(4)ピッコローミニ(1405-64)「子どもの教育について」
【要約】子どもたちが持つ本来の特性を見極めて、早期に善い習慣を身につけさせ、悪習を取り除き、自由諸学芸を学ばせましょう。歴史や修辞学、詩の古典などを幅広く学ばせ、特に雄弁術の修得を通じて徳を身につけさせましょう。教育は早く始めるに越したことはありません。体罰はだめです。
【感想】15世紀、イタリア・ルネサンスの教育論アンソロジーなわけだが、この周辺の事情は学部生向け教育学の教科書ではそうとう手薄い印象がある。私の基礎教養が欠けているのも学部の概論でしっかり学んでいないせいだ(ということにしておこう)。
一般論としては、ペトラルカ以来のイタリア・ルネサンスによってギリシア・ローマの古典が暗黒の中世から甦り、人文主義(ヒューマニズム)が勃興・充実・発展して、現代のリベラル・アーツ(教養主義)にまで繋がることになっている。確かに本書に収められた諸論考はギリシア・ローマの古典からの引用に満ちている。特にキケロ、プルタルコス、クインティリアヌスからの引用は飽き飽きとするくらい大量だ。というか、教育に関する考え方そのものはクインティリアヌスからほとんど進歩していないようにすら見える。古代とルネサンスの距離は、論旨だけに注目すれば、極めて近い。つまりキリスト教による影響は目につかない。
しかし一方、ルネサンス期教育論と近代的教育論との距離は、極めて遠いように思う。ルネサンスの教育論からは、ちっとも近代的な臭いがしない。体罰禁止という主張そのものには近代的な臭いを嗅ぎ取ることもできようが、禁止の根拠はまったく近代的ではない。ルネサンス期教育論と近代的教育論が似ていないと思うおそらく最も大きな原因は「雄弁術」の位置づけだろう。ルネサンス期ヒューマニストたちが雄弁術を最大限に称揚するのは、彼らの教育論の土台がクインティリアヌスにあるのだからまったく不思議ではないというか、当たり前ではある。しかし一方彼らが拝み奉る雄弁術なるものは、近代的教育論ではほぼ完全に抹殺されている。ルネサンス期人文主義を引き継いだとされる現代リベラル・アーツでも、雄弁術そのもののトレーニングなどしない。
近代的な教育においては、任意のテーマについて雄弁に語るより、真実を見極めること(およびその手続き)の方が決定的に重要だ。もちろんそれはガリレオ、コペルニクス、ニュートン等による自然科学の仕事がベーコン、デカルト、カント等によって帰納的・論理的・理性的・科学的な思考法に定式化されて以降のことだ。現代のリベラル・アーツも、雄弁的な素養を身につけることよりも、論理的・理性的・科学的・批判的な思考を育むことを目指している。そういう近代的な観点からすると、自然科学革命以前のイタリア・ルネサンス期の教育論がやたらめったら雄弁術の重要性を前面に打ち出してくるのは、時代背景を踏まえれば理屈では分かるとしても、少なくともその雄弁術への情熱はどう頑張っても共有できない。近現代においては、雄弁術の教育的意義は地に落ちている(まあ福沢諭吉が「演説」の重要性を説いていたことは思い出しておいても損ではないか)。
そして個人的な研究上の関心に焦点を絞ると、教育基本法第一条でいう「人格の完成」という旧制高等学校的観念が雄弁術とどういう関係にあるかが問題となる。言い換えれば、雄弁術の伝統がキケロ的古代からイタリア・ルネサンスを経て近代以降にどう引き継がれているか。あるいは仮説として、たとえば近代的合理主義の浄化作用によって「人格の完成」という古代的・ルネサンス的観念から雄弁術の伝統が漂白され、背景と文脈を失った単なる観念あるいは理念としてより純化した、と見なすべきか。ともかく、雄弁術がリアルに政治的・法的・文化的意味を担っていた時代(たとえばキケロ的古代)であれば具体的にイメージできただろう「人格の完成」というものは、近代合理主義を経て高度に抽象化してしまった結果、現代では内容を失ってただのお題目にしか聞こえない状況になっている。かつて「教養」と呼ばれていた何かが説得力を失っているのもそのせいかもしれない。
ひるがえって。本書収録の諸論文は、科学革命以前(というか前夜)の、雄弁術がまだ大きな権威と説得力を維持していた段階における、具体的な「人格の完成」を当然の前提とするような教育論たちだ。現代的な「人格の完成」概念に至る道筋のヒントが何かないかと思って本書を手に取ったわけだが、結果として欲しかったもの(自分のストーリーに都合の良い言質)は手に入らなかった。というか、ますます混迷の度を深め、軽い眩暈に襲われているのであった。
【個人的な研究のための備忘録】個性
欲しかったものの一つは「個性」という概念(の萌芽)だったが、「かけがえのない個人」というものを指し示すような言葉は皆無だった。モンテーニュの段階(16世紀後半のフランス)では明瞭に見いだせる「かけがえのない私」という観念は、15世紀イタリア・ルネサンスには見いだせない。むしろ14世紀ペトラルカのほうが近代的自我を彷彿とさせるくらいだ。まあ、「ルネサンス期にはかけがえのない私という個性観念は一般論としては成熟しなかった」と、しばらくはみなしておいていいのだろう。
一方、「様々な特性を持った個体がある」という個性観念は極めて重要な論点として前面に打ち出されている。それは古代のクインティリアヌスにも明瞭に見られる考え方で、その論理をそのままそっくり引き継いだルネサンス期教育論が同じような見解を示しているのは当然と言えば当然ではある。まあ、まずは「様々な特性」という意味での個性観念がやたらめったら表明されていることは事実として押さえておく。(とはいえそれは西洋に特徴的な現象でもなく、東洋でも伊藤仁斎などが「性」概念を論究する際に盛んに主張していたことも忘れてはならない)。だから問題は、ここからどうやって近代的な「かけがえのない私」という個性観念に繋がるか、あるいは繋がらないかだ。具体的にはモンテーニュとの関係がポイントになるか。
「各人は生まれたときからその固有の才能をたいせつにしなければなりません。(中略)生来、生まれついているものがなんであるかを熱心に窮めることがすべての人にもっとも重要なこととなります。」(V.20頁)
「ある者にとっては、親たちの期待そのもの、あるいは幼児期からの習慣が障害となります。子どものころから慣れ親しんだことはおとなになってもたやすくおこないます。そして、そのゆえにこそ生み育ててくれた親たちの技術や職業を子どもはみずから選ぶのです。われわれの教育という仕事のもう一つの障害は、生まれた土地の流儀です。われわれは、そこで生活する人びとが承認し、おこなうことを純金の財宝でもあるかのように尊重するのです。そこで、人びとはその固有の人生の方向を選択することが、非常にむずかしくなっています。」(V.37-38頁)
「ところで、才能が多様な性質をもっていることは事実です。ある者は自分の思想を論証する論点と証明を、よういになにごとのなかにでも見いだします。ある者は、それとは反対に、そのようなことには時間をかけなければなりませんが、しかし判断においてはより深くかつすぐれております。(中略)また、ある者は才能にはめぐまれていながら、ことばがさわやかでないということもあります。(中略)ついで、抜群の記憶力をもった人びとがおります。」(V.53頁)
「思弁的で実務的な二重の才能にめぐまれている者は、いずれの方向に自分がより適しているかを各自が判断することによって、のぞましいとおもわれる学問研究に専念すべきです。ついで、才能のおとっている者、つまり法律用語でいう<土地につながれた者>は、普通にはなにごとにおいてもうまくいかないようにおもわれておりますが、しかしなにか一つのことで成功することを示しております。そして場合によってはかなりの力を発揮するものです。したがって当然のことではありますが、このような人びとは、彼らにもっともふさわしいある一つの教育に専念すべきです。」(V.54頁)
「すべての学習者に画一的規則をもうけることはのぞましくないし、また各自が自分の能力の状態ならびにその程度を判断すべきであることをわたしはつけくわえたいとおもいます。」(V.57頁)
「父親は子どもたちに適したことをやらせて欲しいものです。「お前の性質や才能がお前をひき寄せるところに、熱心に従い、はげみなさい」と、キケロに答えたアポロンの神託をお聞きなさい」(A.101頁)
「彼等によって、息子たちがどんな修行や徳に向いているかということを知ることは、それほど困難なことではないでしょう。」(A.102頁)
「日々、子どもたちにどんな習慣が生じるか、どんな欲望が持続するか、彼らはどんなことにしばしば関心を示しているか、何に一番熱心なのか、そして、どんな悪い欲望にとらわれやすいかを、父親は注意深く観察して欲しいと思います。そうすれば、子どもたちの、多くの明瞭な特徴をひき出し、彼らを完全に認識することができるでしょう。」(A.103頁)
「子どもが生来の傾向を何がしか示しはじめる最初の日から、彼らがどんな性向を持っているかということにあなたは気がつくでしょう。」(A.104頁)
「父親は多くの場合、子どもがそれぞれ何にむいているか、かなりよく気がつくものです。」(A.105頁)
「私たちの子どもたちの漠然とした隠れた傾向に注意を払って認めた後で、天性にしたがって彼らがひかれていた傾向に反した、新しい他の道へ彼らを矯正し、導くことが、私たちにとって、非常に困難でほとんど不可能なことではないと思うのですか?」(A.122頁)
「多血質の人は憂うつ質のひとよりももちろん恋をしやすく、胆汁質の人は怒りっぽいということでもわかるように、本来、多かれ少なかれ人間の欲望には何らかの刺激が自然に付与されているということを、おそらく私は告白しなければならないでしょう。」(A.124頁)
「天性は教育がなければ盲目であるように、教育は天性がなければ不具であります。両者とも訓練をしなければあまり役に立ちません。」(P.139頁)
【個人的な研究のための備忘録】習慣
というわけで具体的な教育方法としては、特に幼少期は子どもの「個性」を見極めたうえで、悪い習慣を抑えて良い習慣を身につけさせることがポイントとなる。
このあたりの理屈や筆運びはただちにジョン・ロックの教育論を想起させるところだ。自然科学革命を経た近代合理主義であっても、「習慣」という観念や教育上の意義について変更された気配は感じない。このあたりに「人格の完成」観念の連続性を考えるヒントがあったりするか。
【個人的な研究のための備忘録】体罰
ちなみに体罰は徹底的に非難される。このルネサンスの伝統はエラスムスにまで引き継がれる。
「殴打からは憎悪が生まれ、おとなになっても残ります。学ぶ者にとっては教師に対する憎しみ以上に有害なものはありません。」(P.142頁)
ただし、古代のクインティリアヌスが体罰を徹底的に非難しており、それを無批判に引き継いだルネサンス期教育論が体罰を否定するのも当然というところではある。ルネサンス期の具体的な状況から帰納的に体罰否定の論理が編み出されているわけではない印象だ。
【個人的な研究のための備忘録】自由諸学芸
教育内容としては、もちろん自由諸学芸(人文主義)が全面的に推奨される。
「卑俗な諸技術がその目的としてかせぎを快楽とを目ざすように、徳と栄光とが自由諸学芸の目的となります。」(V.34頁)
解説では以下のようになっている。
この定義については、セネカ、『書簡集』(Epistola 88, 2)参照。かれによれば「なぜ自由諸学芸とよばれるかといえば、それらが自由な人間にふさわしいものだからだ」。(Quare liberalia studia dicta sint, Vides: Quia honine libero digna sunt.)とされている。
ヒューマニストたちが、自由諸学芸の教育的価値を重視していたことが注目されなければならない。それは、自由なる人間に装飾的なものとしてにつかわしいから、自由で人間的な学芸であるのではない。それが人間を人間たらしめ(古典的人間教養研究とよばれるのは人間を完成するからだ。Humanitatis studia nuncupantur quod hominem periciant.)、人間を形成し、光へみちびく古典文学lettereだからである。奴隷の状態から自由へといざなうのは古典文学研究によってである(人間を自由にするから、それゆえに自由なのである。idcirco est liberalis, quod liberos homines facit.)。」
しかし率直に言って、現代的な感覚から言えば、「教養」なるものは単に「装飾的なもの」に過ぎず、それによって「人間を人間たらしめる」ようなものではない。おそらく、我々現代人には既に失われた何らかの前提を設定しなければ、自由諸学芸は「人間を完成する」ものにはならない。しかしその前提は、キケロを読んでもクインティリアヌスを読んでも、もちろんルネサンス期教育論にも見出すことはできない。その前提とは、たとえば奴隷の存在のようなものだ。ルネサンス期教育論は、学問を日常生活で役に立たせることを自由人に相応しくないことだと見なしている。日常生活に役に立たないことこそ人間を人間(自由人)たらしめる。そしてその具体的な内容は、政治や裁判の場で発揮される「雄弁」だ。政治や裁判の場で雄弁を発揮することだけが自由人(完成した人間)に相応しいと言われても、現代人にはもはや何のことやらサッパリだ。だから、現代においてリベラル・アーツなるものに権威と説得力を持たせようと思ったら、古代とルネサンスの遺産に頼るだけではうまくいかない。そんなわけで、古代とルネサンスで言われている「人間」とは、「奴隷」というものの存在を前提とすることで初めて理解できる概念だということを忘れてはいけないだろう。
【個人的な研究のための備忘録】大人と子どもの区別
大人の嗜みとしては許されるが子どもからは遠ざけておくべきもの、という観念をいくつか見ることができた。
「子どもの時期には、特にブドー酒について子どもが節制するようにとわたくしは申しあげたいとおもいます。」(V.29頁)
「酒飲の傾向のある子どもほど不愉快なものはありません。」(P.147頁)
淫猥な演劇やアルコールは子どもに相応しくないと見なされていて、「教育的配慮」の存在を確認できる。アリエスによればアンシャン・レジーム期にはなかった心性のはずだ。というわけで、アリエスが間違っていると見なすか、フランスがイタリアよりも2世紀ばかり田舎だと考えるか、というところだ。
【個人的な研究のための備忘録】歴史的背景
解説の記述について考えてみたい。
「都市の独自の発展に由来する地方主義regionalismの伝統と意識は今日でも顕著にみられる。イタリア人としての民族的自覚よりもさきにナポリ人でありフィレンツェ人であるとする郷土意識は、都市的伝統にもとづくものだ。これは諸都市の独自性を前提とする意識であり、また都市内部においてはそれをささえ構成する市民たちの個性が尊重された。したがって文化的諸成果も市民による個性的能力のあかしとなるものであった。」(201-202頁)
「いじょうにみたようにルネサンス期イタリア都市はそこに展開される諸現実をその所与性、一面性においてうけいれるのでなく、むしろ現実との格闘をとおしてそれをつくりかえ、選択し、展望をきりひらくように、市民たちにせまったのである。そのような環境のもとで、市民たちはその運命にかかわる自己決定や独立独歩の精神を容赦なくせまられることとなり、それを主体的につちかわざるをえなかった。そしてその反映と興亡がそこで生活する市民たちの努力と資質にかかわる都市において、市民たちの多様な個性と諸能力が社会的に重視され、またその発達を可能とするような土壌の準備がなされたことはけだしとうぜんというべきであろう。」(202頁)
「ルネッサンス期も後半にいたるとペダントリーと古代作家の模倣の現象があらわれる。しかし、これはヒューマニズムの思想からすればあくまでも派生的現象であって、けっしてその本質ではない。その理想に個性的で創造的な、しかも実践的な人間の形成がかかげられるいじょう、模倣や衒学は自己撞着であり、その否定こそヒューマニズムのもとめてきたものだったからである。つまり、キケロを読むのは外面的にキケロに似ることのためではなく、自分自身のなかにキケロいじょうの個性と可能性とを発見することをめざしたからであった。」(205頁)
都市国家形成を重要な契機と見る視点は教科書的な記述としては問題がないのだろうが、気になるのは古代との直接的な連続性である。たとえばピレンヌテーゼによれば西ヨーロッパがローマ文化を喪失したのは7世紀中盤のイスラムによる地中海封鎖によるが、イタリア半島だけはビザンツ帝国との繋がりを保ちながらローマ文化を一定程度保存できている。また12世紀シチリア王国がイスラムやビザンツとの交流の中で文化的に栄えていたこともよく知られている。だとしたら、イタリア・ルネサンスに見られる人文主義的伝統は、解説が言うような都市国家形成と市民階級の勃興を待つまでもなく、直接的にローマ帝国からの連続性を保っていたと考えることも可能だ。
あるいは、人文主義が中世のスコラ学とも近代のサイエンスとも異なるユニークな教育論を持っていたことにも留意したほうがいいのだろう。たとえば日本で言う本居宣長の国学のようなものだと理解したらどうなるだろうか。本居宣長は市井の活動の中から中世の漢学とも近代の洋学とも異なる別のストーリを打ち立てた。一定の平和と安定と経済的余裕という前提の下、郷土的意識という土台に立ち、学問に対する熱意と情熱が既存の制度の外にユニークな学統を打ち立てた。そういう観点から言ってしまうと、人文主義と翻訳調で呼ぶより、イタリアで「ローマ学」が流行したと考える方が個人的には落ち着いたりする。
「基本テーマはあくまで人間形成の問題であり、とくに重要なのは教育における人間の多面的把握の必要の強調とその視点である。教育における人間の本来的自然の重要性が強調され、そこから出発して具体的な個々の子どもの個性と人間としての可能性との調和的均衡的な発達の人間形成にしめる役割がくりかえしのべられている。」(205頁)
私の読解では、ルネサンス期教育論から「歴史における主人公の意識」を読み取ることはできない。確かに「具体的な個々の子供の個性」に対する関心は極めて高いのであるが、それが「教育における人間の多面的把握」かと言われると首を傾げざるを得ない。そう見えてしまうのは、私の勉強不足が原因なのかどうか。