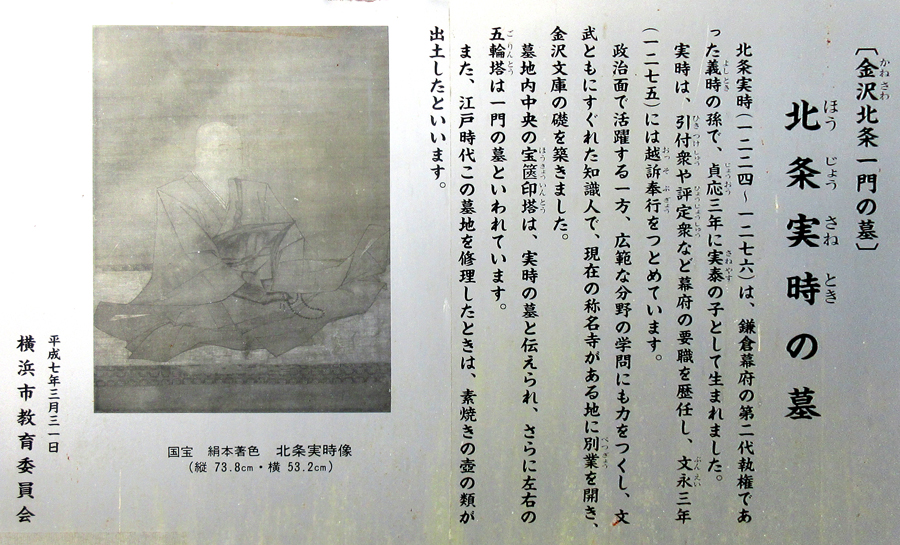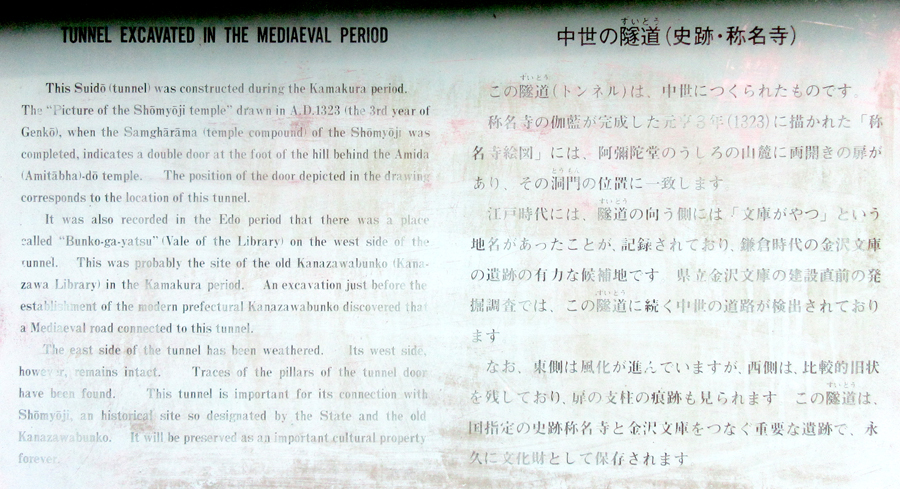金沢文庫に行ってきました。
「金沢文庫」は、創設者とされる北条実時の名前を伴って、しばしば教員採用試験に出題されます。そして雑な参考書では、金沢文庫が「中世の学校」とされているケースを見かけます。いえいえ、金沢文庫は学校(少なくとも私達が知っている学校)ではありませんでした。
ちなみに、もともとあった金沢文庫の建物自体は既に滅びてなくなっています。現在は県立の博物館となっており、常設展の他、定期的に特別展が開催されています。そして金沢文庫に関して言えば、建築物そのものはあまり大きな意味がないかもしれません。というのは、金沢文庫の本質は、建物ではなく、「書物」そのものだからです。「金庫」の守りたいものが箱などではなく金そのものであるように、「文庫」の守りたいものは建築物などではなく「文」そのものです。仮に建物が滅びてなくなったとしても、「文」を運んでくれる書物が残って現在に伝えられていることが極めて尊いのです。
その書物の大部分が遺されていたのは、金沢文庫からごくごく小さな山を隔てて東隣にある称名寺というお寺です。
花頭窓のある立派な山門を抜けて称名寺の境内に入り、太鼓橋を登って阿字池を突っ切って、金堂に向かいます。この阿字池になんとなく異国情緒を感じるのは、我々が室町以降の枯山水庭園のほうに慣れ親しんでいるからかもしれません。
称名寺の境内を囲むように山があります。というか正確に言えば、三方を山に囲まれた谷地を選んで称名寺が建っている、としたほうがいいでしょう。もともとは北条実時の館だったので、戦争時の防御に適した地形を選んでいるということですね。
称名寺の北の山の中に、金沢文庫を創設したとされる北条実時の墓があります。ハカマイラーとしてはぜひ行かなければなりません。この森は軽いハイキングコースとなっていて、地元の人が散歩を楽しんでおりました。
写真の真ん中が北条実時の五輪塔です。
お墓の脇に案内パネルがあります。この説明では、賢明にも慎重に「金沢文庫の礎を築きました」と書いてあります。軽率に「創設」とは言っていないところに注目しておきましょう。
お墓からさらに西に進むと、山の天辺から八景島を臨む絶景が楽しめます。天気も良かったので、海を眼前に臨んでとても良い気分です。手軽なハイキングコースとしては極めて優秀だと思いました。
さて山を一周して称名寺の境内に降りてくると、西の端に銅像が立っています。僧形の北条実時です。本来は武士ではありますが、お寺の開基ですからね。
そして銅像の西に、トンネルがあります。このトンネルを抜けたところが、県立金沢文庫の入口です。少し不思議な景色です。
トンネル入口に設置された案内パネルには、「金沢文庫」の由来が説明されています。ここに明確に「和漢の貴重書を納めた書庫」と書いてあります。「学校」とは一言も書いてありません。ここは誰かを教育したり指導するための場所ではありませんでした。「貴重書」の収集と保管そのものが目的であり、そしてそれを目当てに知識人が集まってくるような、研究所とかサロンとでも呼ぶような場所でした。
平安時代までは、このような「和漢の貴重書」を集めていたのは貴族や僧侶でした。金沢文庫の最大のポイントは、戦闘集団だったはずの武士が「和漢の貴重書」を集め始めたという明確な痕跡が残っているところです。
鎌倉に武家による権力組織が誕生したのはいいとして、現実的に政治を行なうためには立法・行政・司法に関する広範囲の知識と教養が必要になってきます。そして関東武士の土地財政的な実態に合った権力運用のためには、貴族式の律令制では役に立たず、新たなルールが必要とされます。具体的なルールは「御成敗式目」という形で登場することになるわけですが、これらの整備や運用に際しても知識と教養が必要になります。金沢文庫とは、武士が実際に政治を行なうときに必要とされた知識と教養を蓄え、運用し、表現するための場所だったわけです。
トンネルの北側には、「中世の隧道」が遺されています。現在は金網で封鎖されていて通ることはできません。
案内パネルによれば、称名寺と金沢文庫を繋ぐ通路として実際に使用されていた可能性が高いようです。確かにいちいち山を越えるのは面倒そうです。北条実時も、館から文庫へ赴く際は、この水道を利用していたのでしょう。
北条実時が収集を始め、称名寺に遺された「文庫」は、現在も貴重な資料として各種研究に利用されています。ありがたいことです。
(2020年12/26訪問)