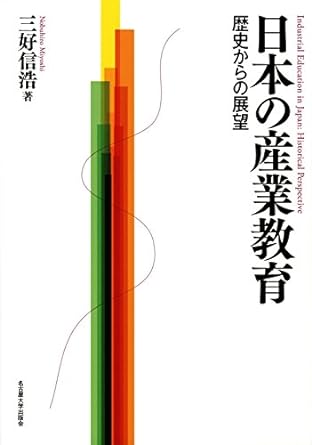【要約】学校で学ぶことはデタラメで何の意味もないことを悟り、自分自身の内部と世界そのものだけに真実を求めて旅に出ました。そしたら旅先でもみんな言っていることがそれぞれ違うので、人が言っていることは何も信じてはいけないことを確信しました。
【要約】学校で学ぶことはデタラメで何の意味もないことを悟り、自分自身の内部と世界そのものだけに真実を求めて旅に出ました。そしたら旅先でもみんな言っていることがそれぞれ違うので、人が言っていることは何も信じてはいけないことを確信しました。
これまでに教師からデタラメを教え続けられたことが分かった以上、曖昧でいい加減な知識は全部捨て去り、焦らず時間をかけて、確実な思考を進めるための原理を考えた結果、4つの規則に落ち着きました。
(1)疑う余地のない明晰で判明な真実以外は判断の材料としない。
(2)解決すべき問題はできるだけ細かい部分に分割する。
(3)もっとも単純で認識しやすいものから階段を上るようにして順番に理解し、最終的に複雑なものの認識に至る。
(4)あらゆる要素を完全に枚挙して見落としがなかったと確信する。
この思考法を数学で試すとたちまち難問を解きまくることができるようになり、これでいけるという自信を持ったので、最も重要な哲学で同じことができるかチャレンジしてみることにしましたが、焦らず時間をかけて丁寧に考えようと思ったので、決定的な答えを見出す前に暫定的な行動方針を立てました。
(1)わたしの国の法律と慣習、そして最も良識ある穏健な人の意見に従う。
(2)一度決断を下したら、多少怪しくても首尾一貫してそれに従う。
(3)他人を変えようと無駄なことはせず、自分を変える。
この方針でしばらく大丈夫そうだったので、予定通り少しでも疑わしいものはどんどん捨て去りました。しかしあらゆるものを疑い続けるうちに、考えている自分自身の存在だけは疑えないことは、何があっても揺るぎない確実な真理であることを見つけました。「われ惟う故にわれ在り」こそ探し求めていた哲学の第一原理ということでファイナルアンサーです。そうなるとたちまち(2)仮に身体(物体)がなくても考えるわたし(精神)は存在する。(3)わたしたちが明晰かつ判明に捉えることはすべて真実である。(4)完全な神が存在する。(5)われわれの理性には何かしら真理の基礎がある、という真理が演繹されます。
この原則に立って考え始めると、これまで哲学上の難問と思われてきたことにも簡単に答えを出すことができます。たとえば地球を含むこの世界全体の成り立ちやあらゆる現象、さらに人間の体の仕組みは、古代哲学やスコラ学が駆使する概念なんかなくても、すべてメカニカルに説明し尽くせます。ただし人間の魂は物質ではないので、別に考えなければいけません。
ここまでの考えを論文にまとめて出版する準備を進めていましたが、宗教裁判でガリレオが有罪になったのを見て、やめました。しかしやはり自分が到達した真実へ至る方法は人々を幸福に導くものです。なぜなら自然の原理を解明し、それを応用することで、われわれは自然の主人となり所有者となることができるからです。わたしが到達した地点はごくごく初歩的なところにすぎませんが、この方法を貫徹すれば、人間はますます発展していきます。今後の探究では実験が重要になります。序説はこれで終わりますので、次の章から具体的な成果をご覧ください。(翻訳はここでおしまい)
【感想】まあ私が改めて評価するまでもないことだが、新しい時代の幕開けを告げる画期的な論考だ。いよいよ近代に突入した。
まず重要な事実は、中世的スコラ学を徹底的に排除しているのに加えて、ルネサンス的人文主義も完全に排除している点である。デカルト的近代は人文主義(ヒューマニズム)の伝統から完全に切り離されている。ルネサンス的人文主義の研究者たちはもちろん人文主義こそが近代の幕開けだと主張するわけだが、虚心坦懐に本書を読めば、そんなことはない。むしろ人文主義は近代化を妨げるような世迷言に過ぎない。古代哲学など、現実を理解するのに何の役にも立たない。デカルトに直接連なるのは、コペルニクス、ブルーノ、ベーコン、ガリレオなど、自然科学の発展に果敢に尽くした人々だ。
とはいえ判断が難しいのは、デカルトの自己主張にも関わらず、既存の権威を相対化するという批判的な姿勢や態度を育む上で人文主義が何の貢献もしていないと即断するわけにはいかない、というところだ。15世紀後半から17世紀前半に至る100年強の時間の中で、人文主義の活動(そして宗教改革)によって少しずつ既存の権威が失われていく。この既存の権威への批判と相対化という地ならしがなければ、デカルトの画期的な論考も芽生えることがなかったかもしれない。というか、たぶんそうだろう。となると、人文主義とデカルトの間に直接的な繋がりがなくとも、時代背景や土台づくりという点で人文主義の意義を認めることはできる。
また、実は「我惟う故に我在り」というアイデアそのものが既にアウグスティヌス『神の国』に見られるという事実には配慮しておいて損はしないだろう。デカルト自身がアウグスティヌスに言及することはもちろんないのだが、あれほどデカルトがバカにしているイエズス会の学校でアウグスティヌスについて聞いていないなんてことがあるわけないので、意識的にパクったか無意識的に参照したかはともかく、アイデアそのものがデカルトの完全オリジナルでないことは間違いないと思う。もちろんそれを第一哲学の原理に据えたのはデカルトの創見だが、学校で学んだことをそんなにコケにすることもないということでもある。
そんなわけで、ルネサンスや人文主義の歴史的意義については、デカルトの方針に従って、少ない情報のみで即断することなく、時間をかけて丁寧に見ていかなければならない。
次に個人的な関心から問題になるのは、「かけがえのない人格」という近代的自我の観念形成に対してデカルトがどれほどの貢献をしているか、というところだ。
まず「我惟う故に我在り」という例のテーゼそのものが「かけがえのない我」という観念を浮上させるのは間違いない。しかも哲学の第一原理ということで、荘子など中国哲学的な独我論とも異なり、あるいは仏教で乗り越える対象となる「欲望の主体としての我」とも異なり、間主観的な議論に発展させることが可能な、つまり民主主義の土台となる健全な個人主義の原理として意味を持つ。デカルトそのものには「かけがえのない人格」という表現を明確に見ることはできないが、ここに個人主義の哲学的土台を見ることは許されるだろう。
そして本書を通読して改めて思ったのは、デカルトは自身の主張を論理形式のみにおいて成立させようとしているのではなく、自分の独自な生育史を踏まえて説得力を持たせようとしている、ということだ。本書の書き方そのものが「過剰な自分語り」になっていて、たとえば扱っている内容や主張がまったく違うように見えるモンテーニュ『エセー』における「私」と立ち位置が実はよく似ている。こういう「自分語り」は古くはペトラルカやダンテあたりの詩的表現には見られるが、哲学の領域において、プラトンのような対話形式でもなく、アリストテレスのような客観的論文調でもなく、過剰に自分語りをしながら表現してみせたのは実はけっこうすごいことではないか。そもそもデカルトは真理の「伝え方」にそうとう意図的で、客観的な真理として他人に押し付けようとはしておらず、あくまでも「自分自身がたどりついた確信」について述べるという表現形式を徹底している。つまり、自分がたどりついた真理を自分自身の表現形式に忠実に適用している。デカルトが画期的なのは、内容だけでなく表現形式と伝達手法においても「我惟う」を貫いたところだ。ここに近代的自我(かけがえのない人格)の始まりを見たくなるわけだ。
ちなみに評判が悪い「神の存在証明」は、確かに無理筋だ。「完全性」という中世スコラ的概念を持ち込んだ瞬間に話がおかしくなった。逆に、いかに「完全性」という概念が中世を支配していたかを照射する表現としては注目できる。そして、実はここにこそ「人格の完成」という概念の根っこがあるのかもしれないので、侮れない。ちなみに「神」を必要としない「我惟う」哲学第一原理の確立は、フッサールを待つことになる。
【個人的な研究のための備忘録】
スコラ学や人文主義に対する批判については直接的な表現を確認できる。
「わたしは雄弁術をたいへん尊重していたし、詩を愛好していた。しかしどちらも、勉学の成果であるより天賦の才だと思っていた。」14頁
「以上の理由で、わたしは教師たちへの従属から解放されるとすぐに、文字による学問(人文学)をまったく放棄してしまった。そしてこれからは、わたし自身のうちに、あるいは世界という大きな書物のうちに見つかるかもしれない学問だけを探求しようと決心し、青春の残りをつかって次のことをした。」17頁
「われわれが人生にきわめて有用な知識に到達することが可能であり、学校で教えているあの思弁哲学の代わりに、実践的な哲学を見いだすことができ、この実践的な哲学によって、火、水、空気、星、天空その他われわれをとりまくすべての物体の力や作用を、職人のさまざまな技能を知るようにはっきりと知って、同じようにしてそれらの物体をそれぞれの適切な用途にもちいることができ、こうしてわれわれをいわば自然の主人にして所有者たらしめることである。」82頁
「これまでの医学で知られているすべてのことは、今後に知るべく残されているものに比べたら、ほとんど無に等しい」83頁
「しかも実験については、知識が進めば進むほど、それが必要になることをわたしは認めていた。」86頁
あとはスコラ学や人文主義を批判する文脈で「自然の主人にして所有者たらしめる」という近代の人間中心主義が露骨に表明されていることについては、やはり見逃すわけにはいかない。
大人と子どもの比較が表現されていたのでサンプリングしておきたい。またここでさりげなく「教師」に対する批判が見られることも確認しておく(ただしヴィーヴェス等に見られるような倫理的人格に対する批判ではないのだろう)。
モンテーニュと比較されることに対する牽制だと理解していい表現か。ともかく16世紀前半の段階で一般的に「懐疑論」について理解されていただろうことは確認しておく。
確認しておけば、デカルトは「方法的」に懐疑しているだけで、結論として懐疑を容認しているわけではない。デカルトの「我惟う」は独我論に陥らず、間主観的な議論が成立する土台となる健全な個人主義に結びつく。そういう意味で、フッサール現象学が方法論としてエポケー(判断停止)するのは、確かにまったくデカルト的である。
デカルト自身が「スコラ学」から言葉を借りてきていると正直に表明している通り、この神の存在証明に近代的な表現は見当たらない。荒唐無稽だ。
ただし、「完全性」という概念がヨーロッパ思想史で極めて重要な役割を果たしてきたことだけは明瞭に理解できる。そして近代の「人格の完成」という概念は、私の感想では、おそらくこの「完全性」の概念を背景として成立している。デカルトのこの荒唐無稽でデタラメな神の存在証明には、しかし繰り返し立ち戻ることになるだろう。