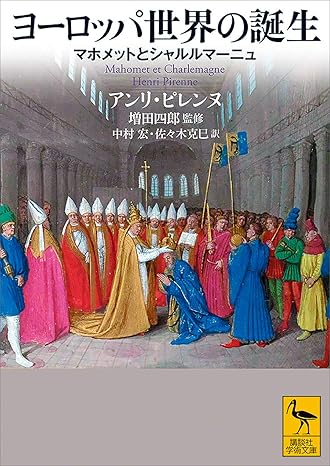 【要約】ヨーロッパの歴史において、ゲルマン民族侵入はこれっぽっちもたいしたことがありません。ドイツ人たちはゲルマン民族の力を不当に過大評価しすぎていますが、完全に間違いです。ゲルマン民族はヨーロッパの文化の発展に対して微塵も貢献していません。ゲルマン民族は単に移動してローマの文化に染まっただけでした。ローマ時代に発展した行政・司法・経済・文学などはゲルマン民族侵入後もそのまま保たれ、学校制度や識字能力も失われていませんでした。たとえば具体的にはメロヴィング朝にはローマの経済・精神生活が色濃く残っていました。
【要約】ヨーロッパの歴史において、ゲルマン民族侵入はこれっぽっちもたいしたことがありません。ドイツ人たちはゲルマン民族の力を不当に過大評価しすぎていますが、完全に間違いです。ゲルマン民族はヨーロッパの文化の発展に対して微塵も貢献していません。ゲルマン民族は単に移動してローマの文化に染まっただけでした。ローマ時代に発展した行政・司法・経済・文学などはゲルマン民族侵入後もそのまま保たれ、学校制度や識字能力も失われていませんでした。たとえば具体的にはメロヴィング朝にはローマの経済・精神生活が色濃く残っていました。
ところがカロリング朝に入ると、まったく様相が変わり、ローマの経済・精神生活は見る影もなくなります。というのは、勃興したイスラム教が地中海を封鎖したことによって古代以来の通商ルートが完全に失われ、ローマ文化を維持するために不可欠だった商品の流通が途絶えた上に、人や情報の交流も断絶したからです。教育は行われなくなり、リテラシーも失われました。西ヨーロッパは商品経済から土地中心経済へと急速に衰退し、教育や行政に教会の聖職者が入り込んできます。カール大帝の戴冠とは、古代ローマ文明が完全に失われ、政治・経済・宗教・教育の閉じたシステムとして中世ヨーロッパが誕生したことの象徴です。
【感想】個人的には、納得感が半端ない。バラバラなピースが全部びしっとあるべきところに嵌まり込むような爽快感を覚える快作だ。具体的なバラバラのピースとは、地中海貿易、ゲルマン民族大移動、西ローマ帝国滅亡?、ボエティウスの学識、学校と識字の消失、ビザンツ帝国の役割、ルネサンスに至るイタリア半島の文化的意味、カール戴冠の意味、中世ヨーロッパにおける教会権力といったところだ。これらの諸要素を見事に一つの世界観に収めてみせる理屈には惚れ惚れとするしかない。まあ、もちろんドイツ人は納得しないだろうし、なるほど細かい実証レベルの話も含めて賛否両論もあろうかというところだが、このピレンヌテーゼに対して個人的には賛の側につきたい。
【個人的な研究のための備忘録】識字と教育
ヨーロッパのリテラシーと教育を考える上で看過ならない記述が大量にあった。
ローマ時代にあんなに栄えていた雄弁術なども含めたリテラシー(及びそれを支えた教育システム)がどのように失われたかは、実はあまりよく分かっていなかった。472年の西ローマ帝国滅亡に伴って文化も同時に失われたかと思いきや、どっこいボエティウスのような知識人がしっかり育っていたりする。ボエティウスがいるということは、6世紀の段階ではまだ教育システムやリテラシーは失われていなかったとみなすしかない。ピレンヌの言うことには合点するしかない。
「知識人と学生たちの憧憬の的であったコンスタンティノープルの影響を見逃してはならない。この都市には就中有名な医学校があったらしく、トゥールのグレゴリウスの著作の多くの個所からそれを立証することができる。」172頁
「文法および修辞学を授ける学校で教養を積んだ元老院貴族の階級が、高級役人の高級源であった。カッシオドルスのごとき、またボエティウスのごとき人物の名前を想起するだけで充分である。そしてこうした人物の死後も、文運の衰退にもかかわらず、同様の状態が続いたのである。」190頁
「こういったすべての役人たちのために学校があったことは明らかである。(中略)ランゴバルド王国においてさえ、学校が存続していた。
西ゴート王国では、文字を書く能力がきわめて広く普及していたから、国王は法典の写本の代価を公定したほどであった。このように読み書きの能力は、行政に関与するすべての人々の間ではごく日常的な事柄だったのである。」192頁
そんなわけで6世紀にはまだ学校システムが存続し、リテラシーも広範に維持されていたわけだが、7世紀半ば以降にイスラム教が西地中海を封鎖することで既存のシステムが崩壊する。
「商業が衰退してしまい、その結果、土地が嘗てないほど経済生活の本質的な基礎になった、と。」357頁
「教養のある人士がもはや聖職者の間にしか求めることができなかったことも事実である。あの危機の間に役人の教育が途絶えてしまったからである。宮宰からして読み書きの術を心得ていなかった。民衆の間に教育を普及させようとしたカール大帝の理想家肌の努力も成功を収めず、宮廷学校の生徒の数も少かった。聖職者と学者が同義語である時代が始まりつつあった。最早ラテン語を解する者の殆どいなくなった王国で、その後の幾世紀にもわたり行政事務にラテン語を用いることを強制した教会が、重要な地位を占めるようになったのはこのためである。この事実のもっている意味をとっくりと考えてみる必要がある。この事実には測りしれない意味がある。ここに出現したものこそ中世の新しい特徴なのである。即ち国家を自分の影響の下におく宗教的階層である。」370頁
「これに対してイタリアではラテン語の存続はより完全なものであった。しかもローマやミラノでは、孤立しながらも若干の学校が引き続いて存続していた。」377頁
世俗的な教育システムが崩壊し、リテラシーが失われ、教会が知識を独占する。地中海との人・モノ・金の流通が途絶した西ヨーロッパの経済と文化は一気に衰退していくが、一方でイタリアへの影響は限定的だったとのことだ。ビザンツ帝国との関係が大きな意味を持つということだろう。そしてこの流れはシチリア王国などを経て、大雑把にはフィレンツェ(ダンテ、ペトラルカ、ボッカッチョ)にも引き継がれていくと考えていいのだろう。
【個人的な研究のための備忘録】ローマ皇帝
この流れを踏まえると、800年のカール戴冠の歴史的意味も明確になる。
西ヨーロッパ(フランク王国カロリング朝)は7世紀半ばに途絶した古代ローマ帝国の文化を復活させることを完全に諦め、あるいは忘却し、新たな経済圏の構築を始める。カール戴冠とは、その断絶を象徴する出来事だ。これ以降は、アルプスを南北に繋ぐルート(後の神聖ローマ帝国)やベルギー・オランダなどの低地地方、ノブゴロドから黒海に抜けてコンスタンティノープルに至るルートなどが重要な地政学的意味を持つことになるだろう。
■アンリ・ピレンヌ、増田四郎監修、中村宏・佐々木克巳訳『ヨーロッパ世界の誕生―マホメットとシャルルマーニュ』講談社学術文庫、2020年<1960年




