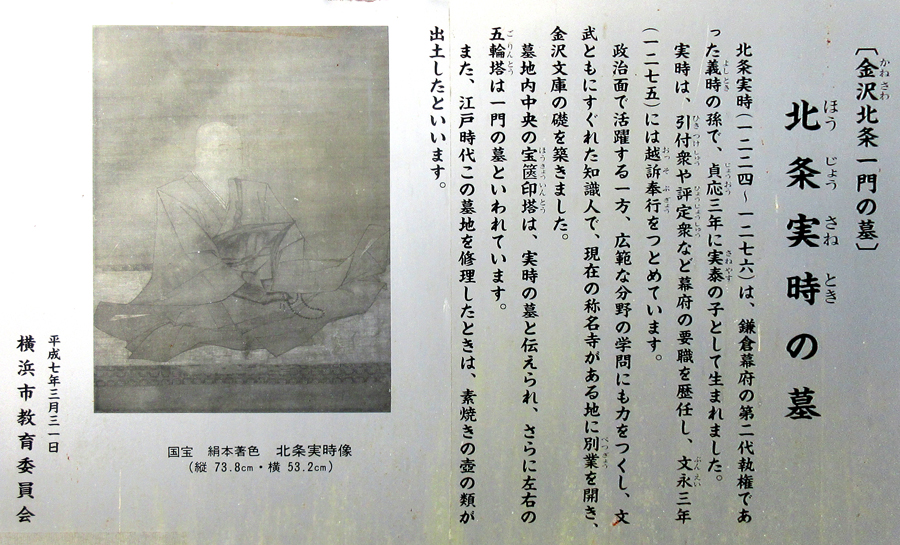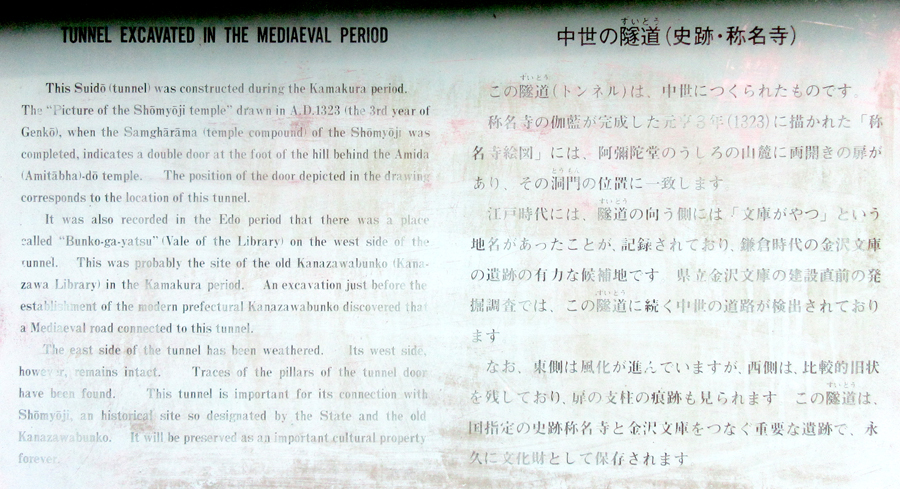【感想書き直し2022/2/12】実は著者が論文の「捏造」をしていたことが、読後に分かった。捏造していたのは他の本ではあるが、本書が捏造から免れていると考える根拠もない。信用できない。読後の感想で、「論文や研究書の類ではズバリと言えず、言葉の定義や歴史的社会的背景を注意深く整理した上で奥歯にものが挟まったような言い方をせざるを得ないような論点を、端的に言葉にしてくれている」と書いたが、それがまさに研究にとって極めて危うい姿勢だということがしみじみと分かった。今後、本書から何か引用したり参考にしたりすることは控えることにする。
【要約】一口にプロテスタンティズムといっても内実は多様で、ルターに関する教科書的理解にも誤解が極めて多いのですが、おおまかに2種類に分けると全体像が見えやすくなります。ひとつは中世の制度や考え方を引き継いで近代保守主義に連なる「古プロテスタンティズム」(現代ではドイツが代表的)で、もうひとつはウェーバーやトレルチが注目したように近代的自由主義のエートスを準備する「新プロテスタンティズム」(現代ではアメリカが代表的)です。前者は中世的な教会制度(一領域に一つ)を温存しましたが、後者は自由競争的に教会の運営をしています。
【感想】いわゆる教科書的な「ルターの宗教改革」の開始からちょうど500年後に出版されていてオシャレなのだが、本書によれば「1517年のルター宗教改革開始」は学問的には極めて怪しい事案なのであった。ご多分に漏れず、ドイツ国家成立に伴うナショナリズムの高揚のために発掘されて政治的に利用された、というところらしい。なるほど音楽の領域におけるバッハの発掘と利用に同じだ。そんなわけで、でっちあげとまでは言わないが、極めて意図的な政治的利用を経て都合良く神話化されたことは、よく分かった。
古プロテスタンティズム=ドイツ保守主義、新プロテスタンティズム=アメリカ自由主義という区分けも、やや図式的かとは思いつつ、非常に分かりやすかった。ウェーバーを読むときも、この区分けの仕方を知っているだけでずいぶん交通整理できそうに思った。
全体的に論点が明確で、情報が整理されていて、とても読みやすかった。が、分かりやすすぎて、逆にしっかり眉に唾をつけておく必要があるのかもしれない。(もちろん著者を疑っているのではなく、自分自身の姿勢として)。
【研究のための備忘録】中世の教会の状態と印刷術
そんなわけで新書ということもあって、論文や研究書の類ではズバリと言えず、言葉の定義や歴史的社会的背景を注意深く整理した上で奥歯にものが挟まったような言い方をせざるを得ないような論点を、端的に言葉にしてくれている。ありがたい。
まず、宗教改革以前(というか「印刷術」以前)の教会の状態を簡潔に説明してくれている本は、実は意外にあまりない。
「また人々は、教会で聖書やキリスト教の教えについての解き明かしを受けていたわけではない。たしかに礼拝に出かけたが、そこでの儀式は、すでに述べた通りラテン語で執り行われていた。一般の人々には何が行われているのかわからない。もちろん人々の手に高価な聖書があるわけではない。仮にあったとしても、聖書はラテン語で書かれているので理解できなかった。」p.28
こういう印刷術前の状況は、「教育」を考える上でも極めて重要だ。たとえば印刷されたテキストそのものが存在しない場合、今日と比較して「朗読」とか「暗誦」という営み、あるいは「声」というメディアの重要性が格段に上がっていく。そういう状況をどれくらいリアルに思い描くことができるか。
で、現代我々がイメージする「教育」は、「文字」というメディアが決定的に重要な意味を持ったことを背景に成立している。もちろん印刷術の発明が背景にある。ルターの見解が急速に広がったのも、印刷術の効果だ。
「ルターの提言は、当時としては異例の早さでドイツ中に広まった。(中略)この当時は、版権があったわけではないから、ヨーロッパ各地で影響力を持つようになっていた印刷所や印刷職人が大変な勢いで提題の複製を開始した。」p.45
「いわゆる宗教改革と呼ばれた運動が、すでに述べた通り出版・印刷革命によって支えられていたことはよく知られている。ルターはその印刷技術による被害者であるとともに受益者でもある。」p.49
これに伴って「聖書」の扱いが大きな問題になる。
「一五二〇年にルターはさまざまな文章でローマの教皇座を批判しているが、その根拠となったのは聖書である。(中略)しかし、すでに触れたようにこの時代の人々のほとんどは聖書が読めなかった。その理由は写本による聖書が高価なため、個人で所有できる値段ではなく、図書館でも盗難防止のために鎖につながれていたほどであったからである。もう一つ、聖書はラテン語訳への聖書がいわば公認された聖書で、知識人以外はそれを自分で読むことはできなかった。
この問題を解決したのは、一つはグーテンベルクの印刷機である。写本ゆえに高価であった聖書が印刷によって比較的廉価なものとなったからだ。しかしなんと言っても重要なのはルターがのちに行う聖書のドイツ語訳である。(中略)これは画期的なことであった。聖書を一般人も読めるのである。文字が読めなくても朗読してもらえば理解できる。」pp.58-59
本書では「近代」のメルクマールを人権概念や寛容の精神に求めていて、もちろんまったく問題ないが、一方でメディア論的にはそういう法学・政治学的概念にはまったく関心を示さず、印刷術の発明による「知の流通量増加」が近代化を促した決定的な要因だと理解している。「教育」においても、印刷されて同一性を完璧に担保されたテキストが大量に流通したことの意味は、極めて大きい。
【研究のための備忘録】フスとの関係
ルターの主張と宗教改革の先輩ボヘミアのヤン・フスの主張との類似性は明らかだと思うが、教育思想史的にはコメニウスとの関係が気になるところだ。フス派だったコメニウスにはどの程度ルター(あるいはプロテスタンティズム)の影響があるのか。本書で説明される「リベラリズムとしてのプロテスタンティズム」の説明を踏まえると、コメニウスの主張にも反映していないわけがないようにも思える。(先行研究では、薔薇十字など神秘主義的な汎知学との親和性が強調されているし、そうなのだろう。)
「エックは、ルターがフスの考えを一部でも支持して、フスは正しかったと言ってくれれば、それでこの二人は同罪だと指摘すべく準備していたのだ。エックは事前にルターの考えを精査し、ルターとフスの考えの類似性を感じ取っており、また内容それ自体で勝負しようとしているルターを陥れるとしたら、この点だと確信していたのである。」p.54
【研究のための備忘録】中世と近代
で、歴史学的な問題は「中世と近代の境界線」だ。はたして「宗教改革」は中世を終わらせて近代を開始したのか。本書は懐疑的だ。
「トレルチの有名な命題は、「宗教改革は中世に属する」というものである。ルター派もジュネーブのカルヴァンの改革もそれは基本的に中世に属し、「宗教改革」という言い方にもかかわらず、教会の制度に関しては社会史的に見ればカトリックとそれほど変わらないのだという。」p.107
「近代世界の成立との関連で論じられ、近代のさまざまな自由思想、人権、抵抗権、良心の自由、デモクラシーの形成に寄与した、あるいはその担い手となったと言われているのは、カトリックやルター派、カルヴィニズムなど政治システムと結びついた教会にいじめ抜かれ、排除され、迫害を受けてきたさまざまな洗礼主義、そして神秘主義的スピリチュアリスムス、人文主義的な神学者であったとするのがトレルチの主張である。」pp.108-109
ということで、本書は中世の終わりをさらに後の時代に設定している。それ自体は筋が通っていて、なるほどと思う。とはいえ、メディア論的に印刷術の発明をメルクマールに設定すると、いわゆる「宗教改革」は派生的な出来事として「知の爆発的増加」の波に呑み込まれることになる。このあたりは、エラスムス等人文主義者の影響を加味して具体的に考えなければいけないところだ。
【研究のための備忘録】市場主義と学校
教会の市場化・自由化・民営化を、学校システムと絡めて論じているところが興味深かった。
「「古プロテスタンティズム」の場合には、国家、あるいは一つの政治的支配制度の権力者による宗教史上の独占状態を前提としているのに対して、「新プロテスタンティズム」は宗教市場の民営化や自由化を前提としているという点である。」p.112
「それ(古プロテスタンティズム:引用者)はたとえて言うならば、公立小学校の学校区と似ているかもしれない。」p.113
「その点で新プロテスタンティズムの教会は、社会システムの改革者であり、世界にこれまでとは違った教会の制度だけではなく、社会の仕組みも持ち込むことになった。それは市場における自由な競争というセンスである。その意味では新プロテスタンティズムの人々は、宗教の市場を民営化、自由化した人々であった。」p.117
現代日本(あるいは世界全体)は、いままさに学校の市場化・自由化・民営化に向けて舵を切っているが、コミュニティ主義からの根強い反対も続いている。なるほど、これはかつて教会の市場化・自由化・民営化のときにも発生していた事態であった。つまり、教会改革の帰結を見れば、学校改革の帰結もある程度予想できるということでもある。
【研究のための備忘録】一と多
本書の本筋とは関係ないが、「一と多」に関する興味深い言葉があったのでメモしておく。
トレルチ講演原稿の結び「神的な生は私たちの現世での経験においては一ではなく多なのです。そしてこの多の中に存在する一を思うことこそが愛の本質なのです」p.208
カトリックの思想家ジャック・マリタンの発言との異同を考えたくなる。
【要約】日本の従来の学校教育で行ってきた集団一斉教授はオワコンになりつつあります。教師や学校は、今こそ新しい教育にチャレンジするべき時です。時期学習指導要領の目玉キーワードになるであろう「個別最適な学び」と「協働的な学び」について、具体的な授業実践を土台にしながら解説します。子どもたちの「学びたい」という気持ちを信じ、教師が教科の本質を捉えた上で丁寧に学習環境を整えれば、子どもたちは本来の「有能な学び手」の力を発揮します。教師は、従来の一斉授業観を放棄し、新しい時代の新しい学びにふさわしい新しい役割を担うべきです。ICTはへっちゃらで使いこなしましょう。