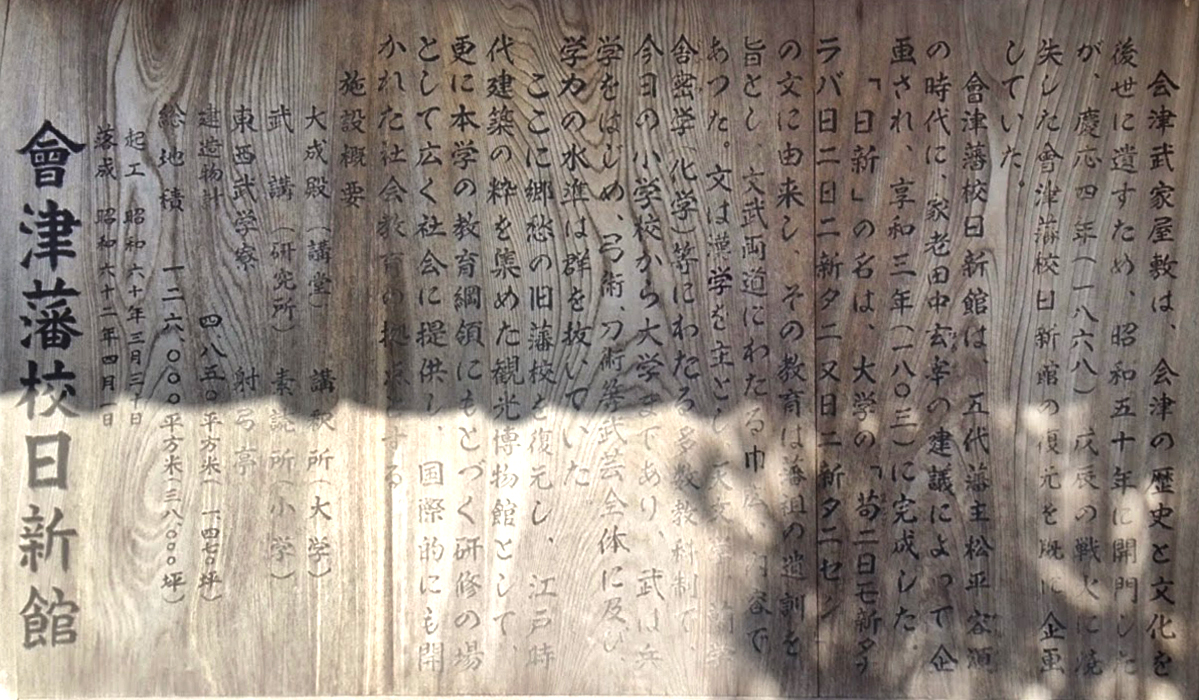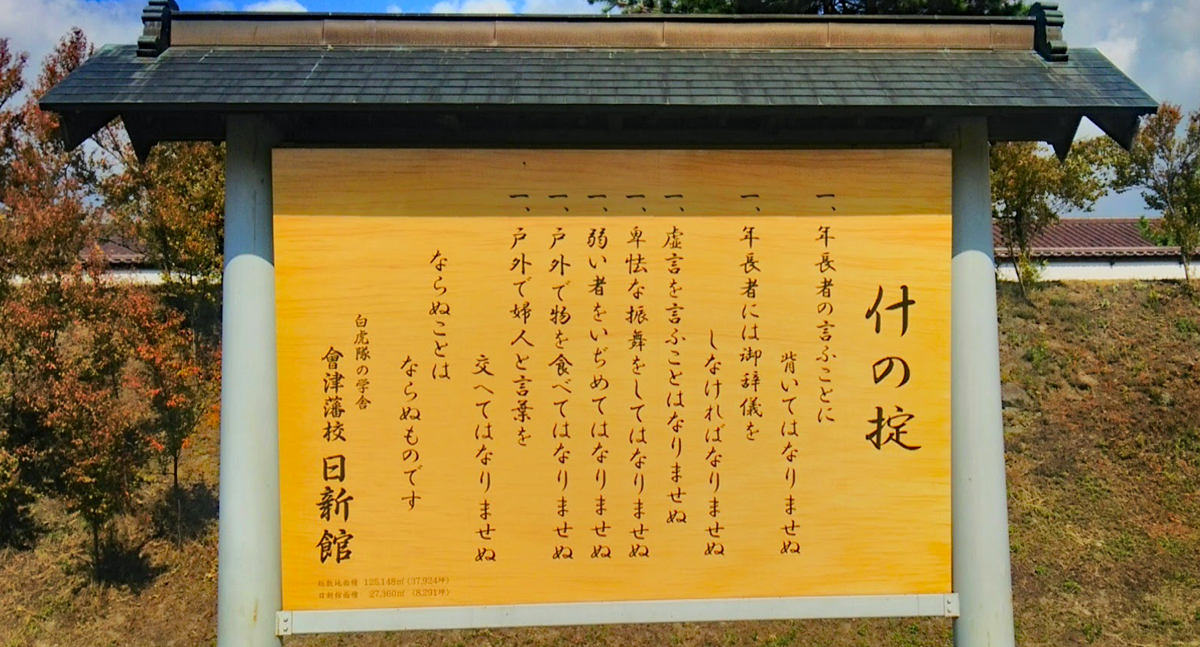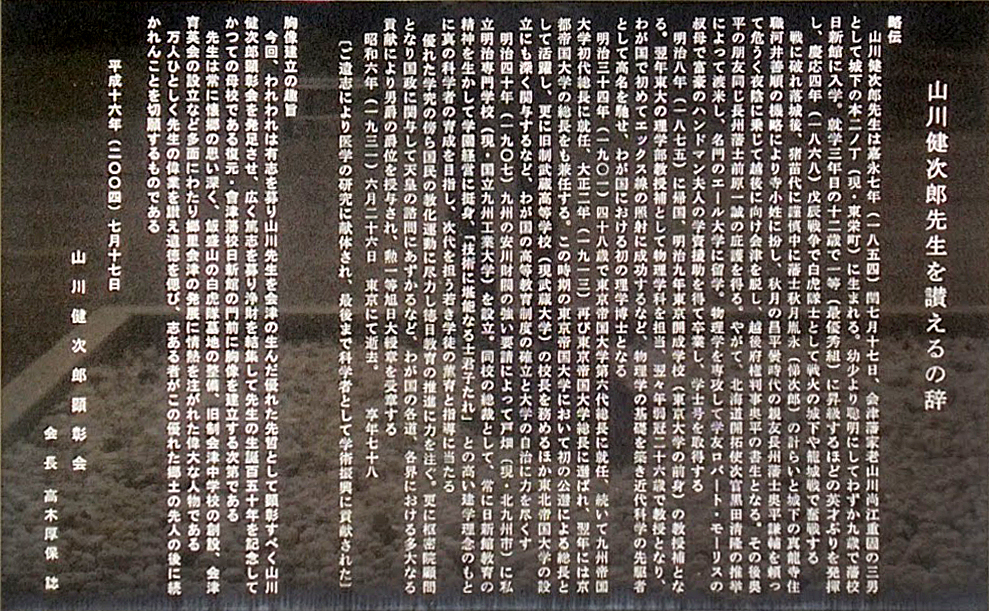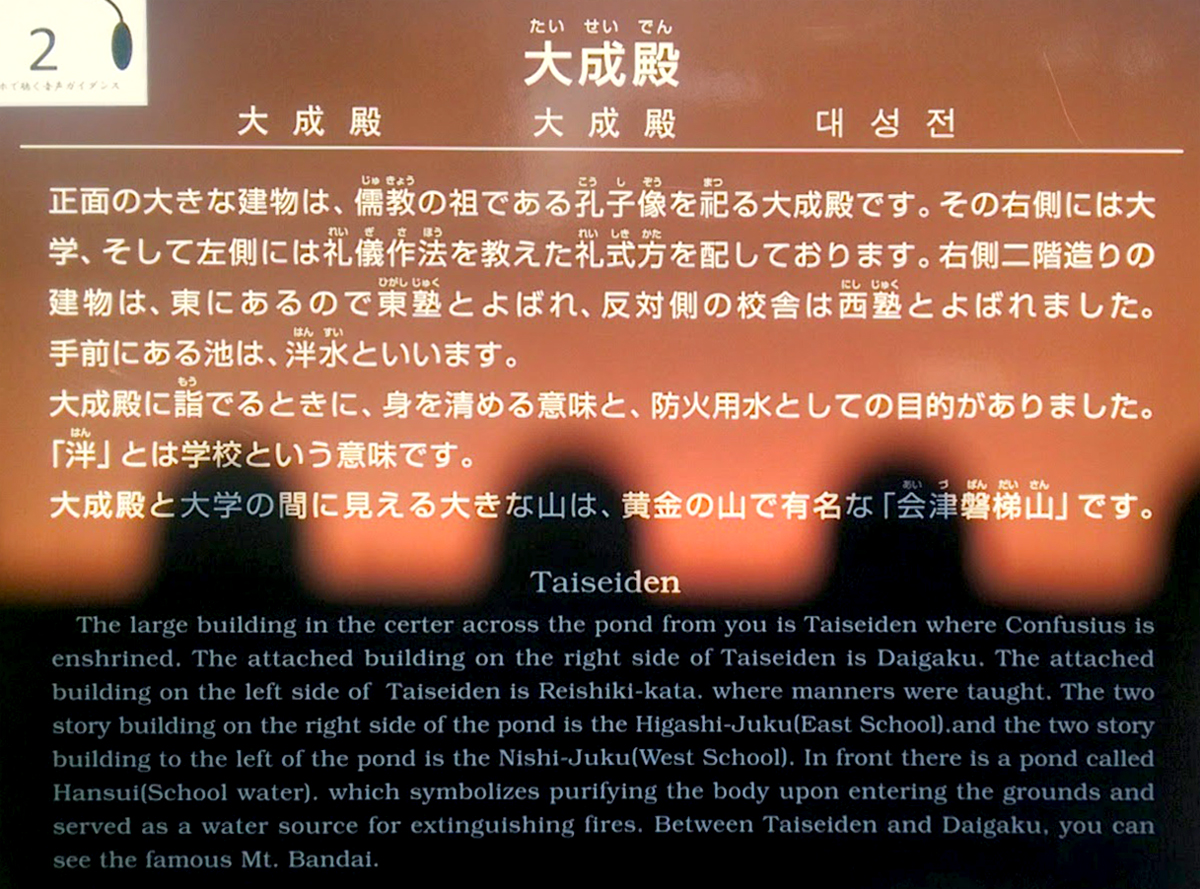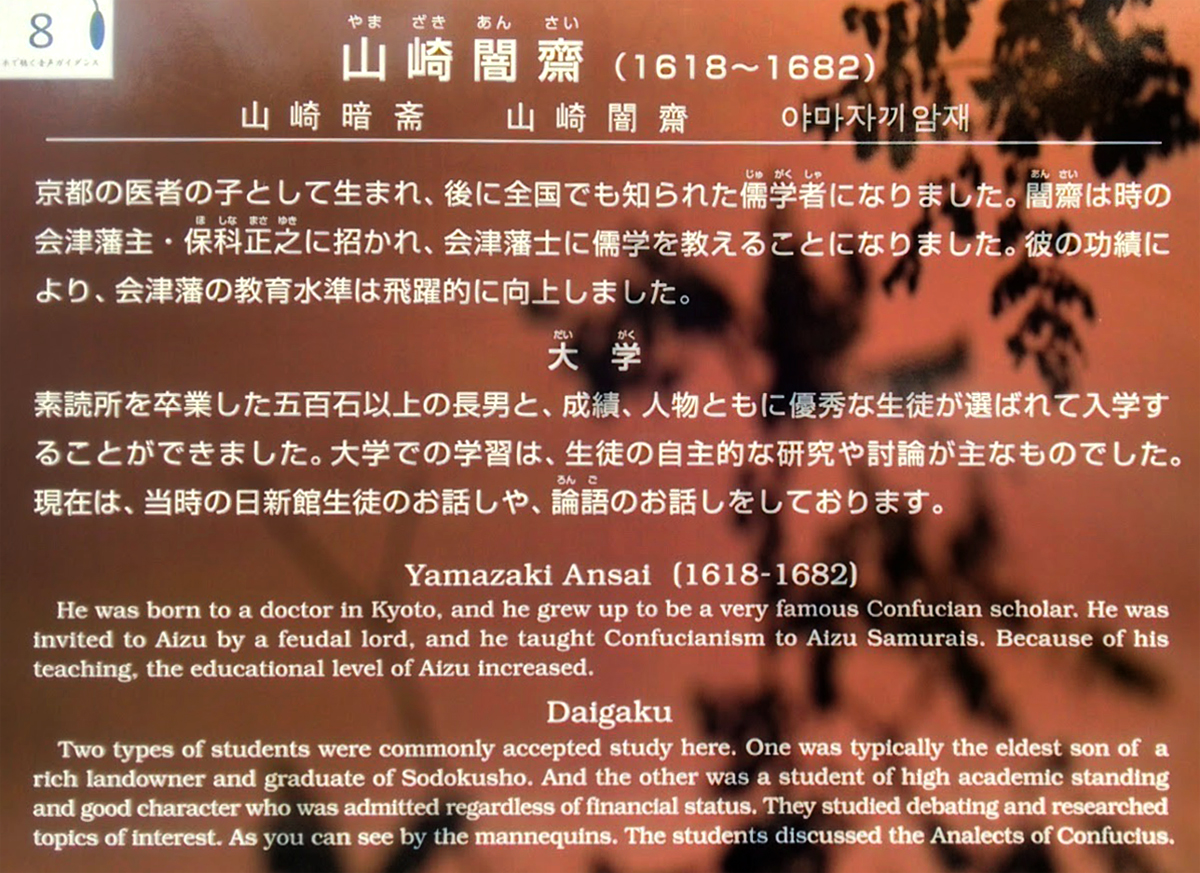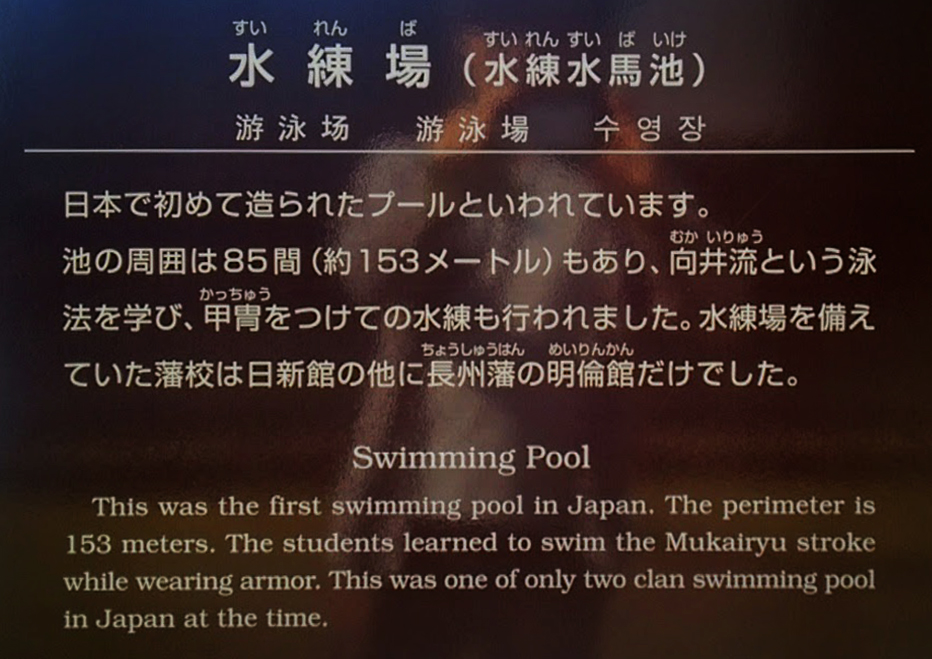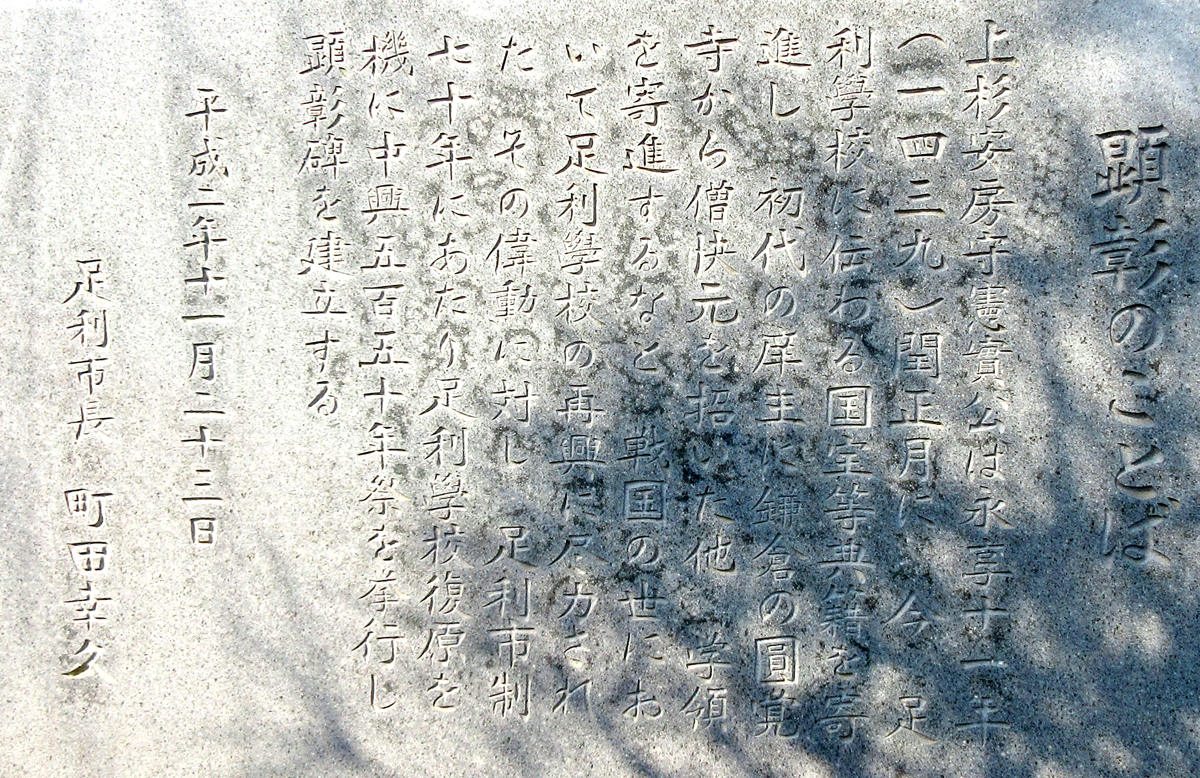2018年2/11にお茶の水女子大学で行われた日本保育学会「関東地区研究集会」に行ってきました。汐見稔幸先生の講演を聞きましたが、保育だけに限らず、新学習指導要領の背景を理解する上でも有益な内容だったと思うので、私が理解したことを書き留めます。
法令の改定を、世界史的な流れで理解する
研究集会のテーマは、「保育所保育指針」「幼稚園教育要領」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」(以下、三法令)の改訂に関してでした。そして汐見先生の話は、会場が期待していたような(?)具体的な保育実践に関わるものではなく、抽象的な理論の話でした。が、抽象的な理論の話でなければならなかった本質的な理由があったと思います。三法令改定の意味は、お上が命令するから逐条解釈するのだという姿勢では理解できず、世界史的な背景を踏まえて理解しなければならないというわけです。
この「世界史的な流れ」というのは、具体的には「20世紀型の教育から21世紀型教育へ」という動きです。この大きな流れを把握しておかないと、三法令の改定の意味がわからないということです。そして、この「20世紀型の教育から21世紀型教育へ」という世界史的動向は、いったん「19世紀型教育から20世紀型教育への転換」を振り返ると、分かりやすくなります。この19世紀型から20世紀型への教育の転換のことを、教育史では「新教育運動」と呼んでいます。
新教育運動:19世紀型教育から20世紀型教育へ
新教育運動を推進した人物として、教科書にはデューイ、キルパトリック、モンテッソーリといった名前が登場します。それぞれ個性的な教育を展開しましたが、古典的な教育とは異なる観点が共通して6点ほど挙げられます。
(1)子ども中心主義:興味関心をベースに
(2)活動主義:なすことによって学ぶ
(3)生活主義:生活の充実を目標とし、生活の中で豊かに学ぶ
(4)ホーリズム:人格全体、特に感情や自我の育ちを重視
(5)性善説・向善説:プロテスタンティズムの子ども観を転換
(6)民主主義の担い手育て:自分で自分を統治する教育
しかしこうした新教育運動の試みは、教養中心で主知主義的な19世紀型教育からは疑惑の目で見られることになります。20世紀の教育は、新教育と詰め込み教育が葛藤する100年となります。
20世紀教育の展開と限界
実際の20世紀の教育は、新教育が目指したものにはなりませんでした。現実には、産業化や工業化に必要な人材を大量に養成する教育となりました。産業至上主義に対応して選抜システムが洗練され、知能指数や学歴が信仰されるようになり、主知主義的で知識中心主義の教育が蔓延し、企業の中で駒として有能に働く能力の育成が追求されることになります。
こうした資本主義に適合する教育に対抗して、マカレンコ等の共産主義的教育が登場しましたが、それは結局は全体を優先する集団主義教育に過ぎませんでした。資本主義教育と共産主義教育の対立は、全体を優先して「個」を犠牲にするという意味では、結局は主知主義内での争いに過ぎませんでした。
しかし、20世紀後半に至り、こうした教育の限界が認識されるようになります。たとえば現在では、民間企業が率先して20世紀型教育を批判しています。20世紀型教育は指示された作業をこなす能力や枠に縛られたノウハウを育てることはできるものの、それ以上の価値を創造する力が弱く、民間から不満が噴出しています。国民の側も、不登校やいじめ、失業問題や環境問題等、教育が機能不全を起こしていることに不満を表明しています。同時に、情報機器の発展等によって学校以外の様々な教育機関が進展し、学校の相対的位置が低下しています。
こうして、20世紀型教育の限界が認識され、21世紀型教育への転換が叫ばれるようになっているわけです。
21世紀を見通したときに出てくる課題
さて、21世紀型教育が必要となるのは、これまでの教育では対応できないような課題に人類が直面しているからです。新たな課題は、主に3つあります。
(1)解決策がまだ見つかっていないが、解決していかないと地球自体がもたないという深刻な問題を解決するための力の養成。
(2)価値観の多様化と地球規模で人々が交流する時代にふさわしい知性の涵養。
(3)AI、ロボット、コンピュータがあらゆる生活に入り込んで情報処理をしてしまう社会での人間らしさの涵養。
これらに加えて、日本特有の課題もあります。
(1)日本の教育は、「個の充実」、特に「主体であること」の自覚と能力育成が弱く、組織の一員になるための教育へと偏っている。
(2)市民になる力の涵養、民主主義の担い手としての自覚とその力の教育の弱く、シティズンシップ教育が不足している。
20世紀教育の限界を突破する方策
こうした限界を突破するために、3つの方策が考えられます。
(1)すでに20世紀初頭に議論し実践してきた新教育運動の知恵からもう一度学び、必要な修正をしながら課題に対応する。
(2)この100年の実践、生活主義を引き継いで発展させる。
(3)シティズンシップ教育など新たな課題に対応する。
方策(1)新教育運動の知恵
倉橋惣三らが世界新教育運動から学び取った知恵を、もう一度振り返ってみると、それらが21世紀的教育が求める「非認知能力」や「社会情動的スキル」と通じていることに気がつきます。新教育運動の人格主義的性格は、感情・意志・主体性等の育てを重視しており、これは21世紀教育が追求する「心情、意欲、態度」とリンクしています。社会情動的スキルという考えには、心理学や社会心理学における情動研究の進展が反映しており、これがアタッチメントの再評価に繋がってきています。これらが、三法令改定における「資質・能力」という概念に反映しています。
三法令が言う「資質・能力」という概念は、倉橋惣三の仕事をしっかり振り返ることで、明確になっていきます。倉橋の仕事を学び直し、引き継いで、必要な修正を施しながら発展させていくことが、21世紀型教育の確立に結びつきます。
方策(2)生活主義の引き継ぎ
生活の中で学ぶという考えを精緻にしたのはデューイで、それを日本に紹介したのは宮原誠一の仕事です。倉橋惣三が言う「生活を、生活で、生活へ」も、この考えに共鳴しています。
「生活」とは英語では「life」ですが、「life」とは「生命」でもあり「日々の営み」でもあり「人生」でもあり、それらを串刺しにした概念です。人間は生活=いのちの営みを充実させることで必要な文化を身につけ、教育はそれを手伝い、ときには少しコントロールし、社会に必要な市民として子供を育てる営みと言えます。
生活主義の根底には、子供は自ら育っていこうとする存在だという子ども観があります。それを宮原は「形成」という独特の言葉で総称しました。一方で「教育」のことを、「形成」への関わりであり、その首尾良い具体化のための援助であると定義しました。現代の日本では、形成を具体化するための援助のことを「環境づくり」と呼んで、環境を通じた教育を目指しています。倉橋惣三が言う「保育の四層構造=自己充実、充実指導、誘導保育、教導保育」も同じことを言っているわけです。
方針(3)シティズンシップ教育
新たな教育課題として特に市民教育が挙げられますが、具体的な実現を目指して導入されたのが総合教育でした。前回の学習指導要領改訂では総合教育が後退したように見えますが、今回の改訂は総合教育の再登場であり、さらに言えば乳幼児期からの開始という特徴があります。乳幼児期教育は、シティズンシップ教育という観点から小学校以降の総合教育と結びついていくことで大きな意義を発揮すると言えます。
総合教育を成功させるためには、教育の3つの層の統合を考えなければいけません。すなわち(1)個別知(2)実践知(3)人格知の統合されたものです。この統合を目指すために必要となるのが、「主体的・対話的で深い学び」というものです。これを単に「教える方法」だけに矮小化せず、「目的」そのものであることを理解する必要があります。
保育学会の役割
というわけで、保育という営みを、生涯にわたる教育という大きな枠の中に積極的に位置づけていくことが重要になってきます。保育とは乳幼児教育学に他なりません。この大きな背景を見失っては、具体的な保育の方針も見えてきません。
こういう観点を得ると、たとえば保育の五領域についても考え直していく必要が見えてきます。たとえば具体的には、ニュージーランドの教育指針「テファリキ」等と比較したとき、日本の五領域には将来の市民を育成していくという視点が弱いのではないかと思われます。生涯にわたる学習という視点が乏しいということでしょう。
学会は、そうしたことを議論していく場です。ラディカルな議論をしていきましょう。
そんなわけで、単に三法令の逐条理解なんかしても大した意味はありません。改訂の背景にある時代の流れを大きな観点から理解していかなくてはいけません。その理解を促進するためには、20世紀の新教育が目指したものを振り返って学び直すことが極めて重要になってくるわけです。
個人的感想
学習指導要領本文には、20世紀初頭の新教育運動について振り返るような記述はまったくありません。あるいは、宮原誠一や倉橋惣三が行った仕事をリスペクトしているような記述もまったくありません。だから、学習指導要領だけ読むと、先哲の仕事をいったいどう考えているのか、何を引き継ぎ何を発展させるかという問題意識があるのかどうか、たいへん不安になるわけです。
が、汐見先生の話を聞く限りでは、先哲の仕事を十分に踏まえ、その重要性を理解した上で、さらに新たな課題を見据えて修正し、学習指導要領なり保育所保育指針が構成されているだろうことが伺えます。逆に言えば、こういう話がなければ、学習指導要領や保育所保育指針が本当に何を目指しているかは見えてこないように思います。そういう意味で、この講演の内容は、逐条解説なんかよりも、はるかに本質的な理解に繋がる内容だったと思います。
(以上、あくまでも私が講演を聴いて理解し考えたことを私の観点からまとめたものであって、誤解があった場合は汐見先生の責任でないことは書き添えておきます。)